
この記事は3部構成です
1)事業計画書の作り方|事業コンセプトとは
→ https://hojyokin-hiroba.com/business-concept-guide/
2)事業計画書の作り方|事業計画書のサンプル&雛形解説
→ https://hojyokin-hiroba.com/business-plan-writing-guide/
3)事業計画書の作り方|「ビジョン・目標」の作り方と考え方
→ https://hojyokin-hiroba.com/business-plan-vision-goals/
はじめての事業計画書作成ガイド ✍️
飲食店(ベジリアンカフェ)の事例から学ぶ、実践的な事業計画書の書き方
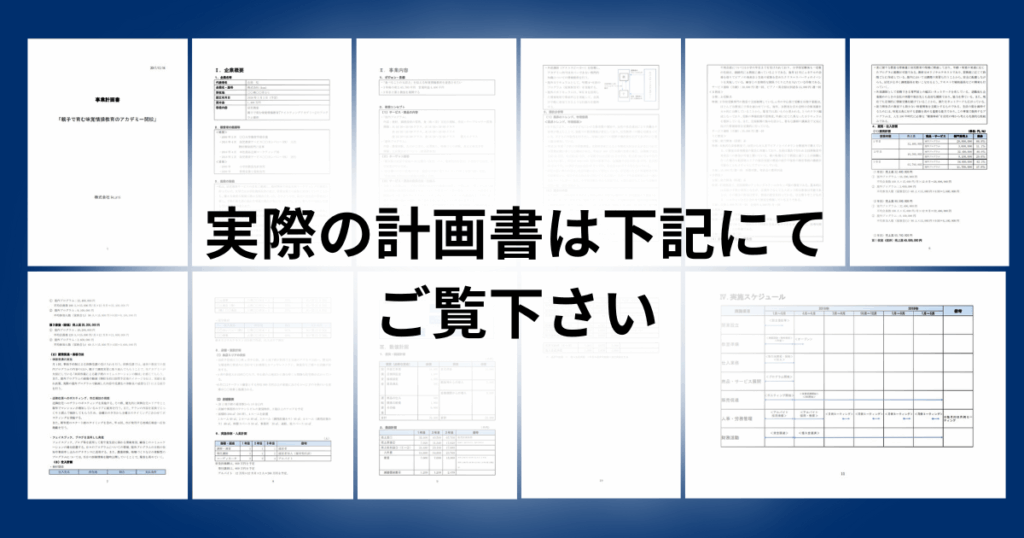
出典元 J-Net21(中小企業基盤整備機構)
計画書閲覧はこちら→ https://j-net21.smrj.go.jp/startup/manual/list5/t5drrv0000007l9j-att/case3.pdf
事業計画書は、創業や資金調達、事業の方向性を明確にするための重要なツールです。ここでは、J-Net21で公開されている事業計画書の構成をもとに、各セクションで何をどう書けばよいかを、初心者にもわかりやすく解説します。
📘 表紙
事業計画書の「表紙」は、第一印象を決める重要なパートです。金融機関や支援機関、投資家などが最初に目にする部分であり、信頼感・期待感・プロフェッショナリズムを伝える役割があります。以下に、表紙作成時の注意点とアドバイスを詳しく解説します。
🧭 表紙に記載すべき基本項目
下記のような項目から提出先や状況に応じて記載内容を取捨選択して下さい。
| 項目 | 内容 | アドバイス |
|---|---|---|
| 事業計画書のタイトル | 事業の特徴やコンセプトを簡潔に表現 | 「〇〇を提供する△△カフェ」など、具体性と魅力を両立させる |
| 企業名・屋号 | 法人名または個人事業主の屋号 | 仮名でも可。設立予定の場合は「(予定)」と記載 |
| 代表者名 | フルネームで記載 | 読みやすく、肩書き(代表取締役など)も添えると丁寧 |
| 所在地 | 事業所の住所 | 予定地でもOK。市区町村まで記載すると信頼感が増す |
| 設立年月日 | 実際または予定の設立日 | 「2025年12月1日(予定)」など明記 |
| 資本金 | 金額を明記 | 「500万円」など。未定の場合は「未定」と記載 |
| 事業内容 | 一言で事業の概要を説明 | 「地元野菜を使った料理と自家焙煎珈琲を提供するカフェ」など |
✨ 表紙作成のポイントと注意点
1. タイトルは「魅力」と「わかりやすさ」が命
- 抽象的な表現よりも、具体的なサービスや価値が伝わる言葉を使いましょう。
- 例:「地域の人が集まる自家焙煎珈琲と野菜料理のカフェ」など。
2. フォーマットはシンプルかつ整然と
- フォントは明朝体やゴシック体など、読みやすく信頼感のあるものを選びましょう。
- 余白を適度に取り、項目ごとに改行して見やすく配置します。
3. ロゴやデザインは必要?
- ロゴがある場合は小さく添えるとブランディング効果があります。
- 派手すぎる装飾は避け、ビジネス文書としての品位を保ちましょう。
4. PDF化して提出する場合の注意
- 表紙は1ページ目に独立させるのが基本です。
- ファイル名は「事業計画書_ベジリアンカフェ株式会社.pdf」など、誰が見ても内容がわかるように。

💡 初心者向けアドバイス
事業内容は一言で言えるように練りましょう。これはプレゼンや面談でも役立ちます。
「表紙は名刺」と考えましょう。あなたの事業の顔です。
書き方に迷ったら、他の事業計画書の表紙を参考にしてみるのもアリです。
1. 企業概要
企業概要は、事業の骨格と経営者の人間性を伝える重要なセクションです。数字や事実だけでなく、あなたの想いや背景を丁寧に記すことで、読み手に「この人なら応援したい」と思ってもらえる可能性が高まります。
1-1 企業名等
この項目では、事業の基本情報を整理して記載します。
✅ 記載すべき内容
- 企業名・屋号:法人名または個人事業主の屋号。設立前なら「(予定)」と記載。
- 代表者名:フルネームで記載。肩書き(代表取締役など)も添えると丁寧。
- 所在地:事業所の住所。市区町村まで記載すると信頼感が増します。
- 設立年月日:予定でもOK。「2025年12月1日(予定)」など。
- 資本金:金額を明記。「500万円」など。未定の場合は「未定」と記載。
- 事業内容:一言で事業の概要を説明。「地元野菜と自家焙煎珈琲を提供するカフェ」など。
💡 アドバイス
- 読み手が一目で「どんな事業か」「どこでやるのか」がわかるように、簡潔かつ具体的に書きましょう。
- 事業内容は、後の詳細説明につながる“予告編”のような位置づけです。
1-2 経営者の経歴等
ここでは、経営者のバックグラウンドを紹介します。事業との関連性がある経験やスキルを中心に記載しましょう。
✅ 記載すべき内容
- 学歴・職歴:特に事業に関連する職歴(例:カフェ勤務歴)は詳しく。
- 資格:食品衛生責任者、調理師免許、野菜ソムリエなど、事業に役立つ資格を記載。
💡 アドバイス
- 「なぜこの事業を自分がやるのか」の根拠になる部分です。経験やスキルが事業にどう活かされるかを明確にしましょう。
- 職歴は「いつ・どこで・何をしていたか」を時系列で書くと読みやすくなります。
1-3 起業の動機
この項目では、事業を始めるに至った背景や想いを記載します。読み手の共感を得るために、個人的なエピソードも交えて構いません。
✅ 記載すべき内容
- 起業のきっかけ:どんな経験や気づきがあったか。
- 地域とのつながり:地元への貢献意欲などがあると好印象。
- 事業へのこだわり:商品やサービスに対する想い。
💡 アドバイス
- 感情や人間味が伝わるように書くと、読み手の印象に残ります。
- 「自分だからこそできる事業」という独自性を意識しましょう。

💡 初心者向けアドバイス:企業概要は「信頼」と「人柄」を伝える場
企業概要は、事業の骨格と経営者の人間性を伝える重要なセクションです。数字や事実だけでなく、あなたの想いや背景を丁寧に記すことで、読み手に「この人なら応援したい」と思ってもらえる可能性が高まります。
2. 事業内容
ここでは、事業の魅力を伝えると同時に、「本当にできるのか?」という疑問に答える部分でもあります。理想だけでなく、現実的な根拠や仕組みを丁寧に説明することで、読み手の信頼を得ることができます。
2-1 ビジョン・目標
✅ 記載すべき内容
- 事業を通じて実現したい理想像(例:「地域の人が集まる居心地の良い空間を提供したい」)
- 数値目標(売上高、利益、顧客数など)
💡 アドバイス
- 「なぜこの事業をやるのか」「どんな未来を目指すのか」を明確にしましょう。
- 数値目標は、後の損益計画と連動させることで信頼性が高まります。
- 理想論だけでなく、現実的な達成可能性を感じさせるバランスが重要です。

事業計画の策定に必要となるビジョンや目標設定。
こちらについて更に詳しく知りたい方はこちらの記事もご活用下さい。
→ https://hojyokin-hiroba.com/business-plan-vision-goals/
2-2 事業コンセプト
2-2-1 商品・サービスの内容
✅ 記載すべき内容
- 提供する商品・サービスの種類と特徴
- 他社と差別化できるポイント(例:自家焙煎、地元野菜、野菜スイーツなど)
💡 アドバイス
- 「何を提供するのか」だけでなく、「どうしてそれが魅力的なのか」まで書きましょう。
- 商品のこだわりや開発背景、素材の選定理由なども加えると説得力が増します。
- 写真やイラストを添えると、視覚的にも伝わりやすくなります(別添資料でもOK)。
2-2-2 ターゲット顧客
✅ 記載すべき内容
- 年齢層、性別、ライフスタイル、価値観など
- 地域性や行動パターン(例:子育て世代の女性、駅前でランチを探す人)
💡 アドバイス
- 「誰に売るか」が明確でないと、商品や販促の方向性がブレてしまいます。
- ペルソナ(理想的な顧客像)を1〜2人設定すると、より具体的な戦略が立てやすくなります。
- 地域の人口構成や消費傾向など、統計データを活用すると説得力が増します。
2-2-3 サービス・商品の提供方法・仕組み
✅ 記載すべき内容
- 商品の選び方、注文方法、体験の流れ
- 情報発信の工夫(例:珈琲マップ、野菜の紹介、SNS活用)
- 店内の雰囲気づくりや接客スタイル
💡 アドバイス
- 「どうやって提供するか」は、顧客満足度やリピート率に直結します。
- 体験型の仕組み(選ぶ楽しさ、知る喜び)を盛り込むと、印象に残りやすくなります。
- SNSやブログなど、オンラインでの接点も忘れずに。情報発信は集客の要です。
2-3 現状分析等
2-3-1 業界のトレンド、市場規模
✅ 記載すべき内容
- 業界全体の動向(成長性、消費者ニーズの変化)
- 市場規模や消費傾向(例:カフェ市場は1兆円規模、喫茶代の支出増加)
💡 アドバイス
- 最新の統計や業界レポートを引用し、出典を明記しましょう。
- 自社の事業がそのトレンドにどう乗っているかを示すと、説得力が増します。
- 「今この事業を始める理由」が明確になるように構成しましょう。
2-3-2 競合の状況
✅ 記載すべき内容
- 出店予定地周辺の競合店の特徴と比較
- 価格帯、客層、雰囲気、メニューなどの違い
💡 アドバイス
- 実際に競合店を訪問し、体験した感想を交えるとリアルな分析になります。
- ポジショニングマップ(価格×品質など)を使うと、差別化ポイントが視覚的に伝わります。
- 「競合がいるからこそ勝てる理由」を明確にしましょう。
2-3-3 自社・事業の強み・優位性
✅ 記載すべき内容
- 商品・サービスの独自性
- 経営者のスキルや人脈、仕入ルートなど
- 顧客体験や空間づくりのこだわり
💡 アドバイス
- 「他にはない価値」が何かを明確にしましょう。
- 技術力、素材、接客、空間、情報発信など、複数の視点から強みを整理すると効果的です。
- 自社の強みがターゲット顧客のニーズと一致していることを示すと、説得力が倍増します。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
2-4 販売・仕入計画
ここでは、事業が「ちゃんと売れて、ちゃんと回る」ことを証明する必要があります。数字の根拠と、運営の仕組みを丁寧に説明することで、読み手は「この事業は現実的だ」と納得してくれます。
2-4-1 販売計画
✅ 記載すべき内容
- 年度ごとの売上目標(1年目〜3年目が一般的)
- 時間帯別・商品別などの売上構成
- 客単価、席数、回転率、営業日数などの根拠
💡 アドバイス
- 売上は「希望」ではなく「計算」で示しましょう。以下のような式が基本です:
売上=席数✕客単価✕回転数✕営業日数 - 時間帯別に分けることで、営業戦略の具体性が伝わります(例:ランチタイムが売上の中心)。
- 客単価や回転率は、競合店の実績や自店のコンセプトに基づいて設定しましょう。
- 3年目までの成長を見込む場合は、根拠(販促強化、席数増加など)を添えると信頼性が高まります。
2-4-2 販売促進・集客方法
✅ 記載すべき内容
- 顧客を呼び込むための施策(オンライン・オフライン両方)
- ターゲット層に響く工夫(例:子育て世代向けの情報発信)
- 実施時期や頻度、連携先などの具体性
💡 アドバイス
- 販促は「誰に」「何を」「どう伝えるか」の3点セットで考えましょう。
- オープン時の集客は特に重要。フライヤー配布やSNS告知は必須です。
- 地元とのつながりを活かした紹介(例:野菜の生産者紹介)は、共感を呼びやすく、リピーター獲得にもつながります。
- SNSは「情報発信」だけでなく「関係構築」の場。コメント返信やイベント告知など、双方向の活用を意識しましょう。
2-4-3 仕入計画
✅ 記載すべき内容
- 主な仕入先と所在地
- 仕入割合と支払条件(例:末締め翌25日払い)
- 安定供給の仕組み(契約、複数ルートなど)
💡 アドバイス
- 食材や原材料の仕入は、品質・価格・安定性の3点が重要です。
- 地元農家との契約は、地域貢献にもつながり、販促にも活用できます。
- 支払条件は資金繰りに直結するため、無理のない範囲で設定しましょう。
- 複数の仕入先を持つことで、リスク分散になります(例:天候不良時の代替ルート)。
2-5 店舗・施設計画
ここでは、事業が「どこで」「どんな空間で」行われるかを具体的に示すことで、読み手に事業のリアリティと魅力を伝えます。立地の選定理由や店舗の特徴が、ターゲット顧客のニーズと一致していることを示すと、事業の成功可能性が高く評価されます。
2-5-1 出店エリアの状況
✅ 記載すべき内容
- 出店予定地の人口構成、世帯数、年齢層などの基本情報
- 地域の開発状況や生活環境(例:駅前再開発、子育て支援施設の充実)
- ターゲット顧客層がその地域に多く住んでいるかどうか
- 周辺エリアからの集客可能性(例:隣接地区の買い物客)
💡 アドバイス
- 地域との親和性は、事業の成功可能性を左右する重要な要素です。
- 行政の施策(子育て支援、移住促進など)を調べて記載すると、説得力が増します。
- 地元住民の声やニーズ(例:「おしゃれなカフェがない」)を拾って記載すると、共感を得やすくなります。
- 地域の統計データ(市区町村のHP、国勢調査など)を活用して、客観的な根拠を添えましょう。
2-5-2 店舗概要
✅ 記載すべき内容
- 店舗の立地(駅からの距離、周辺施設など)
- 建物の構造(築年数、階数、材質など)
- 店舗の広さ(延べ床面積、厨房面積など)
- 席数とレイアウト(テーブル数、座席配置)
- 居抜き物件か新築か、改装の有無
💡 アドバイス
- 店舗の物理的条件は、営業スタイルや収益性に直結します。
- 居抜き物件を活用する場合は、コスト削減のメリットを明記しましょう。
- 席数は販売計画の根拠になるため、正確に記載することが重要です。
- 店舗の雰囲気づくり(例:北欧風の家具で統一)なども記載すると、ブランドイメージが伝わりやすくなります。
- 周辺施設(学習塾、雑貨店など)との相乗効果もアピールポイントになります。
👥 2-6 実施体制・人員計画セクションの書き方と実践アドバイス
ここでは、事業を実際に動かす「人」の配置と役割を明確にすることで、事業の実行力と持続可能性を示します。読み手に「このメンバーなら安心して任せられる」と思ってもらえるよう、経験・スキル・役割分担を丁寧に記載しましょう。
✅ 記載すべき内容
- 役割分担:経営者、共同経営者、スタッフなどの担当業務(例:厨房、ホール、仕入、販促など)
- 人員数の計画:開業初年度から3年目までの人員構成(正社員・アルバイトの別も明記)
- 報酬・人件費:役員報酬、アルバイトの給与など
- 組織体制図:簡単な図で役割と関係性を示すと、視覚的に伝わりやすい
💡 アドバイス
1. 「誰が何をするか」を明確に
- 経営者がどの業務を担うのか(例:厨房、仕入、経営管理など)を具体的に記載しましょう。
- 家族経営の場合は、家族の役割も明記します(例:妻が販促とホールを担当)。
- アルバイトの人数やシフト体制も、営業日・営業時間と照らし合わせて現実的に設定することが重要です。
2. 人件費は損益計画と連動させる
- 役員報酬やアルバイトの給与は、損益計画の「人件費」と一致させましょう。
- アルバイトの時給や勤務時間の根拠も簡単に記載すると、計画の信頼性が高まります。
3. 成長に応じた人員増加を見込む
- 1年目は最小限の体制でスタートし、売上の増加に応じて人員を増やす計画を立てると現実的です。
- 例:3年目にアルバイトを1名増員し、ホール業務の負担を軽減する。
4. 組織体制図で視覚的に伝える
- 経営者を頂点に、各担当者の役割を矢印や階層で示すと、読み手にとって理解しやすくなります。
- 小規模事業でも、体制が整理されていることを示すことで、事業の安定性を印象づけられます。
3. 数値計画

アドバイス:3数値計画&4実施スケジュールについて
ここでは事業の「お金の流れ」と「時間の使い方」を具体的に示すことで、読み手に「この事業はちゃんと準備されていて、実行できる」と納得してもらうことができます。数字と行動計画が連動していることが、事業計画書の完成度を高める最大のポイントです。
3-1 投資・調達関連計画
✅ 記載すべき内容
- 開業に必要な資金(設備資金+運転資金)
- 資金の内訳(内装工事費、機器、備品、仕入、開業経費など)
- 調達方法(自己資金、親族からの借入、金融機関からの融資など)
💡 アドバイス
- 設備資金と運転資金は分けて記載すると、資金使途が明確になります。
- 金額は千円単位で記載するのが一般的です(例:8,000千円=800万円)。
- 自己資金の割合が高いほど、金融機関からの評価は高くなります。
- 親族からの借入も「返済計画があること」を明記すると信頼性が増します。
- 金融機関からの借入は、金額・返済期間・金利などを損益計画と連動させましょう。
3-2 損益計画
✅ 記載すべき内容
- 売上高(販売計画と連動)
- 売上原価(原価率を設定)
- 売上総利益(売上高 − 売上原価)
- 販売費および一般管理費(人件費、家賃、広告費、水道光熱費など)
- 営業利益(売上総利益 − 販売費等)
- 支払利息、税金、税引後利益
- 借入金の返済可能額(利益+減価償却費)
💡 アドバイス
- 損益計画は「3年分」を記載するのが一般的です。
- 原価率は業種によって異なりますが、カフェの場合は30〜35%が目安です。
- 人件費は「役員報酬+アルバイト給与」で構成し、人数・単価と連動させましょう。
- 家賃は「坪単価×面積×月数」で算出し、契約条件に基づいて記載します。
- 減価償却費は設備投資額に応じて設定し、返済可能額の計算に含めます。
- 税金は「経常利益×40%」など、簡易的な計算でも構いません。
- 借入金の返済額と返済可能額を比較し、「返済可能であること」を示すと安心感を与えられます。
4. 実施スケジュール
✅ 記載すべき内容
- 開業までの準備スケジュール(設立登記、物件契約、内装工事、仕入開始など)
- 開業後の運営スケジュール(販促活動、メニュー開発、スタッフ会議など)
- 資金調達・借入返済のタイミング
- 月ごとの活動内容を時系列で整理
💡 アドバイス
- スケジュールは「いつ、何をするか」を明確にすることで、事業の実行力を示せます。
- 開業までの準備は、最低でも3〜6ヶ月前から逆算して計画しましょう。
- 販促活動はオープン前後に集中させると効果的です(例:フライヤー配布、SNS開始)。
- スタッフ採用・教育は、開業の1〜2ヶ月前に実施するとスムーズです。
- スケジュール表は表形式やガントチャート形式で整理すると、視覚的に伝わりやすくなります。
📝 まとめ
事業計画書は「夢を現実にする設計図」です。数字だけでなく、あなたの想いやこだわりをしっかり盛り込むことで、支援者や金融機関にも伝わりやすくなります。ベジリアンカフェのように、具体的な事例を参考にしながら、あなたらしい計画書を作ってみましょう!
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
士業やコンサルとして中小・零細企業の社長様から要望の多い補助金支援業務について学びたい方はこちら。補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
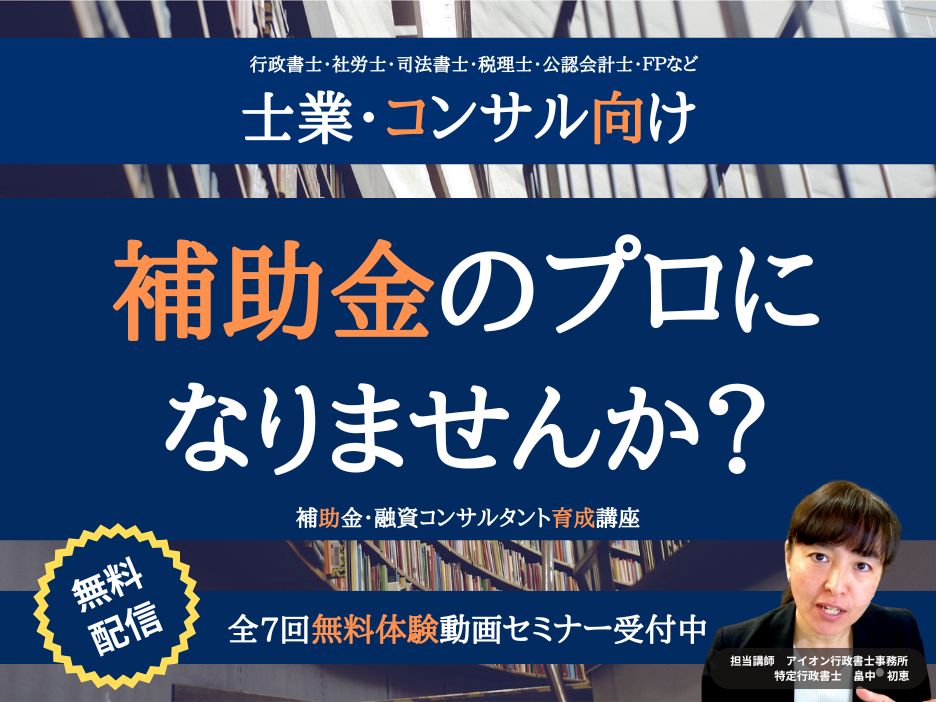
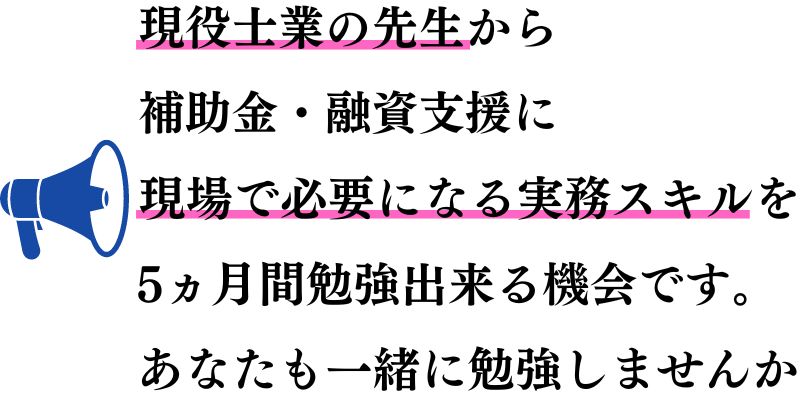

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。

