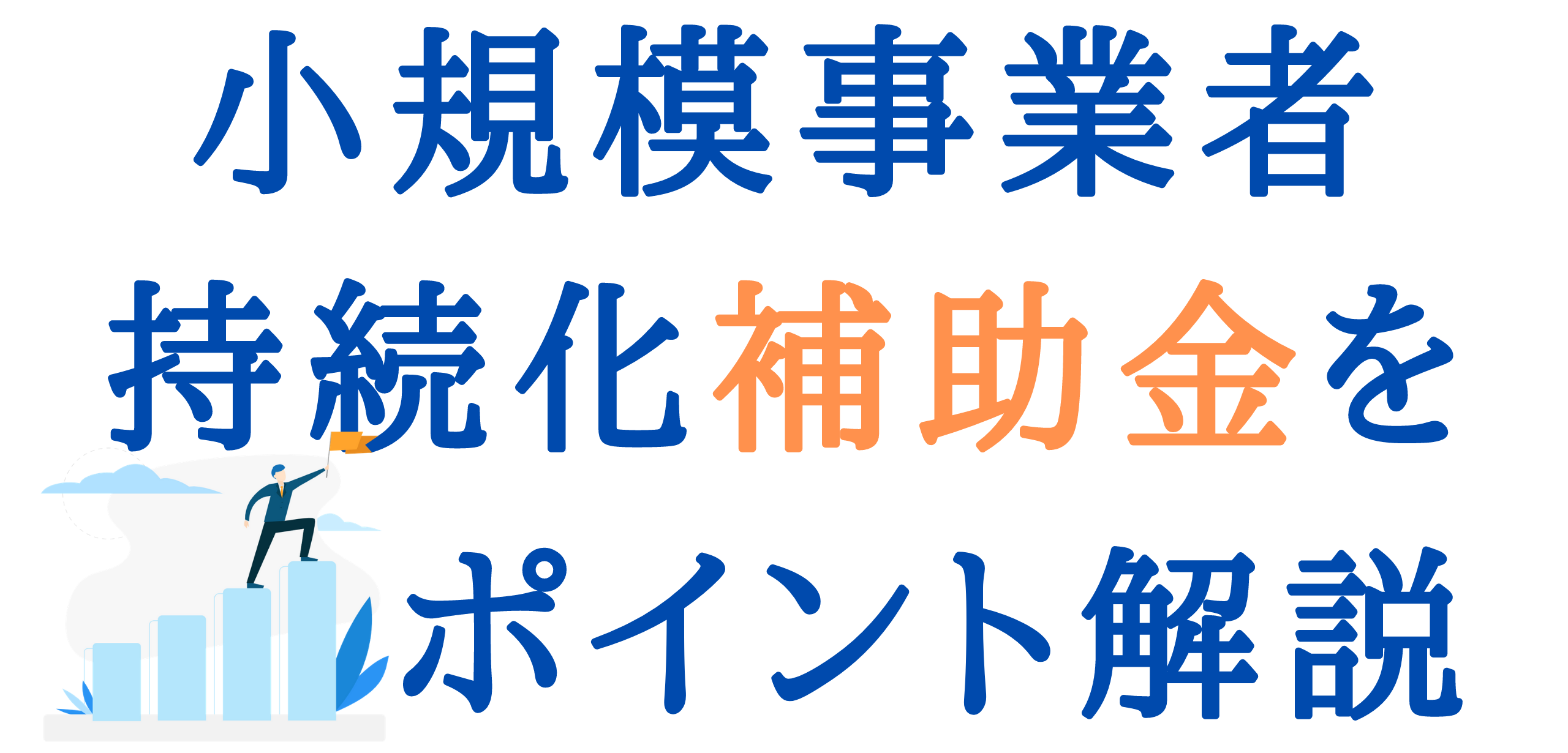2021年6月10日現在
こんにちは、補助金の広場です。
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)を知り、是非申請したいんだけれども
「何から始めていいかさえわからない!困った!」とお悩みではないですか?
こちらの記事では、小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)を始めて申請する補助金申請初心者の会社経営者の方や、上司から申請手続きをするように業務命令を受けて困っている補助金申請担当者の方に向けて次のようなご説明をさせていただきます。
・本来ご自身で行う公募要領を読み込んでいくと理解出来ること
・他の申請者の方がよく疑問に思うポイントとその回答
この記事を読んでいただけると、申請の基本がザックリ理解できるようになります。
会社を運営する上でいつも悩みの種となる事業資金を確保する手段として、この補助金制度を有効活用するノウハウを身につけることは、今後の武器になります!
是非、この記事の内容を有効にご活用下さい!!
なお、既にご存じの内容をご説明している部分がありましたら、そういった部分はどんどん読み飛ばして下さい!
それでは、どうぞ!
目次
始めに
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の公募要領から分かること
▼小規模事業者持続化補助金とはどんな補助金?
▼対象者となるのはどんな人・会社?
▼どんな事業を対象に補助してくれるの?
▼どんな経費を対象に補助してくれるの?
▼結局いくらぐらい補助してくれるの?補助額は?
▼商工会議所・商工会等の助言って必要なの?
終わりに
ご注意:
この記事は毎年行われている小規模事業者持続化補助金(一般型)についてご説明しています。一般型以外の持続化補助金では要件などが異なる場合がありますのでご注意下さい。
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の公募要領から分かること
▼小規模事業者持続化補助金とはどんな補助金?
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者等が、地域の商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作成、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助する補助金です。
補助額の上限は50万円
(低感染リスク型ビジネス枠では上限100万円)
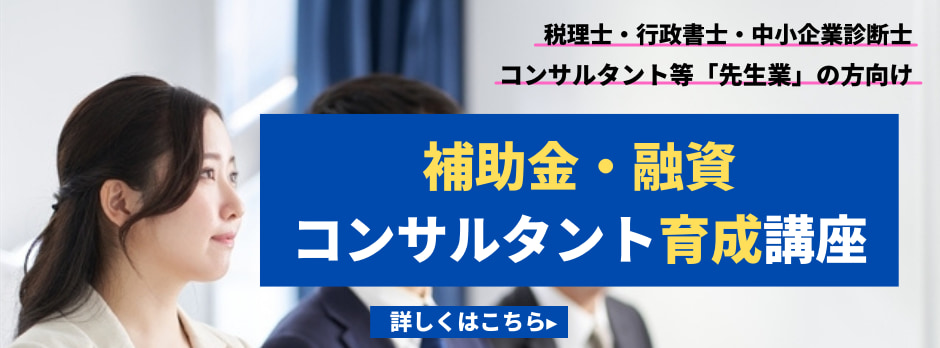
1. 販路開拓の費用=主に広告宣伝費を補助してくれる。
2. 上限50万円(or100万円)を補助してくれる。
この2点をおさえましょう。
▼対象者となるのはどんな人・会社?
対象となるのは国内の小規模事業者です。
対象となる小規模事業者とは、日本国内の小規模の事業者で、業種ごとの従業員数で判断されます。
◆業種別従業員数◆
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
▼どんな事業を対象に補助してくれるの?
策定した経営計画に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組(事業)が補助の対象となっています。
※低感染リスク型ビジネス枠は要件が異なります
次のような取組が「地道な販路開拓」とされています。
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(ウエブ広告・その他広告媒体での宣伝)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 など
▼どんな経費を対象に補助してくれるの?
下記経費が補助対象となります。
・機械装置等費
・広報費
・展示会等出展費
・旅費
・開発費
・資料購入費
・雑役務費
・借料
・専門家謝金
・専門家旅費
・設備処分費
・委託費
・外注費
Q. 販路開拓の為の機会装置等費ってどんなケース?
A. 販路開拓の為の機会装置等費とは、例えばレストランでファミリー向けの集客を図るために幼児用の椅子を新たに導入するなどを指します。
Q. 認められる旅費とはどんな旅費?通勤費も対象なの?
A. 例えば展示会を行う補助事業で、地方の企業が販路開拓のために首都圏で実施した展示会出展に伴う出張旅費などです。
▼結局いくらぐらい補助してくれるの?
一般型:上限額50万円。補助率は対象経費の2/3以内。
(低感染リスク型ビジネス枠:上限100万円。補助率は対象経費の3/4以内。)
▼商工会議所・商工会等の助言って必要なの?
結論:当サイトからのアドバイスとしては「商工会の助言は必須ではなくなりましたが、採択率を上げるために助言を受けることをお勧めします。」
小規模事業者持続化補助金の申請には商工会議所・商工会等の助言が必要でしたが、その助言を受けた事を証明する商工会議所が発行する「支援機関確認書」(様式3)は、申請の際、任意提出書類になりましたので必須ではありません。
ただし、出来るだけ確実に補助金を採択してもらうためには、申請書提出時に「支援機関確認書」を添付する事をオススメします。
現在はコロナの影響で申請者が多く、商工会が面談希望をすべて受けるだけの事務処理を行う従業員数がいないなどの理由から経営指導員からの助言は任意となりましたが、今まで自社の経営計画作成などを行う機会のなかった経営者の方は、一度社外の意見を聞く機会を持つ意味でも経営指導員からのアドバイスを受けることをオススメします。
自社の事業についてデータから分析などを行う機会のなかった経営者の方は今後の会社経営の為に参考になる考え方や知識を得るいい機会になるようです。
尚、各商工会等へ小規模事業者持続化補助金の申請アドバイスを求めると、面談中等に各商工会への加入依頼があることがありますが、加入は強制ではありません。
費用負担が難しい方は商工会への加入は断り「支援機関確認書」(様式3)のみ頂戴しましょう。
商工会議所と商工会の違いは、商工会議所は都市部にある組織、一方で商工会は地方にある組織といったイメージです。
ご自身の管轄の商工会議所・商工会をお探しの方は日本商工会会議所のWEBサイトでお探し下さい。 https://www5.cin.or.jp/ccilist/search