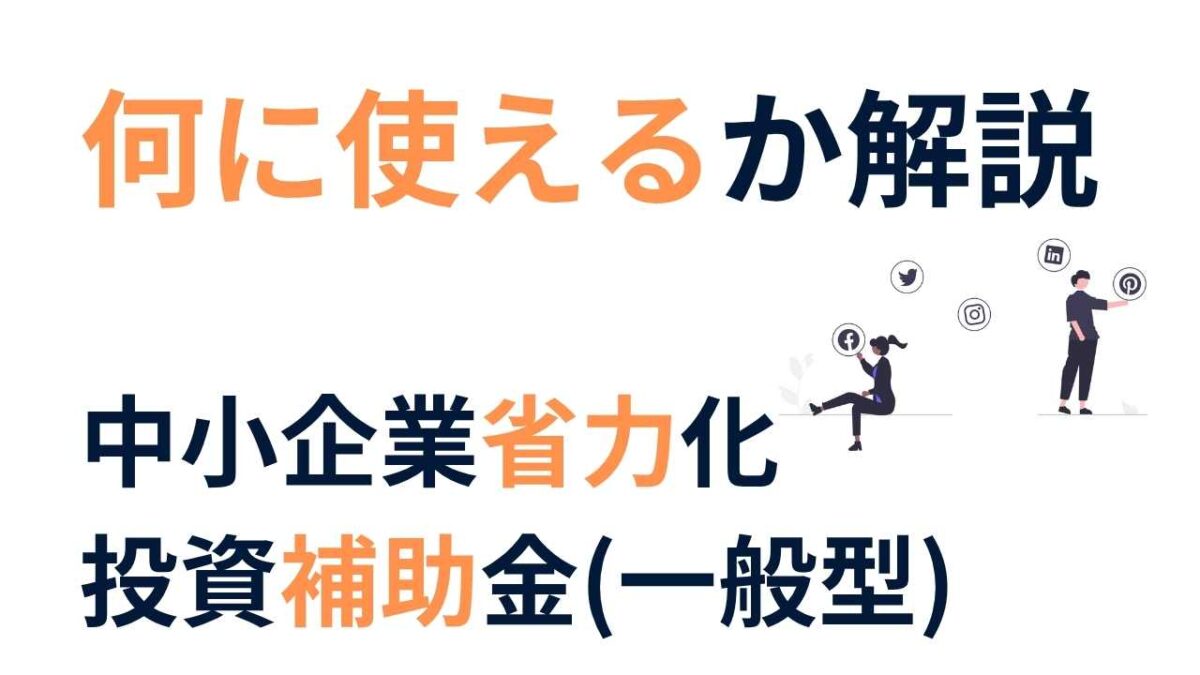🌟省力化投資補助金(一般型)とは?制度の目的と概要

中小企業省力化投資補助金(一般型)は、中小企業が省力化・業務効率化に取り組むための設備投資を支援する制度です。人手不足への対応、生産性向上を図る施策として、50万円(税抜)以上の機械装置等の導入を条件に、対象経費の2分の1(一部3分の2)または3分の1を補助金として交付します。
補助対象は、交付決定後に契約・発注され、補助事業実施期間中に支払いを完了した経費に限定されます。また、契約先以外への支払いは認められていません。
本記事は省力化投資補助金(一般型)第3回公募の情報を元に作成しています。
→ https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/
🛠補助対象となる経費とは?設備投資の基本ルール
本補助金では「機械装置・システム構築費」の申請が必須です。以下の条件に注意してください:
- 単価50万円以上(税抜)の設備が1件以上含まれること
- 借用(リース・レンタル)の場合でも、交付決定日以降の契約で補助期間内の費用に限る
- 自社製作の場合も、部品の購入費は対象になります
- 設備設置に伴う軽微な据付け費用は対象、基礎工事等は対象外
対象となる設備は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で規定される分類のみに限られ、車両・船舶・航空機などは補助対象外です。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
💡対象となる具体的な経費の内訳
以下の経費が対象になります。ただし経費区分ごとに補助率や上限額が設定されているため、詳細を確認しましょう。
機械装置・システム構築費(必須)
この補助金制度で最も重要かつ申請時に必須となる経費が、「機械装置・システム構築費」です。以下に、制度上求められる条件と対象範囲、注意点を詳しく解説します。
✅申請の前提条件
補助金の申請には、必ず税抜で単価50万円以上の設備投資を1件以上含めることが求められます。この条件を満たさない場合、申請自体が受付対象外となるため注意が必要です。
設備投資の対象は、自社の省力化に直結する、かつ専ら補助事業のために使用されるものに限られます。
🧩対象となる主な経費分類
以下のような経費が対象となります。申請時にはそれぞれの必要性・妥当性を証明する書類の添付が必須です。
- 機械・装置・工具・器具の購入・製作・借用
- 例:測定工具、検査工具、電子計算機、デジタル複合機など
- 自社製作の場合は、部品購入費も含まれます
- 専用ソフトウェアや情報システムの導入・構築・借用
- 自動化や業務効率化のための業務アプリケーション、基幹システムなど
- システム構築を伴う場合は、要件定義書、作業工数・時間、担当者記録などの詳細資料を提出する必要があります
- 設備への改良・据付けに要する経費
- 改良:性能向上や耐久性向上を目的とした新設備への追加工事
- 据付け:設置場所に固定するための軽微な設置工事(整備・基礎工事は対象外)
📦借用(リース・レンタル)の扱い
「借用」も補助対象に含まれますが、以下の条件があります:
- 契約は必ず交付決定後に締結されたものであること
- 支払いは補助事業期間中に完了していること
- 契約期間が補助事業期間を超える場合は、対象期間分のみが按分され補助対象になります
- 特定のリース会社と共同申請することで、対象リース会社に補助金が交付されるケースもあり(リース料から補助分を減額)
🔐サイバーセキュリティ対策費も対象に
システムやネットワーク導入に伴うウイルス対策ソフト等のセキュリティ対策費も対象となります。ただし以下のようなケースは除外されます:
- ウイルス対策ソフトを単体で導入する場合
- 汎用PCやスマートフォンなどの本体費用
- これら汎用製品に付随するセキュリティソフト購入費
対象となるのは、あくまで補助事業に必要な範囲での導入に限られます。
🏦金融機関からの借入に関する注意点
補助事業に使用する機械装置等を担保として金融機関から融資を受ける場合には、中小機構への事前申請が必須です。また、担保権の実行時には、補助対象設備の売却代金等を国庫へ納付する義務があります。
外注費(任意・補助対象)
外注費は、設備投資の一部を外部事業者に委託する際に活用できる補助対象経費です。機械装置・システム構築費と並び、業務の効率化や自社での対応が難しい部分の支援として活用されます。以下で制度上のポイントや注意点を詳しくご紹介します。
✅補助対象として認められる外注内容
外注費の対象は、あくまで「専用設備の設計等」に該当する業務のうち、自社の補助事業に直接必要となる作業です。請負契約や委託契約で外部に発注するケースが想定されており、以下のような例が該当します:
- 補助事業に用いる設備の設計や工程開発
- 外部ベンダーによるプログラム開発、システム設計
- セキュリティ対策を目的とした、脆弱性診断(システムの安全性評価)
補助率は補助対象経費の最大2分の1まで補助されます。
📋必須条件と注意点
外注費を補助対象として申請するには、制度上の条件を満たす必要があります。
- 外注契約の書面提出が必須
口頭契約や非公式な委託は認められておらず、契約書によって業務範囲・金額・期間などを明確に定義する必要があります。 - 設備購入は補助対象外
外注先が機械装置等を購入した場合、その費用は補助の対象にはなりません。製作費を委託する場合は、「機械装置・システム構築費」へ計上してください。 - 他の区分との併用不可
外注先へ「技術導入費」または「専門家経費」を同時に支払うことはできません。補助対象となる費用区分は1つに限定されます。 - セキュリティ関連も対象に
クラウドシステムや業務アプリケーションの導入に伴い、第三者による「脆弱性診断」などのセキュリティチェックも補助対象です。これは近年特に重要視されており、サイバーリスク対策を含めた申請も増加しています。
専門家経費(任意・補助対象)
専門家経費は、補助事業の実施に際して外部の有識者や専門家の知見を活用するために支出する経費です。補助率は対象経費の最大2分の1まで補助されます。ただし、1日あたりの上限額や対象範囲には厳格なルールがあります。以下に詳しくご紹介します。
✅対象となる専門家とは?
補助事業の中で技術的助言や指導が必要な場合、以下のような専門家への依頼が認められます:

- 学識経験者(大学教授、准教授)
- 国家資格者(弁護士、弁理士、公認会計士、医師、技術士)
- コンサルタント(中小企業診断士、ITコーディネータ)
- フリーランスや兼業・副業専門家など
彼らに依頼する業務は、補助事業に必要不可欠である必要があります。たとえば、製品やサービス設計時のセキュリティ設計アドバイスなども対象です。
💰謝金と費用上限の考え方
専門家に支払う謝金には、以下の単価上限が設定されています(すべて税抜):
| 専門家の区分 | 日額上限 |
|---|---|
| 大学教授、弁護士、公認会計士など | 5万円 |
| 大学准教授、中小企業診断士など | 4万円 |
※1日当たりの補助対象額は最大5万円です。見積もり時には、複数の見積書を取得することで費用の妥当性を示す必要があります。
🧳国内旅費も補助対象
専門家が事業支援のために現地に出向く場合、その旅費も補助対象になります。ただし、中小機構が定めた「旅費支給に関する基準」に基づく必要があります。過剰な旅費や領収書が不備なものは対象外となるので注意しましょう。
⚠️補助対象外となるケース
以下のようなケースは、専門家経費として申請できません:
- 応募段階で事業計画書の作成を支援した人物への支払い
→申請時の支援者は補助対象外です。 - 外注費や技術導入費との同時支出
→同一の専門家に対しては、いずれか1区分の経費のみが対象になります。 - 謝金単価や契約内容が不明瞭な場合
→口頭契約や不明確な依頼は対象外となるリスクがあります。
技術導入費(任意・補助対象)
技術導入費は、中小企業が補助事業の遂行に必要な「知的財産権」等を外部から取得する際に活用できる補助対象経費です。補助率は補助対象経費(税抜)の最大3分の1までが補助されます。
知的財産の導入によって、自社内で再開発や試行錯誤をせずに、迅速かつ確実な業務改善や新製品の展開につなげられるメリットがあります。
✅補助対象となる技術導入とは?
技術導入費の対象は、以下のようなケースに該当します:
- 特許権や実用新案、意匠権などの知的財産権を他者から取得する費用
- 開発済みの技術を自社で活用するための実施権の取得費
- 実施契約に基づくライセンス契約費用など
取得対象の技術は、補助事業で使用することを前提としており、事業の生産性向上に寄与するものである必要があります。
📄契約に関する要件
補助対象となるには、以下の契約関連の条件を満たしていることが必要です:
- 書面による契約締結が必須
契約内容には、取得する技術の範囲・使用条件・金額などが明記されていることが求められます。口頭契約や契約書が不十分な場合は対象外になります。 - 相手先の技術所有権が明確であること
知的財産権が正当に登録・保有されている技術である必要があり、権利の有効性が確認できないものは補助の対象外です。
🚫経費の併用に関する注意点
技術導入費を支出する相手には、外注費や専門家経費を同時に支払うことはできません。これは補助金制度上の重複支出を防止するための措置であり、必ずどの区分に該当するか明確にしたうえで申請する必要があります。
例えば、ある技術ベンダーに技術導入費としてライセンス契約を結ぶ場合、そのベンダーに対してコンサルティング費(専門家経費)や設計委託費(外注費)を別途支出することはできません。
知的財産権関連経費(任意・補助対象)
知的財産権等関連経費は、生産性向上や業務プロセス改善のために必要な知的財産の取得に関連する支出を補助するための枠です。補助率は補助対象経費(税抜)の最大3分の1までが補助されます。
事業の独自性や競争力を強化するために、法的保護のある技術やアイデアを活用したい場合には、この経費区分が重要なサポートとなります。
✅補助対象となる知的財産権関連経費
この区分で補助対象となるのは、以下のような費用です:
- 特許権などの知的財産権を取得するために要する弁理士の手続き代行費用
- 知的財産権の取得に付随して発生する書類作成や相談業務の経費
たとえば、新しい生産工程の改善に関する特許を取得するために、弁理士に書類作成や申請手続き代行を依頼する際の費用などが対象になります。
❌補助対象外となる代表的な費用
取得に関わるすべての費用が補助されるわけではありません。以下の費用は補助対象外となりますので、申請時は十分に注意してください:
- 日本特許庁への法定手数料(出願料、審査請求料、特許料など)
- 拒絶査定に対する審判請求費や訴訟にかかる費用
- 補助事業期間内に出願手続きが完了しないものの費用
これらは制度外の法的手続きに関する費用として扱われるため、補助対象には含まれません。また、完了前の出願や未決定の取得に関する費用も原則対象外です。
📄補助対象と認められるための条件
申請を受理されるには、以下のような準備が求められます:
- 弁理士との契約内容を記載した書面の提出(業務範囲・報酬額・作業期間など)
- 補助事業における知的財産権の必要性や導入効果の説明資料
- 補助事業期間中に出願手続きが完了することを示すスケジュールと証拠
補助事業において活用される知的財産であることが前提であるため、汎用性の高い技術や独自性のないものについては対象外となる可能性があります。
クラウドサービス利用費(任意・補助対象)
クラウドサービス利用費は、補助事業に必要なインフラ環境の整備を目的として、クラウドベースのサービスやWEBプラットフォームを活用する際に支出される費用です。業務の省力化や生産性向上に資する仕組みであれば、補助対象となる可能性があります。
✅補助対象となるクラウド関連経費
この区分で対象となるのは、「補助事業に専ら使用する」クラウドサービスであり、他事業との併用が認められない点に注意が必要です。
主な対象項目は以下の通りです:
- サーバー領域のレンタル費用
クラウド上の物理的なディスク領域を借りるための支払い(ホスティング、クラウドストレージ等) - クラウドプラットフォームやサービスの利用料
SaaS型アプリケーション、オンライン業務支援ツールなど - 補助事業専用WEBシステムの利用料
業務自動化のための専用システムをクラウド上で利用する場合 - 付帯する最低限の通信関連費用
ルーターの使用料、プロバイダ契約料、必要最低限の通信料等
これらはすべて、補助事業に限定して使用されるものであることが前提です。
📋対象外となるクラウド関連経費
以下のような費用は補助対象外となりますので、誤って申請しないよう注意してください:
- サーバー本体の購入費や、物理サーバーのレンタル費
- パソコン、スマートフォン、タブレット端末などの機器本体費用
- 自社の他事業と共用するクラウド環境
- 補助事業期間外に利用される契約分の費用
また、契約期間が補助事業の実施期間を超える場合は、対象期間分のみを按分して補助申請することになります。
📝申請時の注意事項
ラウドサービス利用費を補助申請するには、以下の書類の提出が求められます:
- 契約書または利用規約(契約開始日・終了日・サービス内容・金額などを記載)
- 見積書(対象期間の料金内訳が明記されたもの)
- サービスが補助事業専用であることを示す説明資料(事業計画書と合わせて記載)
これらの書類は補助対象の妥当性を判断する材料となるため、正確かつ詳細に整えておくことが重要です。

運搬費(任意・補助対象)
運搬費は、補助事業に必要な機材や関連物品を安全かつ確実に事業所等へ届けるために支出される経費です。補助金制度では「任意項目」として認められており、補助対象経費に計上することが可能です。ただし、申請時には費用の妥当性や区分の整理が求められます。
✅補助対象となる運搬費の例
運搬費として補助対象となる可能性があるのは、以下のような費用です:
- 宅配便・配送業者を利用した送料
- 機材・装置を外部から事業所に運ぶ際の運搬料
- 郵送費(報告書類や関連書類の送付に限定されるケース)
これらの費用は、補助事業の遂行に不可欠な「物品の物理的移送」にかかる支出であることが前提です。
⚠️対象外となる運搬費の扱い
注意すべき点として、購入時に支払う機械装置の運搬料は「機械装置費」に含めることが制度上定められています。そのため、同じ運搬費であっても経費区分を誤って申請すると却下や減額のリスクがあります。
たとえば:
- 機械装置を納入する際の配送料を「運搬費」として申請する → ❌
- この費用は「機械装置・システム構築費」に含めて申請する → ✅
つまり、運搬費として申請できるのは、設備の購入以外に付随する移送・郵送に関する支出が中心となります。
📝申請の際に準備すべき書類
運搬費を補助対象として計上する場合には、以下のような資料を整えておくと安心です:
- 見積書または請求書(運搬内容・距離・重量・料金が明記されたもの)
- 契約書や発注書(運搬業務を委託する場合)
- 支払い実績証明(銀行振込の記録など)
これらの資料により、補助事業に直接関連する支出であることを明確に示す必要があります。
🚫補助対象外の経費に注意!申請前に押さえるべきポイント
補助事業として認められる経費には厳密な条件が定められており、以下に挙げる経費はすべて補助対象外です。申請前にこれらの項目を十分に確認し、対象外経費を含まないよう計画を立てましょう。
🛑対象外となる具体的な経費一覧
- 交付決定前に発生した経費(事前着手は一切認められません)
- 過去に購入済みの設備に関する作業費や、補助対象外の設備に関する費用
- 設備とは関連のない設置作業・運搬費・データ作成や投入作業など
- 設備試運転に伴う原材料費や光熱費
- 通常業務に対する代行作業費用
- 製品やサービスの販売を目的とした開発・調達にかかる費用
- 自社の社員による社内システムの開発・改修の人件費
- 開発不要なパッケージソフトや汎用ソフトの購入、設定・セットアップ費
- 既存システムやソフトウェアのアップデート・改修費用
- 工場建屋や仮設構造物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費・組み立て部材費
- 太陽光パネルなど再生エネルギー設備および付属装置の取得費
- 設置場所の整備工事や基礎工事の費用
- 家賃、敷金、仲介料、光熱水費などの事務所経費
- 電話料金、インターネット料金(※クラウド経費として認められる範囲を除く)
- 商品券などの金券類
- 文房具、雑誌、新聞代、団体会費などの消耗品・購読・会費類
- 飲食費、娯楽費、接待費など事業と無関係な支出
- 不動産、車両(※工場内のみ使用できるもの除く)、船舶、航空機などの取得・修理・車検費
- 税務申告・決算作成等に対する税理士・会計士・弁護士の報酬
- 収入印紙代
- 振込・代引・両替等の手数料
- 消費税および地方消費税などの公租公課
- 各種保険料
- 借入金の利息および遅延損害金
- 事務局提出用の報告書類作成にかかる経費
- 汎用性があり目的外使用になり得る製品の購入費
(例:事務用PC・プリンタ・文書作成ソフト・スマホ・タブレット・カメラ・家具など) - 中古品の購入費
- 自社従業員に対する旅費・交際費・ソフトウェア開発時の人件費
- 補助事業者自身の交通費・宿泊費
- 親子会社間や資本関係がある企業への支払い(みなし同一法人)
- 自社内の部署間取引(社内製造や社内発注など)
- リース契約に伴う金利や保険料などの付帯費用
- 本事業の目的にそぐわないと中小企業庁等が判断した経費
- その他、社会的に不適切と認められる経費
このように、補助対象外の経費は非常に細かく定義されており、誤った申請は却下・減額・取消の対象となります。申請前のチェックリストとしても活用し、補助金制度の趣旨を十分に理解したうえで正しく利用しましょう。
🎓補助金の基礎を学ぶ──コンサルタント育成講座のご案内
本記事をご覧いただいた皆さまの中には、「補助金の申請支援を仕事にしたい」「企業の成長をサポートする立場として活躍したい」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。当社では、そうした方々に向けた「補助金・融資コンサルタント育成講座」を開講しております。
この講座は、省力化投資補助金ではなく、補助金支援の基礎を習得することを目的としており、主に「小規模事業者持続化補助金」をベースにカリキュラムが構成されています。
📚講座で学べること:
- 小規模事業者持続化補助金の制度理解と活用ポイント
- 補助金申請に必要な事業計画書の作成手法
- 経営者とのヒアリングスキルや提案力の向上
- 実際の申請支援に活かせる実務的ノウハウ
- 補助金活用の幅広い相談業務への応用方法
初心者の方でも安心して参加できる内容となっており、「知識ゼロからプロの支援者へ」を目指せる実践的な学習環境を整えています。
👨💼補助金の支援を仕事にしたい方、まずは基礎から学んでみませんか?
👉 詳細はこちら:補助金・融資コンサルタント育成講座
補助金支援のプロフェッショナルとして、あなたも新しいキャリアを築いてみましょう。
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
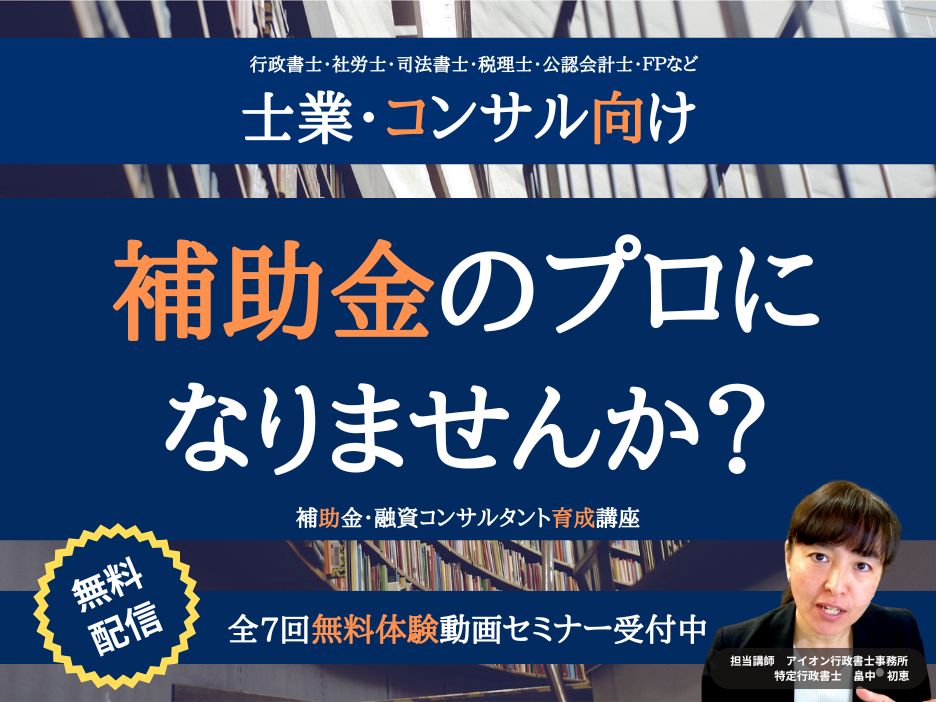
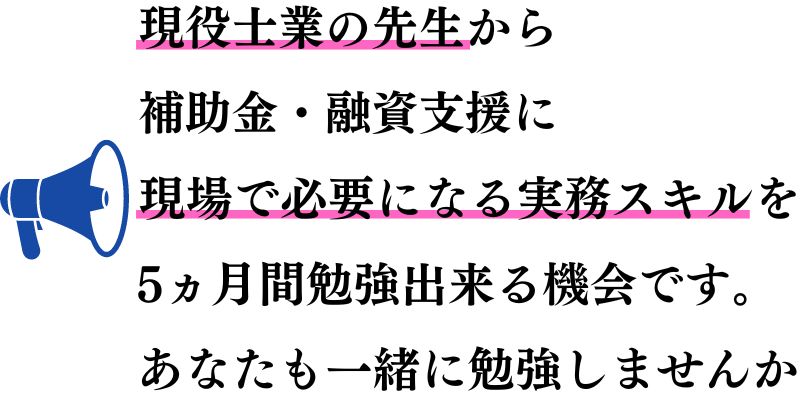

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。