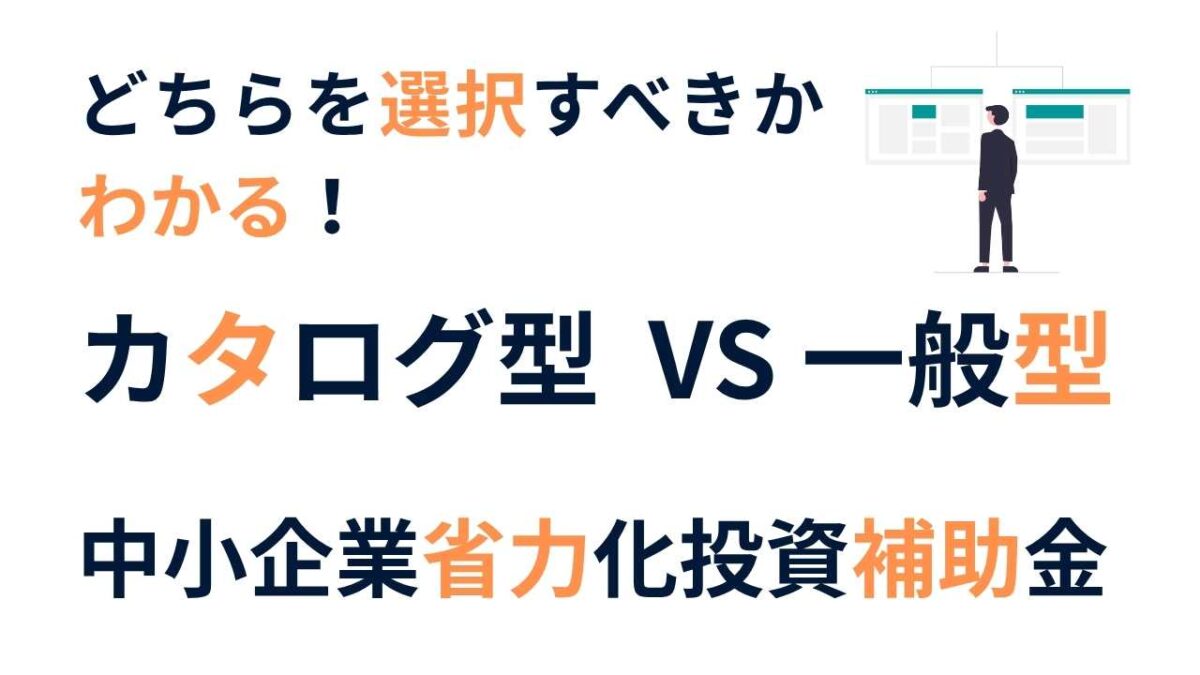🌱 省力化補助金 カタログ型と一般型 どちらを選ぶべきか?

中小企業や小規模事業者が人手不足に悩まされる中、省力化や自動化による生産性向上はますます重要なテーマとなっています。こうした背景のもと、中小企業庁が2024年度から開始した「中小企業省力化投資補助金」は、設備導入にかかる費用の一部を補助し、業務効率化を後押しする制度です。
補助対象は、作業の自動化、DX推進、従業員の負担軽減などを目的とした機械設備やソフトウェア。導入を通じて、持続可能な経営や人的資本の活用強化が期待されます。
この補助金は「カタログ型」と「一般型」の2つの申請方法に分かれており、自社の状況や目的に応じた選択が重要です。
こちらの記事は2025年7月現在の公開情報を元に作成しています。
🏷 カタログ型と一般型の基本的な違い【申請前に知っておくべきポイント】
「中小企業省力化投資補助金」には、現在2つの申請タイプがあります。それが従来型の「カタログ型」と、2024年度から新設された「一般型(オーダーメイド型)」です。
両者の最大の違いは、設備の選び方と申請の柔軟性、そして手続きの難易度とスピード感です。以下の比較表をご覧いただくと、その違いが明確に分かります。
| 比較項目 | カタログ型(継続中) | 一般型(オーダーメイド型) |
|---|---|---|
| 申請方式 | 国が事前に認定した「省力化カタログ」掲載製品から選択 | 事業者が独自に設備を選定して申請 |
| 審査の難易度 | 省力化効果が事前に認定されており、審査は比較的スムーズ | 省力化効果や投資回収計画などを自社で説明する必要あり |
| 補助対象設備 | カタログ掲載製品のみが対象 | 業務に最適な設備を自由に選定できる |
| 補助率 | 1/2~2/3(設備・条件によって変動) | 同じく1/2~2/3(ただし1,500万円超は1/3) |
| 補助上限額 | 一般的に小~中規模投資向け | 高額な補助も可能、事業規模に応じて柔軟に対応 |
| 導入の柔軟性 | 選択肢は限定的だが、選ぶだけで申請可能 | 自社課題に沿った設備の自由設計が可能 |
🗣️ 制度設計者の意図と当社からのアドバイス
弊社の担当者が、行政が開催した「省力化補助金の説明会」に参加した際、制度の設計に関わった方から次のような主旨のお話がありました:
「従来の補助金制度では、情報公開から募集、審査、結果発表、検査、補助金の支払いまでに非常に時間がかかり、事業者にとっては手続きの煩雑さや入金までの待機期間が大きなストレスとなっていた。これを改善するために、今回“カタログ型”という制度を新設した」
この設計思想を踏まえると、早期導入を実現したい方や、申請手続きに不安を感じている事業者には「カタログ型」の申請が非常におすすめです。
選択肢が限られる分、スピーディかつ確実に導入を進められるという利点があります。また、審査も「省力化効果が事前認定されていること」で簡略化されているため、補助金初心者の企業でも取り組みやすい制度です。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
🧰 カタログ型の特徴と活用しやすいケース
カタログ型申請では、公式カタログページに掲載された製品の中から希望するものを選び、導入するだけで申請できます。事務局側があらかじめ設備の省力化効果を確認済みであるため、審査がシンプルになるのが特長です。
カタログ型が向いている事業者:
- 迅速に設備を導入したい
- 申請書類作成に時間をかけたくない
- 標準的な業務効率化ツールを導入予定
カタログ掲載製品には、業種ごとのニーズに応えるよう多様なラインアップがあります。例えば、レジ・POS機器、検温・受付システム、業務用ロボットなどが含まれます。

🛠 一般型の特徴と採択されやすい戦略
一般型は、自社の業務フローや課題に合わせてオリジナルの省力化アイデアを補助対象として申請できる方式です。審査には、「その設備がなぜ必要か」「どう省力化につながるか」といった定量的・定性的な説明が必要となります。一般型の公式サイトはこちら。
一般型を検討すべき事業者:
- カタログ掲載品ではニーズに合わない
- 自社独自の効率化を目指している
- 高度なDX機器や特注設備を導入したい
採択率を高めるには、具体的な省力化効果(例:作業時間削減率、人的コストの変化)を数値で示すことが大切です。また、過去に同様の施策を導入した事例があれば、それも説得材料になります。
📊 どちらを選べばいい?判断のポイント

選択の際に意識すべきポイントは次の通りです:
設備の自由度・高度化→一般型
導入スピード重視→カタログ型
自社に特化した省力化→一般型
書類・申請作業の簡便さ→カタログ型
また、補助率や上限額も型によって異なる場合があります。最新の公募要領を確認したうえで、申請スケジュールや補助対象品を十分に検討することが重要です。
💡 申請時に押さえるべき注意点
申請にあたり共通して気をつけたいのが以下の点です:
- 補助対象外となる支出を避ける(例:汎用品、既存契約品など)
- 実績報告や支払証明の提出が必要となる
- 自己負担額の確認と資金計画の整備
特に、一般型では提案の質と説得力が求められるため、事業目的や導入効果を簡潔かつ論理的に説明できるよう準備しておきましょう。
🚪 未来につながる選択へ:補助金活用後の展望
補助金の活用は、単なる資金援助に留まりません。導入された設備が現場にもたらす変化は、中長期の生産性や組織力強化に直結します。たとえば、従業員の負担軽減が離職防止につながったり、デジタルツール活用が新たな収益モデルの構築に発展する可能性もあります。
制度を正しく使うことで、補助金は「設備投資」ではなく「経営投資」に進化します。
本記事では「カタログ型」と「一般型」の違いと選び方について解説しましたが、補助金の世界はまだまだ広く、奥深いものがあります。
補助金の活用をきっかけに、経営支援・資金調達の専門性を磨きたい方は、ぜひ次のステップへ。
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
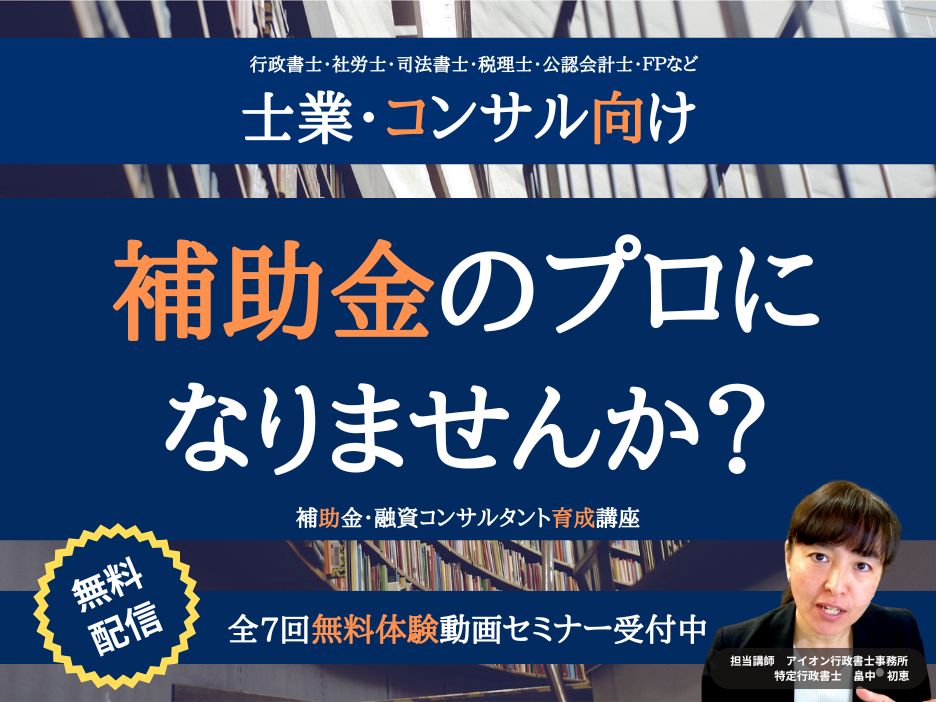
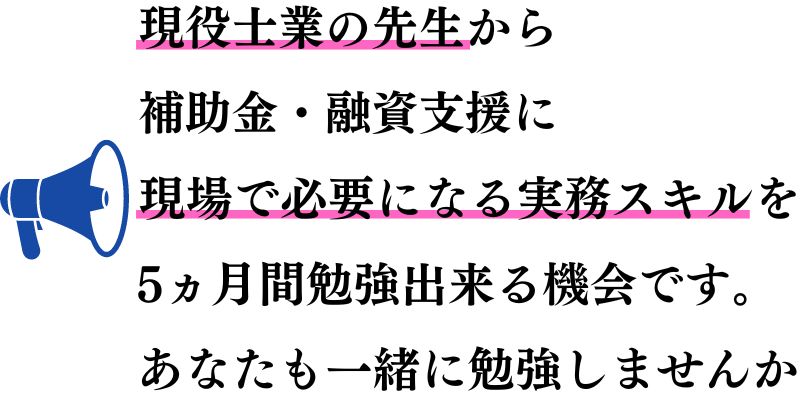

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。