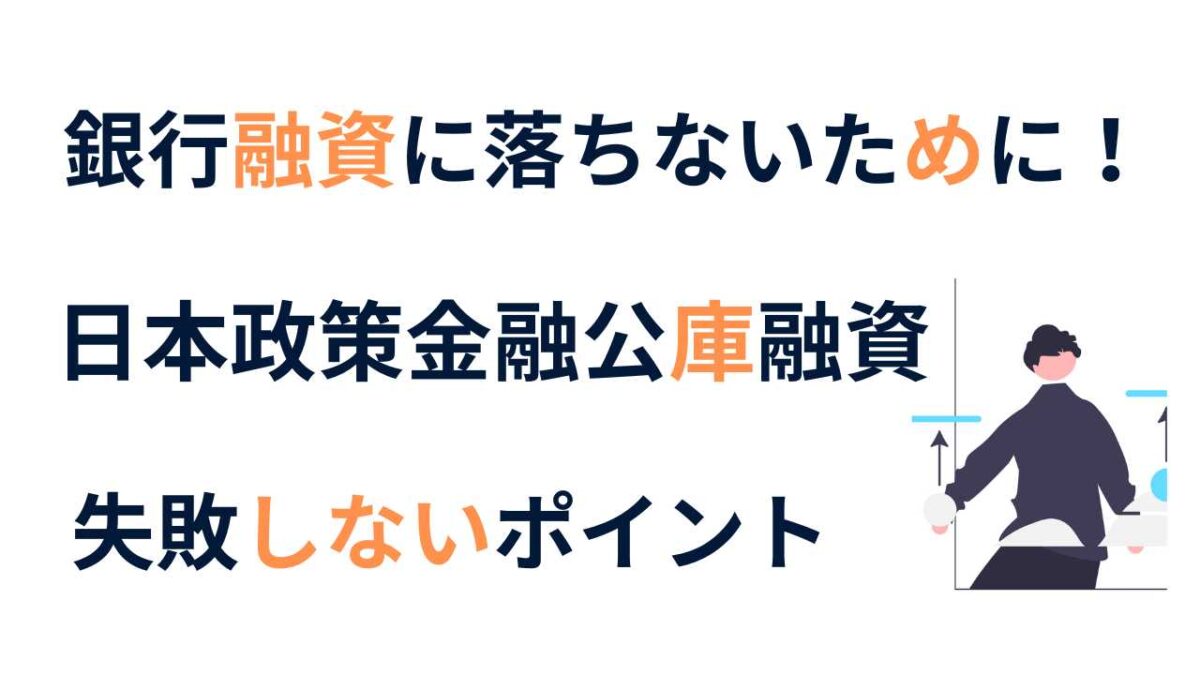✨はじめに:なぜ銀行融資の審査に落ちるのか?

日本政策金融公庫は、政府が全株式を保有する公的金融機関として、中小企業や創業者に向けた支援に力を入れています。
特に創業支援においては、民間の金融機関よりも審査のハードルが低いと見られがちですが、一部情報では融資に通過する確率は約50〜60%と言われており、決して甘い審査ではありません。(【融資通過率】日本政策金融公庫本体から審査通過率に関する公式なデータは公開されておりませんのであくまでも参考例として認識願います)
では、なぜ審査に落ちてしまう人がいるのか?この記事では、その理由を5つに絞り、具体的な対策とあわせて解説します。
🧩理由①:信用情報に問題がある
日本政策金融公庫に融資を申込む際、必ず「信用情報」の調査が行われます。これは、申込者の過去の返済履歴や借入状況から「この人に資金を貸しても問題ないか」を判断するためです。
この信用情報とは、信用情報機関に登録されている個人の金融取引履歴であり、日本政策金融公庫では主に「CIC(株式会社シー・アイ・シー)」という信用情報機関のデータを参照しています。
CICには、次のような情報が登録されています:
- クレジットカードの利用状況
- 消費者ローンの残高と返済履歴
- 支払いの延滞履歴(過去2年分が中心)
- 債務整理や自己破産などの記録(5〜10年間保存)
なお、審査の際に特に不利になるのは以下のケースです。
| 🔍信用情報上の問題内容 | 審査への影響 |
|---|---|
| 過去2年以内に複数回の支払い遅延 | 審査に大きく不利 |
| キャッシングやカードローンの債務が残っている | 信用性が低下し不利 |
| 過去5年以内に61日以上の延滞履歴がある | 審査通過は非常に困難 |
| 債務整理(任意整理・自己破産など)をしている | 審査対象外となる可能性あり |
| 強制解約の記録 | 信頼性に大きく影響 |
| 自己破産の記録が残っている(10年以内) | 通常は融資不可 |
逆に、住宅ローンなどの有担保融資を返済中であり、過去2年間に1〜2度の軽微な遅延があった場合は、審査にそこまで大きな支障はありません。
ですが、注意すべきなのは以下のような点です:
- 短期間で複数回の延滞があると「返済の継続力がない」と判断される
- キャッシングの残高があると「借金の多さ」に懸念をもたれる
- 債務整理や破産歴があると、審査以前に申込を断られる可能性も
長期延滞や債務整理した方は、信用情報機関に一度登録されると、その情報を5年から10年間保持されます。この期間中は、融資審査に通る可能性が極めて低くなるため、融資申込のタイミングには慎重になる必要があります。
🎯どう対処すれば良いか?
- 信用情報は、事前に自分でCICを通じて照会することが可能です
- 延滞中の債務は、できれば一括返済してから申込むのが理想です
- 過去に長期延滞や債務整理した方は、その記録が消えるまで待ってから申請しましょう
融資審査は、「現状」だけでなく「過去の履歴」も重視されます。今後の信頼構築に向けて、まずは金融取引をきちんと見直し、記録の健全化を図ることが大切です。

当社からのアドバイス:CIC(株式会社シー・アイ・シー)とは?
CICとは、クレジットやローンの契約・返済状況などの信用情報を管理している日本の指定信用情報機関です。カード会社や消費者金融など、全国の金融機関と情報を共有しており、個人の金融履歴が融資審査において客観的に判断されるための仕組みを担っています。CICの情報開示は、本人であればWebや郵送、窓口で簡単に請求できますので、融資申請前には一度確認しておくことをおすすめします。
※【不安な方】本人であれば自分の信用情報の公開を申請出来ますよ
💡理由②:公共料金や税金の支払いに遅延がある
日本政策金融公庫の審査では、申込者の日常的な金銭管理能力もチェックされています。その中でも特に重視されるのが、電気・水道・ガスなどの公共料金や、住民税・所得税などの税金の支払い状況です。
🔍なぜ公共料金や税金の支払い状況が重視されるのか?

その理由は、「生活の基盤にかかわる支払いが期日通りにできない人は、融資を受けても返済が滞る可能性がある」と判断されてしまうからです。
公共料金や税金は、個人や事業者としての最低限の信用を示す要素でもあり、支払い能力や支払いの意思を評価する目安とされています。
たとえば、電気代を長期にわたって滞納している場合は、「資金管理がずさんではないか?」と疑念を持たれやすくなります。税金の支払いが滞っている場合も同様で、政府系金融機関である日本政策金融公庫では、税の未納状況を特に厳しく見る傾向があります。
📖通帳提出で何がわかるのか?
日本政策金融公庫の融資審査では、会社や個人名義の通帳を提出します。この通帳には、公共料金や税金の引き落とし履歴が記載されており、支払いの遅延や未払いがあるかどうかを確認するための重要な資料となります。
- 支払いが期日通りに行われているか
- 一度でも引き落とし不能(残高不足)になっていないか
- 毎月の支払先が一定しているか(頻繁な変更がないか)
これらが通帳から読み取られるため、審査時には厳密にチェックされるのです。
🏁創業予定者も対象になる
創業前でまだ法人格がない方でも例外ではありません。創業融資の場合は、個人の通帳や、半年分の公共料金の支払い明細書などが求められます。
つまり、これから事業を始める方でも、「すでに日常生活で支払いをきちんと行っているか?」が問われるということです。これは、金融機関が事業者の信用を測るために、個人の金銭管理の状態を審査対象にしている証拠です。
✅事前にできる対策は?
- 毎月の支払いは期日までに確実に済ませる
引き落とし口座に十分な残高を確保し、支払い漏れが起きないように管理しましょう。 - 通帳を整理しておく
公共料金の引き落としが一つの口座に集約されていると審査の確認がスムーズです。 - 税金の納付書は必ず保管しておく
通帳に記載がない税金の支払いも、領収書や納付書で支払い証明ができます。 - 半年〜1年前から準備を開始する
審査書類として「最近の履歴」が提出されるため、最低でも6ヶ月前から支払い習慣の改善を心がけることが重要です。
公共料金や税金は、金額の大小ではなく「支払い姿勢」が審査の対象となります。事業者としての信頼を築くためには、こうした日常の支払いをおろそかにしないことが、融資通過への第一歩です。

当社からのアドバイス:銀行通帳履歴の重要性
事業用と個人用の口座を一つにしている方は要注意です。以前、趣味で競馬をされている方が、馬券購入の支払い履歴も記載されている通帳を提出しようとした際、金融機関担当者から「この通帳では融資は厳しい」と指摘を受けました。
通帳には日々の資金の使い方が表れます。だからこそ、事業用口座と個人用口座は早めに分けて管理することをおすすめします。それだけで、資金管理の姿勢が整い、融資審査でも信頼されやすくなります。
💰理由③:自己資金が不足している

創業融資を検討する際、最初に確認されるのが「自己資金の有無」です。自己資金とは、融資以外で自ら用意した事業資金のことを指し、言い換えれば「リスクを取って事業に賭けているか」を示す指標でもあります。
日本政策金融公庫では、創業融資の申込条件として、「総資金額の10分の1以上の自己資金が確認できること」と定めています。
たとえば500万円の創業資金を希望する場合、最低でも50万円の自己資金が必要となり、これがなければ申込自体ができません。
📖審査でチェックされるポイント
審査では、「半年前からの普通預金通帳」が提出資料として求められます。
これは、自己資金が本当に申込者自身のものであるかを確認するための措置です。以下のようなケースは、審査で不利となる可能性があります:
- カードローンから借り入れて、申込直前に自己資金として一時的に入金した場合
- 知人や家族から借りたお金を“見せ金”として通帳に反映させた場合
- 預金額が急激に変動しており、安定性に欠けると判断される場合
こうした“資金の信頼性”も審査対象となるため、形式だけ揃えても意味がありません。実際に半年以上の期間をかけて、計画的に貯蓄してきたことが通帳上に示されていることが重要です。
✅審査通過に向けた対策は?
- 早い段階から自己資金を確保しておく
創業の半年以上前から、着実な積み立てを行い、通帳でその履歴が見えるようにしておきましょう。 - 資金の出どころに一貫性を持たせる
使っていない口座に突然大金が入るような不自然な動きは避けましょう。給与口座など、普段使いの口座で貯めるのがおすすめです。 - “見せ金”と疑われないよう注意する
借入金や臨時の入金で自己資金を一時的に見せるのではなく、コツコツと積み上げてきた信頼性のある履歴を作りましょう。
自己資金は、単なる“お金”以上に、事業への本気度を示すものです。「自分のリスクを背負って挑もうとしているか」を審査担当者はしっかりと見ています。
融資の成功率を高めるには、計画的に時間をかけて準備することこそが最も効果的な近道です。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
📊理由④:経営計画が現実的か
融資審査では、資金の使い道や返済計画に加えて、「経営そのものの見通し」がしっかりしているかどうかが重要視されます。
日本政策金融公庫が求める経営計画とは、単なる売上目標の羅列ではなく、数字と実態が結びついた「現実的な計画」に基づいて構成されていることが条件です。

⚠️よくある経営計画の不備
- 根拠が不明瞭な売上急増の予測
→ 過去実績や市場動向と照らして、現実味がないと判断される - 売上が伸びる一方で、仕入・人件費が減少している
→ 通常ならコスト増が想定される場面で、逆に支出が減る設定は不自然 - 設備投資などの支出が曖昧・目的が不明確
→ 資金使途が曖昧な場合は、融資対象として適さないと見なされやすい
このような矛盾や曖昧な設定があると、「この事業には本当に計画性があるのか?」「返済能力はあるのか?」という不安を与えてしまいます。審査担当者は、計画の中身が整合性に富み、具体的かつ客観的に説明できるかを厳しくチェックしています。
✅対策:説得力のある経営計画をつくるために
- 数値の根拠を明示する
市場調査やターゲット客層の需要データをもとに、売上や利益予測を構築する - 支出項目の内訳を詳細に記載する
商品原価、人件費、広告費、店舗維持費など、具体的な金額を設定する - 資金使途を明確に記載する
例えば「厨房機器の購入に100万円」「販促費に30万円」など、実際に何のために資金が必要かを具体的に示す - 計画と事業内容が一致しているか確認する
提出する事業計画書と面談時の説明が一致していることが重要です。数字の整合性だけでなく、「なぜその計画が必要か?」を自分の言葉で説明できるように準備しておきましょう。
経営計画とは、融資審査における「事業の将来性を示すレポート」です。どんなに熱意があっても、数字に裏付けされた信頼性がなければ、資金を引き出すことは難しくなります。だからこそ、経営者としての思いと、数字の説得力を両立させた計画書づくりが欠かせません。
🗣理由⑤:面談でうまく説明できない
日本政策金融公庫の融資を申請すると、書類審査の後に「面談」が行われます。
この面談は、単なる形式的なヒアリングではなく、融資を実行するかどうかを判断する“対面評価”の場です。
💬面談で確認されるポイントとは?
担当者は次のような内容について、直接質問してきます:
- なぜ融資が必要なのか(資金の使途)
- どのような事業を行うのか(業種・業態・提供価値など)
- 売上はどのように得るのか(集客・販売の方法)
- どのように返済していくのか(利益計画・収益見通し)
それに加え、次のような“人物評価”も同時に行われています:
- 経営者としての本気度や熱意
- 準備・知識・数字への理解力
- 応対の誠実さ・信頼感
つまり、ただ数字や計画の説明だけではなく、「この人は本当に事業をやり切る力があるか?」が見られているのです。
⚠️説明不足が審査落ちにつながる理由

よくある失敗例は次のようなケースです:
- 「とりあえず始めたい」など動機が曖昧
→ 計画性がないと判断されやすい - 売上の根拠が示されず、数字が“希望的観測”に見える
→ 現実性に欠けると評価される - 曖昧な発言に終始する
→ 信頼関係の構築が難しくなる
上手に話す必要はありません。しかし「何を聞かれても、自分の言葉で答えられる準備」ができていることが、審査を左右します。
✅面談通過のためのポイント
- 事前に質問を想定しておく
融資の使い道、売上予測、返済計画などは必ず聞かれる内容です。想定問答を自分で準備しましょう。 - 創業計画書と話す内容を一致させる
書類に書いてあることと面談で話す内容が食い違うと、「信頼性が低い」と判断されることがあります。 - 数字の根拠は具体的に説明できるようにしておく
例えば「SNS広告を使って月○件の集客を見込む」「原価率は○%で利益率は○%」など、数字で語れる準備が必要です。 - 人柄・熱意をしっかり伝える
この事業にどんな思いがあり、なぜ自分が取り組むのか。こうした背景は審査担当者の心に響きます。
面談は、融資担当者との“信頼構築の場”です。言葉のうまさではなく、準備と誠実さが一番の武器になります。
あなた自身の熱意と計画性が伝われば、数字以上の信用が生まれ、審査通過にぐっと近づくはずです。
✅まとめ:審査に通過するために今すべきこと
銀行融資を成功させるには、以下のような準備が欠かせません:
- 信用情報の確認と改善
- 公共料金などの支払いの習慣化
- 計画的な自己資金の蓄え
- 矛盾のない経営計画の作成
- 面談に向けた事前準備と誠実な説明
これらを着実に進めることで、日本政策金融公庫の審査通過率を大きく高めることができます。
🎯最後に:融資は「信頼構築」の場
融資の審査は、単なる数字の評価ではありません。
過去の履歴、事業計画、そして経営者としての人柄や姿勢など、複数の視点から「この人に資金を託せるか?」が見られています。
だからこそ、事前の準備が結果を左右する大きなポイントなのです。
審査に通過するためには、資金計画や書類の整備はもちろん、面談に向けた説明力の強化など、総合的なスキルが求められます。
これらを体系的に学べる機会があれば、あなたの事業もさらに強いスタートが切れるでしょう。
そこで次にご紹介するのが、創業支援の専門家を目指す方にも役立つ、弊社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」です。
資金調達の成功率を高めたい方、事業者支援に関わりたい方は、ぜひご覧ください。
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
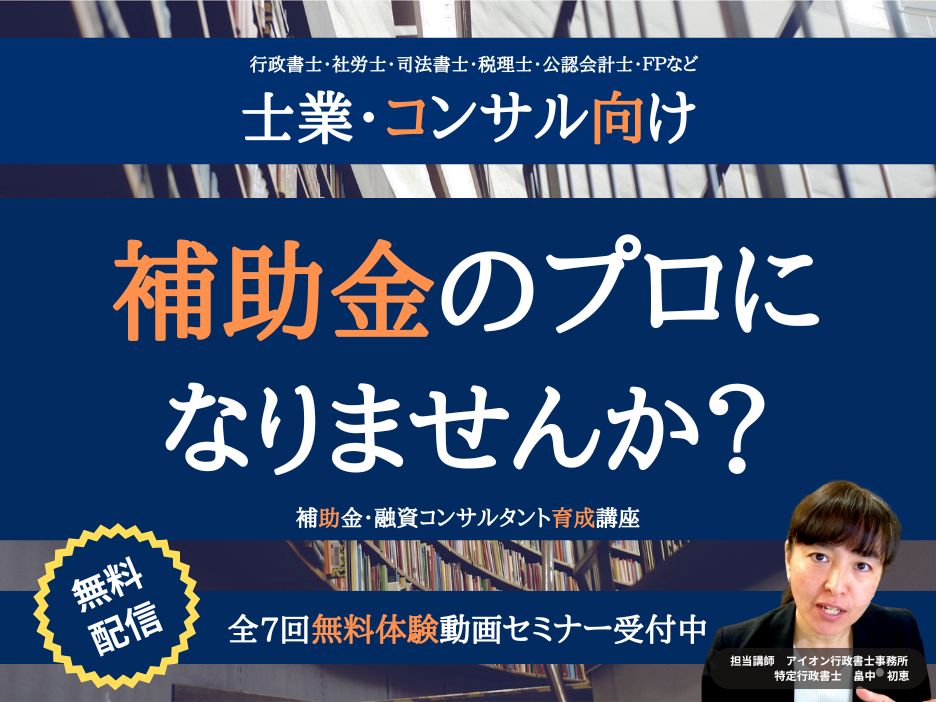
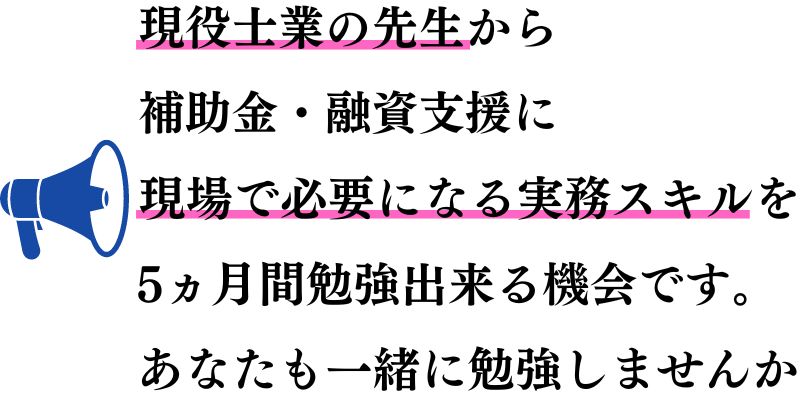

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。