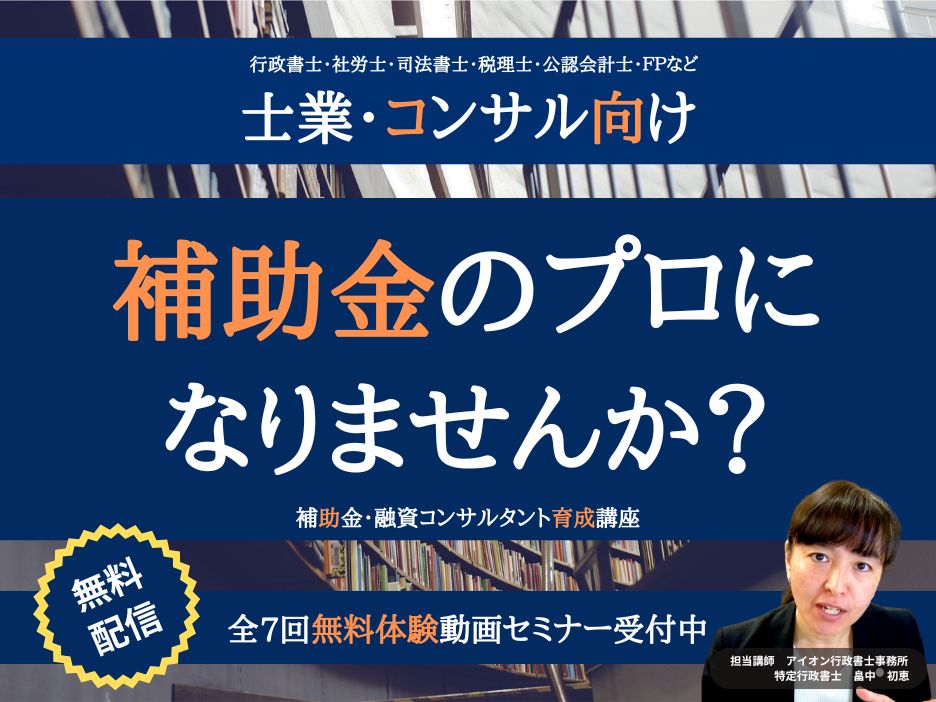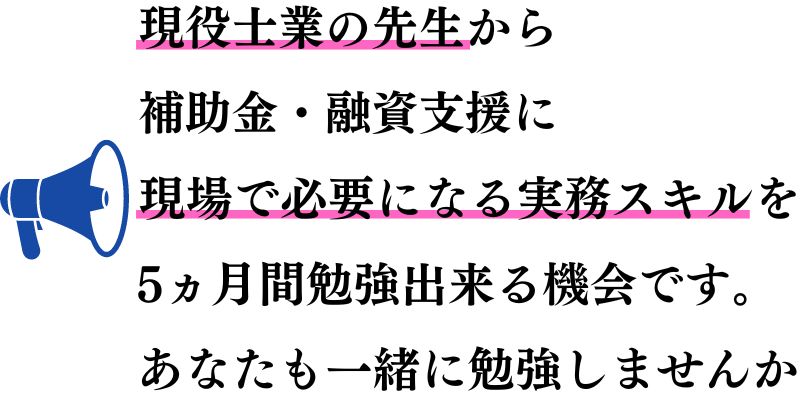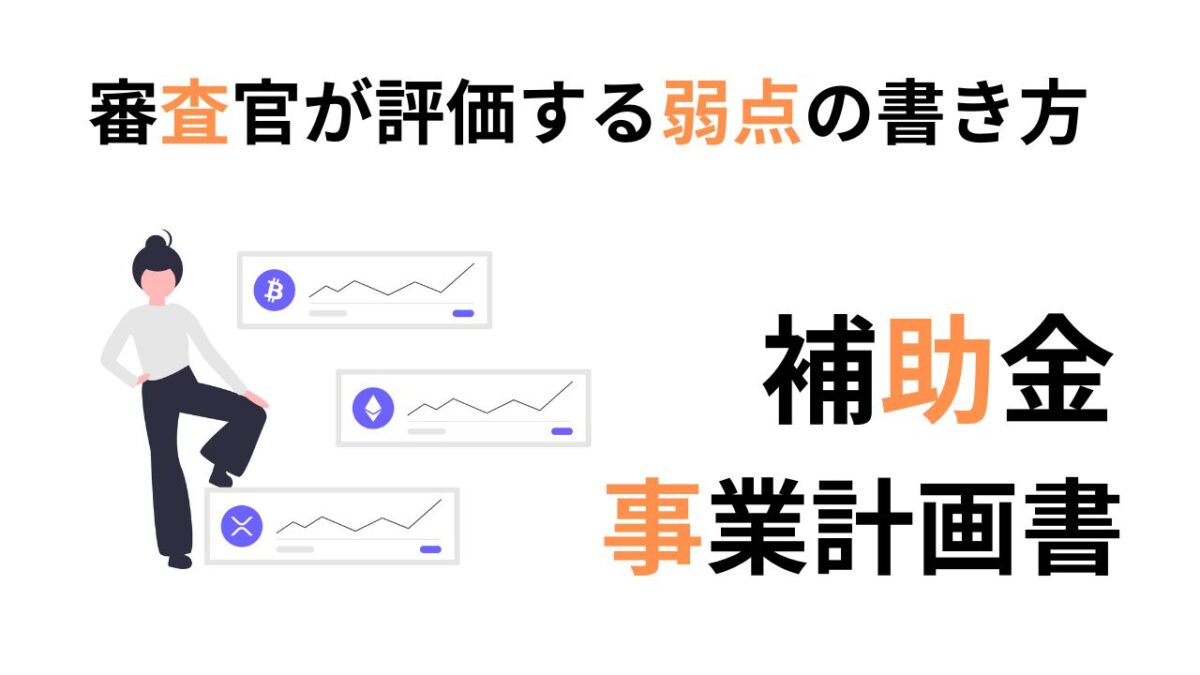🎯この記事を読んでほしい方
- 補助金の申請を検討している中小企業経営者・個人事業主の方
- 初めて事業計画書を作成する方
- 「リスクの書き方がわからない」「弱点を正直に書いていいのか?」と悩んでいる方
- 採択率を高めるために、事業計画書の質を上げたい方
📌目次
- リスクは書かない方が得?その誤解が落とし穴
- なぜ審査官は「リスク」を見たがるのか
- リスクの正しい定義と考え方
- リスクの洗い出し方:社内要因と社外要因
- リスクの書き方4ステップ
- 書いてはいけないリスクのNG例
- リスクの解決策は「ゼロにする」必要なし
- SWOT分析との連携で説得力アップ
- リスクを味方にする!事業計画書の戦略的な書き方
- 【まとめ】リスクは「書かない」より「活かす」時代へ
- 📘「ものづくり補助金の教科書」でさらに学ぶ
1. リスクは書かない方が得?その誤解が落とし穴
補助金申請において「リスクを書く=マイナスに評価される」と誤解している人は少なくありません。
「リスクなんて書いたら、採択されないのでは?」という不安から、すべての項目をポジティブに埋めようとしてしまう気持ち、よくわかります。
しかし、審査員はあくまで“現実的かつ持続可能な事業計画”を求めています。現実性のない“成功しか描かれていないプラン”はかえって不信感を招きやすく、説得力を欠く要因となってしまいます。
むしろ、リスクを明確に把握し、その対策まで考慮された計画こそが、審査官の信頼を得やすくなるのです。
2. なぜ審査官は「リスク」を見たがるのか

補助金審査官の主な視点は以下の3つに集約されます:
- 事業の継続性があるか
- 実現可能性が高いか
- 社会的意義・波及効果が期待できるか
その中で、「リスク記載」は1つ目と2つ目に直結する情報です。
審査官にとっては、どんなに魅力的な構想でも「失敗の可能性に無自覚な事業者」には投資しづらいのです。むしろリスクを認識し、対策を練る姿勢を見せることが、事業者としての信頼感を高めます。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
3. リスクの正しい定義と考え方
事業計画書における「リスク」とは、単に“失敗する原因”を書くことではありません。重要なのは次のような視点です。
| リスクの種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 外部リスク(市場変化) | 市場の競争激化、仕入れ価格の高騰、法律改正など |
| 内部リスク(経営資源) | 人材不足、技術力不足、資金繰りの弱さなど |
| 技術的リスク | 製造工程の不確実性、新技術の導入遅延など |
| 経営的リスク | 事業経験の浅さ、販売網の未整備、マネジメント体制の未成熟 |

私の経験上、補助金申請ではリスクを書くこと自体が悪なのではなく、「問題を想定し、それにどう対処しようとしているか」こそが評価の対象となっているようです。問題が発生する前から、将来のリスクを分析し、その弱点に対する対策をとれば事業の成功率が高まるのは当然の事です。
補助金の審査員はその点を評価しているようです。
4. リスクの洗い出し方:社内要因と社外要因
リスクを記述する際は、まず「内側」と「外側」からの視点でリスクを洗い出すことが有効です。
✅ 社内要因からのリスク
- 技術やノウハウの不足
- キーパーソンの業務負荷過多
- 売上シミュレーションの精度不足
- 経営者の過去の失敗経験 など
✅ 社外要因からのリスク
- 顧客ニーズの変化
- 価格競争の激化
- 為替・仕入れ価格の変動
- 法改正によるルール変更
- 地域特性や競合他社の動向
これらをSWOT分析などと組み合わせることで、網羅的かつ論理的にリスクを抽出しやすくなります。
弊社の経験上、分析手法にSWOTを活用することは採択率を上げるために効果的といえます。
5. リスクの書き方4ステップ
リスクを効果的に事業計画書へ記載するには、次の4ステップで整理するのがオススメです。
ステップ①:課題・リスクを明確にする
例:新商品の市場ニーズがまだ明確でなく、売上が計画どおりに立たない可能性がある。
ステップ②:リスクの背景・原因を分析する
例:市場調査が一部地域に偏っていた/販路が一部顧客層に限定されている。
ステップ③:対策・備えの記載
例:複数地域でモニター調査を実施し、ニーズの検証を行う。対象顧客を拡張した販路開拓も進行中。
ステップ④:予備のプランや対応策も併記する
例:想定売上を達成できない場合に備え、既存取引先との共同販売プランも検討している。
この4ステップに沿って書くことで、説得力が高まり、計画全体が現実的かつ信頼感のある内容に仕上がります。
6. 書いてはいけないリスクのNG例
今までは「事業計画書に弱点は書くべきだ」と説明してきました。しかし、当然ながらリスクは何でも書けばいい、というわけではありません。特に避けたいのが以下のパターンです。
| NG例 | 問題点 |
|---|---|
| 「大きなリスクは特にないと考えている」 | 楽観的すぎる印象。リスクへの備えがないと見なされやすい |
| 「外部要因に左右されるが、今は順調」 | 他人任せ・無責任に見える可能性 |
| 「資金繰りが不安だがなんとかなる」 | 解決策が曖昧で、経営管理能力の欠如を疑われる |
審査官は、ポジティブな幻想よりも誠実で現実的な見通しを好みます。
弱点を補う姿勢があるかどうかが、信頼に直結するのです。
7. リスクの解決策は「ゼロにする」必要なし
すべてのリスクに「完全解決」を求める必要はありません。重要なのは、「起こりうる問題に対して、どこまで準備しているか」「それに向けた行動を開始しているか」です。
実際の採択事例でも、「○○というリスクがあるが、代替策として○○を準備中である」といった形で段階的な取り組みの途中を記載している事業者が多く見られます。
つまり、『リスク=不採択』ではなく、リスクへの対応策の明確さが重要というわけです。

「弱点」に対し数値など客観的なデータで示された現実的な解決策を示せるかが採択を勝ち取るための重要ポイントです。
8. SWOT分析との連携で説得力アップ
リスクの洗い出しには、SWOT分析が非常に有効です。以下の4つの視点から分析し、それぞれに対応するリスクを抽出すると、論理性と網羅性がぐっと高まります。
| SWOT分析 | 内容 | 関連するリスク例 |
|---|---|---|
| Strength(強み) | 独自の技術、高品質な製品 | 特定スタッフ依存による技術継承問題 |
| Weakness(弱み) | 人手不足、資金力の低さ | 計画の実行に必要な運転資金不足の懸念 |
| Opportunity(機会) | ニッチ市場の拡大、法改正の追い風 | 需要予測の不確実性/競合の参入スピード |
| Threat(脅威) | 市場縮小、国際情勢の変化 | 輸入コストの高騰/顧客ニーズ変化への対応遅れなど |
SWOTを活用すれば、「なぜこのリスクに注目するのか」という背景説明にもつながり、審査官への説得力が増します。
9. リスクを味方にする!事業計画書の戦略的な書き方
リスクを堂々と「書く」ことで、次のような効果を得ることができます。
- 信頼感の獲得:「現実を見据えた冷静な経営者」としての印象
- 採択率の向上:対策が明確であれば、むしろ安心材料になる
- 計画の精度向上:記載することで、自社の課題が明確化される
- 社内の結束力アップ:リスク共有が社内改革のきっかけになることも
つまり、「リスク」は書かない方が怖いのです。
それを前提に「どうすれば乗り越えられるか?」を描けるかどうかが、事業計画の質を左右します。
10. 【まとめ】リスクは「書かない」より「活かす」時代へ
- リスクは審査官への不安要素ではなく、「信頼材料」にもなり得る
- 審査官は“完璧な計画”よりも、“現実を見据えた堅実な経営”を評価
- 書き方にはコツあり:背景→課題→対策→代替策の4ステップで整理
- SWOT分析と併用すれば、論理的・網羅的な記述がしやすくなる
- 実例のように、具体的な対応を明記すれば、弱点も評価対象に変わる
11. 📘「ものづくり補助金の教科書」でさらに学ぶ
もしあなたが「補助金申請を本格的に進めたい」「もっと実践的な書き方を知りたい」とお考えであれば、
当社が提供する無料記事「ものづくり補助金の教科書」もぜひご覧ください。

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。
補助金のプロを目指すなら