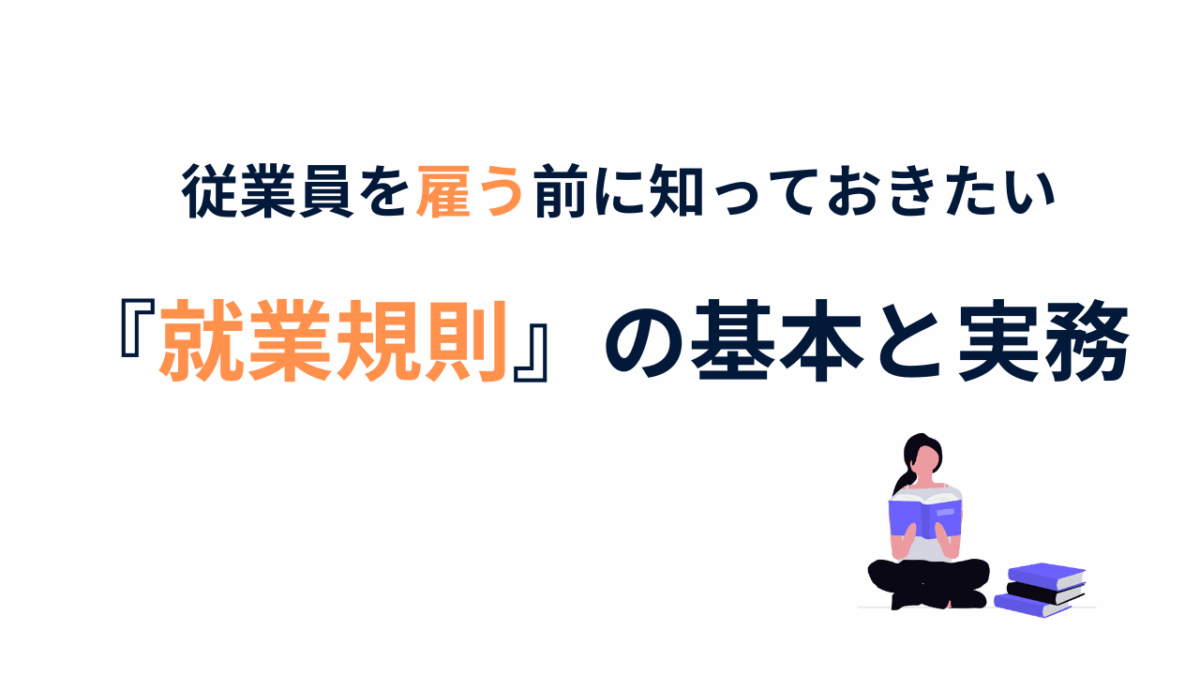📝 はじめに:事業拡大とともに必要になる「就業規則」という備え
事業が軌道に乗り、従業員の雇用を本格的に検討し始めるタイミングは、経営者にとって大きな節目です。特に、従業員数が10人を超える規模になったとき、企業には「就業規則」の作成と届け出という法的義務が発生します。
就業規則とは、企業と従業員の間で交わされる“働く上での約束事”を明文化したもの。労働時間、賃金、休日、退職など、労働条件の基本を網羅するだけでなく、トラブルを未然に防ぎ、企業の信頼性を高める役割も果たします。

しかし、初めて就業規則を作成する場合、何をどこまで記載すればよいのか、誰に相談すればよいのか、どのような手続きが必要なのか、戸惑うことも多いでしょう。そこで本記事では、これから従業員を雇用する方や、事業規模が拡大しつつある方に向けて、就業規則の基本から実務的な運用までを体系的に解説します。
以下の章では、就業規則の定義、作成義務のある企業の条件、監督機関と罰則、専門家への依頼方法、記載すべき内容、作成から届け出までの流れ、そして周知方法まで、順を追って詳しくご紹介します。
第1章:就業規則とは
🔍 就業規則の定義と目的
就業規則とは、企業が労働者に対して定める職場のルールブックです。労働基準法第89条により、一定の条件を満たす事業場には作成・届出が義務付けられています。具体的には、労働時間、賃金、休日、退職など、労働条件に関する基本事項を網羅し、企業と従業員の間で共通の認識を持つための文書です。
この規則は、単なる社内文書ではなく、法的効力を持つものとして、労働契約の補完的役割を果たします。労働契約が個別の合意であるのに対し、就業規則は全従業員に対して一律に適用されるルールです。
⚖️ 就業規則の法的性質
就業規則は、企業が一方的に定めることができますが、労働者の不利益変更は原則として認められません。判例では「合理性」と「周知性」が重要視されており、労働者に不利益となる変更を行う場合は、労働者代表との協議や説明責任が求められます。
また、就業規則は労働契約の内容としてみなされるため、労働者がその内容を知らなかった場合でも、周知されていれば効力を持ちます。

🛡️ トラブル予防の観点からの重要性
就業規則が整備されていない企業では、労働トラブルが発生した際に対応が後手に回ることが多く、解雇や懲戒処分の正当性が問われるケースもあります。逆に、明確な規則があれば、企業は法的根拠を持って対応でき、労働者も安心して働くことができます。
例えば、ハラスメント防止、テレワークのルール、副業の可否など、現代の働き方に対応した規定を盛り込むことで、企業の信頼性や働きやすさが向上します。
第2章:就業規則が必要な会社とは
🏢 就業規則の作成義務がある企業とは
労働基準法第89条により、「常時10人以上の労働者を使用する事業場」は、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられています。ここで重要なのは「事業場単位」である点です。企業全体の人数ではなく、支店や営業所など、各拠点ごとに10人以上の労働者がいるかどうかで判断されます。
また、「労働者」には正社員だけでなく、契約社員、パートタイマー、アルバイトも含まれます。雇用形態に関係なく、雇用契約を結んでいる者はすべてカウント対象です。

【注意】よくある勘違いです
❌️就業規則の作成及び届け出は任意
⭕️常時10人以上の従業員を雇用する場合は届け出が義務
❌️常時10人以上の従業員は正社員を指す
⭕️「労働者」には正社員だけでなく、契約社員、パートタイマー、アルバイトも含まれます
❌️届け出をしなくても特に罰則はない
⭕️就業規則の作成・届出義務に違反した場合、30万円以下の罰金
初めて人を雇う方はご注意下さい!
📌 義務ではないが作成が推奨される企業
常時10人未満の事業場には法的義務はありませんが、就業規則の作成は強く推奨されます。理由は以下の通りです:
- ✅ 労働条件の明文化によるトラブル予防
- ✅ 従業員の定着率向上と信頼感の醸成
- ✅ 労働基準監督署の調査時に備えた体制整備
- ✅ 労働契約書だけでは網羅できない細則の補完
特に、従業員数が増加傾向にあるスタートアップや、複数の雇用形態を抱える企業では、早期に就業規則を整備しておくことで、後々の制度改定やトラブル対応がスムーズになります。
📊 業種・規模別の実態と傾向
実際には、義務のある企業でも就業規則を未整備のまま運営しているケースが少なくありません。特に、飲食業や小売業など、現場主導で運営される業種では、制度整備が後回しになる傾向があります。
一方で、IT企業や製造業など、労働時間や業務内容が明確な業種では、就業規則の整備が進んでいる傾向があります。最近では、テレワークや副業解禁など、働き方の多様化に対応するために、就業規則の見直しを行う企業も増えています。
第3章:就業規則の監督機関はどこ?作成しない場合の罰則とは
🏛️ 就業規則の監督機関:労働基準監督署とは
就業規則の作成・届け出に関して監督を行うのは、厚生労働省の出先機関である「労働基準監督署(労基署)」です。労基署は、労働基準法をはじめとする労働関係法令の遵守を監視・指導する役割を担っており、企業が適切に就業規則を整備・運用しているかを確認する権限を持っています。
企業が就業規則を作成・変更した場合は、所轄の労基署に届け出る必要があります。届け出の際には、以下の書類が必要です:
- 就業規則本体(正本・写し)
- 労働者代表の意見書(意見を聴取したことを証明する書類)
この「意見書」は、労働者の同意を得る必要はありませんが、意見を聴く手続きは必須です。意見書がない場合、労基署は受理してくれません。
⚠️ 就業規則を作成しない場合のリスクと罰則

労働基準法第120条により、就業規則の作成・届出義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。これは「行政罰」ではなく「刑事罰」に該当するため、悪質な場合には企業名が公表されることもあります。
ただし、実際には「即座に罰金が科される」わけではなく、まずは労基署から是正勧告が行われ、改善の機会が与えられます。それでも改善が見られない場合に、罰則が適用される流れです。
🔥 トラブル時の“盾”にも“矛”にもなる就業規則
就業規則が未整備のまま労働トラブルが発生した場合、企業は「社内ルールが存在しない」状態で対応を迫られることになります。たとえば、懲戒処分や解雇を行う際、就業規則にその根拠がなければ、処分の正当性が認められず、裁判で不利になる可能性があります。
逆に、就業規則が整備されていれば、企業は「事前に周知されたルールに基づいて処分を行った」と主張でき、法的な防御力が格段に高まります。
🧭 まとめ:就業規則は“義務”であると同時に“備え”
就業規則の作成と届け出は、単なる法令遵守のためだけでなく、企業と従業員の信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐための重要なステップです。特に、労働環境が多様化する現代においては、就業規則の整備が企業の持続的成長を支える基盤となります。
第4章:就業規則を外部作成依頼する場合の専門家とは
👨⚖️ 就業規則の作成依頼にオススメ:社会保険労務士(社労士)とは

就業規則の作成を外部に依頼する場合、最も一般的で信頼性の高い専門家が「社会保険労務士(社労士)」です。社労士は、労働法や社会保険制度に精通した国家資格者であり、企業の人事・労務管理を法的観点からサポートする役割を担っています。
特に就業規則の作成においては、以下のようなメリットがあります:
- ✅ 法令遵守を前提とした内容設計
- ✅ 業種・規模に応じたカスタマイズ
- ✅ 労働基準監督署への届け出代行
- ✅ 労使トラブルを未然に防ぐリスク管理
社労士は、単に文書を作成するだけでなく、企業の実態や課題をヒアリングした上で、実効性のある規則を提案してくれる点が大きな強みです。
⚖️ 弁護士との違いと連携の必要性
弁護士も労働法の専門家ですが、主に「紛争対応」や「訴訟代理」に強みを持っています。就業規則の作成そのものは社労士が得意とする領域ですが、以下のようなケースでは弁護士との連携が有効です:
- 🔹 解雇・懲戒処分に関する規定の法的リスク評価
- 🔹 ハラスメント対応や内部通報制度の整備
- 🔹 労働組合との交渉が必要な場合
社労士が制度設計を行い、弁護士が法的リスクをチェックするという連携体制を取ることで、より盤石な就業規則が完成します。
💰 外部委託の費用相場と注意点
就業規則の作成を社労士に依頼する場合の費用は、企業の規模や内容の複雑さによって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです:
| 費用相場(税別) | 備考 | |
|---|---|---|
| 就業規則の新規作成 | 約10から30万円 | オーダーメードの場合 |
| 規則の見直し・改定 | 約5から15万円 | 法改正対応など |
| 労働基準監督署への届出代行 | 約1から3万円 | オプション料金の場合が多い |
※テンプレートをベースにした簡易作成であれば、5万円以下で対応する事務所もありますが、企業の実態に合わない内容になるリスクもあるため注意が必要です。
※単発業務ではなく、就業規則の作成を含めた社労士業務全般支援を年間契約で提供する社労士事務所も多いです。
🧩 テンプレート vs オーダーメイド
最近では、インターネット上で無料・有料の就業規則テンプレートが多数公開されています。これらを活用することで、一定のコスト削減は可能ですが、以下のような注意点があります:
- ❌ 自社の業態・働き方に合っていない可能性
- ❌ 法改正に対応していない古い内容が含まれることも
- ❌ 労働者とのトラブル時に「実態と規則が乖離している」と指摘されるリスク
一方、オーダーメイドで作成する場合は、企業の実情に即した内容となり、将来的な制度改定にも柔軟に対応できます。特に、テレワーク、副業、フレックスタイム制など、現代的な働き方を導入している企業では、テンプレートでは対応しきれない細則が必要になることが多いです。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
第5章:就業規則では何を記載するのか
— 絶対的必要記載事項・相対的必要記載事項・任意記載事項とは —
📘 就業規則の構成と記載項目の分類

就業規則は、単なる社内ルールではなく、労働条件の法的根拠となる文書です。そのため、記載すべき内容は労働基準法によって明確に分類されています。主に以下の3つに分けられます:
- ✅ 絶対的必要記載事項
- ✅ 相対的必要記載事項
- ✅ 任意記載事項
それぞれの性質と記載例を詳しく見ていきましょう。
✅ 絶対的必要記載事項
労働基準法第89条により、必ず記載しなければならない項目。
これらは、すべての労働者に共通して適用される基本的な労働条件です。記載漏れがあると、労働基準監督署から是正指導を受ける可能性があります。
| 具体例 | |
|---|---|
| 始業・終業時刻、休憩時間 | 9:00~18:00、12:00~13:00休憩など |
| 休日・休暇 | 土日祝日休み、有給休暇の取得方法 |
| 賃金 | 基本給、手当、支払い方法、締日・支払日 |
| 退職・解雇 | 退職手続き、解雇事由、予告期間など |
これらは、労働者の生活に直結するため、曖昧な表現や例外規定が多すぎるとトラブルの原因になります。具体的かつ明確に記載することが重要です。
📌 相対的必要記載事項
制度を導入している場合に限り、記載が義務となる項目。
企業が以下のような制度を設けている場合は、その内容を就業規則に明記する必要があります。制度が存在しない場合は記載不要です。
| 具体例 | |
|---|---|
| 退職手当 | 勤続年数に応じた支給額、支給条件 |
| 賞与 | 年2回支給、業績連動型など |
| 表彰・制裁 | 勤続表彰、懲戒処分の種類と手続き |
| 安全衛生 | 健康診断の実施、産業医の配置など |
これらは、企業の裁量で制度設計が可能ですが、曖昧な運用や口頭での説明だけでは法的効力が弱くなります。制度の有無にかかわらず、導入するなら明文化が必須です。
📝 任意記載事項
法的義務はないが、記載することで運用が安定する項目。
現代の働き方や企業文化に対応するため、任意記載事項の重要性は年々高まっています。特に、以下のような項目は、記載しておくことでトラブル予防や従業員の安心感につながります。
| 具体例 | |
|---|---|
| 副業・兼業 | 許可制、届出制、禁止の範囲など |
| テレワーク | 対象業務、勤務時間、通信費の扱い |
| ハラスメント防止 | 定義、相談窓口、対応手順 |
| 服装・身だしなみ | 制服の有無、髪型・アクセサリーの制限 |
| SNS利用 | 業務外での発信ルール、企業名の使用制限 |
任意記載事項は、企業の価値観や働き方を反映する“企業らしさ”の表現でもあります。従業員との信頼関係を築くうえで、こうした細則の整備は非常に有効です。
🧭 記載内容の見直しと定期的な更新
就業規則は一度作成すれば終わりではなく、法改正や働き方の変化に応じて定期的な見直しが必要です。特に、以下のようなタイミングでは更新が推奨されます:
- 法律改正(例:育児・介護休業法、労働時間法制)
- 新制度の導入(例:フレックスタイム制、在宅勤務)
- 労働トラブルの発生後の再発防止策
更新時には、労働者代表の意見聴取と労基署への届け出が必要になるため、社労士などの専門家と連携して進めるのが望ましいです。
第6章:就業規則の作成から届け出までの流れ
🛠️ ステップ①:草案の作成
まずは、企業の実態に即した就業規則の草案を作成します。ここでは、以下の点を意識することが重要です:
- ✅ 法令に準拠した記載項目の網羅(第5章参照)
- ✅ 自社の業種・働き方に合った制度設計
- ✅ 労働者にとって理解しやすい表現
テンプレートを活用する場合でも、必ず自社の実情に合わせてカスタマイズする必要があります。特に、テレワーク、副業、フレックスタイム制などを導入している企業では、制度の運用ルールを明確に記載することが求められます。
👥 ステップ②:労働者代表への意見聴取
草案が完成したら、労働者代表から意見を聴取します。これは、労働基準法第90条に基づく義務であり、以下の点に注意が必要です:
- 労働者代表は、民主的な手続きで選出された者であること
- 意見聴取は「同意」ではなく「意見を聞く」ことが目的
- 意見書には、代表者の署名または記名押印が必要
この意見書は、就業規則の届け出時に労働基準監督署へ提出する必須書類です。意見が反映されていなくても、聴取した事実があれば受理されます。
🏛️ ステップ③:労働基準監督署への届け出
意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に就業規則を届け出ます。提出方法は以下のいずれかです:
- 郵送(控えを返送してもらうための返信用封筒を同封)
- 窓口持参(その場で受理印をもらえる)
- 電子申請(e-Govを利用)
提出する書類は以下の通りです:
- 就業規則(正本・写し)
- 労働者代表の意見書
- 添付書類(必要に応じて:賃金規程、退職金規程など)
受理された場合、控えに受理印が押されて返却されます。これが「届け出済み」の証拠となります。
📂 ステップ④:受理通知の確認と保管
労基署からの受理通知(受理印付きの控え)は、企業内で厳重に保管しておきましょう。これは、将来的に労働トラブルが発生した際に「法的に有効な就業規則である」ことを証明する重要な書類です。
また、就業規則の改定を行う際にも、過去のバージョンとの比較や履歴管理が必要になるため、改定履歴を残しておくことが望ましいです。

📣 ステップ⑤:社内への周知準備
届け出が完了したら、最後に「周知」が必要です。これは、就業規則が法的効力を持つための必須条件です。周知方法については次章で詳しく解説しますが、ここでは以下の点を押さえておきましょう:
- 労働者がいつでも内容を確認できる状態にすること
- 書面配布、社内掲示、イントラネット掲載などが有効
- 周知の証拠(署名、記録)を残しておくと安心
🧭 まとめ:作成から届け出までの流れは“法的整備”と“社内浸透”の両輪
就業規則の整備は、単なる書類作成ではなく、企業の労務管理体制を法的に確立し、従業員との信頼関係を築くためのプロセスです。各ステップを丁寧に進めることで、企業のリスク管理力と組織力が大きく向上します。
第7章:就業規則の周知方法とは
— 法的効力を持たせるための“最後の一手” —
📣 なぜ“周知”が必要なのか?
就業規則は、作成して労働基準監督署に届け出るだけでは、法的効力を持ちません。労働基準法第106条により、「労働者に周知されていること」が効力発生の条件とされており、周知されていない就業規則は、たとえ内容が正しくても無効と判断される可能性があります。
つまり、就業規則は「作る」「届け出る」だけでなく、「伝える」ことで初めて意味を持つのです。
📂 周知の具体的な方法
労働基準法では、周知の方法について明確な形式は定められていませんが、以下のような手段が一般的かつ有効とされています:
| 方法 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 書面配布 | 印刷して全従業員に配布 | 物理的に残る証拠になる | 紛失リスク、更新時の再配布が必要 |
| 社内掲示 | 休憩室や事務所に掲示 | 常時閲覧可能な状態を維持できる | 掲示場所の選定が重要 |
| イントラネット掲載 | 社内システムにPDF等で掲載 | 更新が容易、検索性が高い | アクセス権限の管理が必要 |
| 電子メール通知 | 就業規則の改定時などに送信 | 受信履歴が残る | 添付ファイルの管理が必要 |
複数の方法を併用することで、周知の確実性を高めることができます。特に、テレワークや多拠点展開を行っている企業では、イントラネットやクラウドストレージの活用が効果的です。
🖊️ 周知の“証拠”を残す工夫

就業規則が周知されていたかどうかは、トラブル発生時に争点となることがあります。そのため、以下のような証拠を残しておくことが推奨されます:
- ✅ 書面配布時の受領サイン
- ✅ 電子メールの送信履歴
- ✅ イントラネット上のアクセスログ
- ✅ 周知説明会の開催記録(議事録、写真など)
これらの記録は、万が一裁判になった場合に「就業規則が周知されていた」ことを証明する重要な資料となります。
⚠️ 周知が不十分な場合のリスク
周知が不十分な場合、以下のようなリスクが生じます:
- ❌ 懲戒処分や解雇が無効と判断される可能性
- ❌ 労働者が「知らなかった」と主張し、トラブルが長期化
- ❌ 労働基準監督署から是正指導を受ける可能性
特に、懲戒処分や賃金規定など、労働者に直接影響を与える項目については、周知の有無が法的判断の分かれ目になることが多いため、慎重な対応が求められます。
🧭 まとめ:周知は“制度の定着”と“信頼構築”の鍵
就業規則の周知は、単なる法的要件ではなく、企業文化の浸透と従業員との信頼関係を築くための重要なステップです。ルールが明確に伝わっている職場では、従業員の安心感が高まり、トラブルの予防にもつながります。

弊社では、士業や経営コンサル等専門性の高いお仕事をされている方を様々なシーンでご支援しています。
下記は、補助金や銀行融資を学べる講座のご案内です。
ご興味がある方は是非ご覧下さい。
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
士業やコンサルとして中小・零細企業の社長様から要望の多い補助金支援業務について学びたい方はこちら。補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
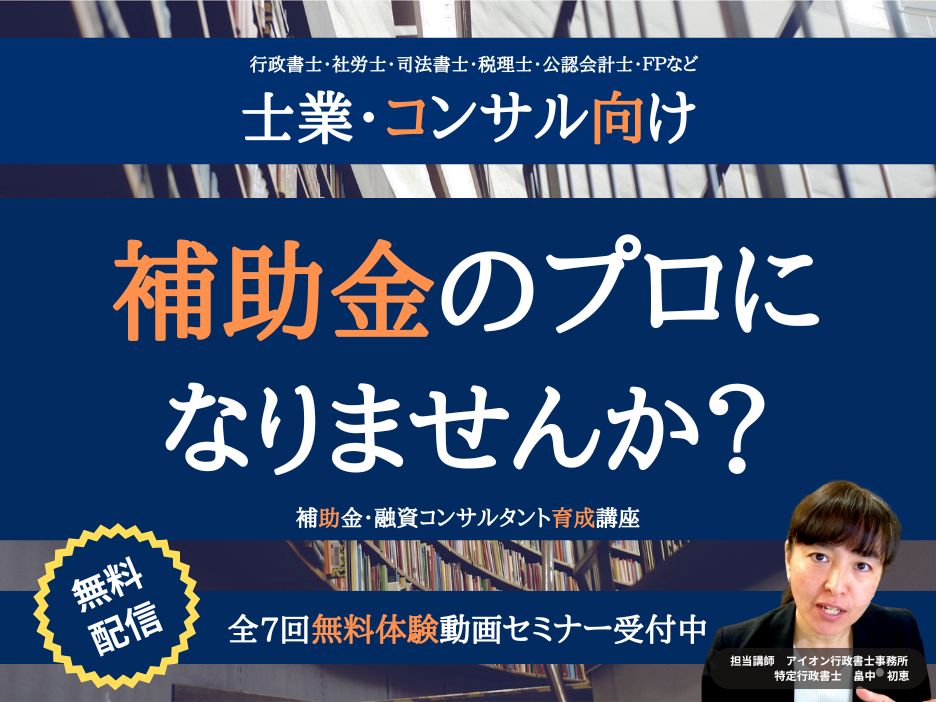
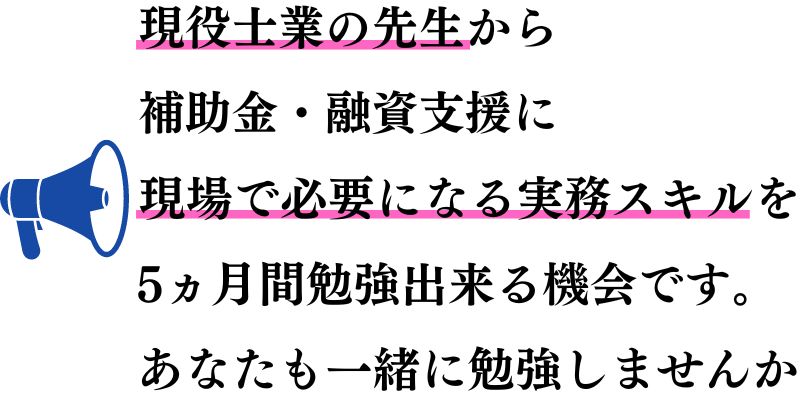

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。