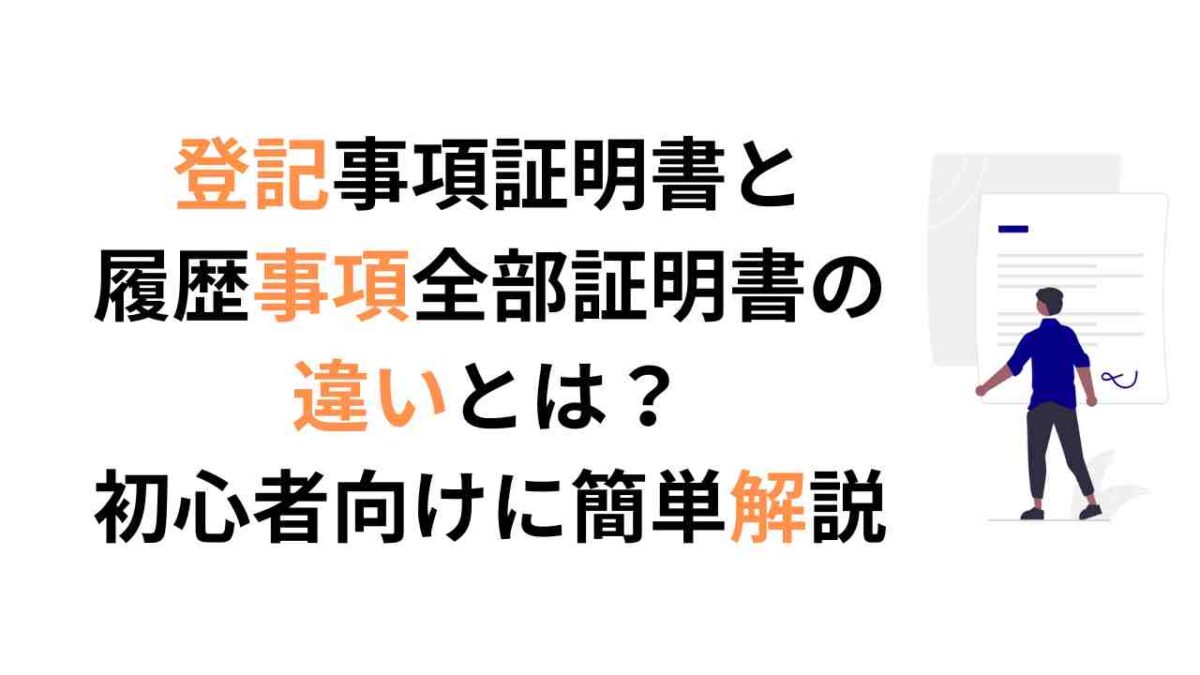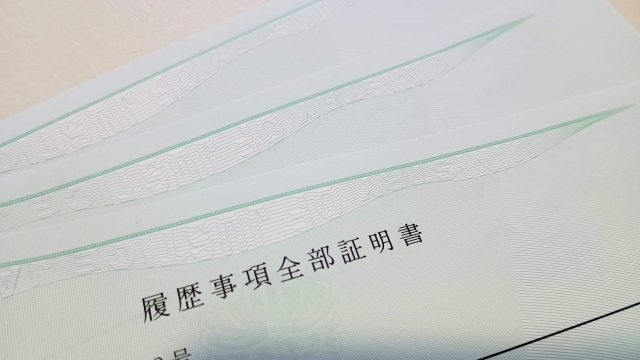
法人登記に関する手続きでは、「登記事項証明書を提出してください」と言われることがあります。しかし、実際には登記事項証明書にはいくつかの種類があり、目的に応じて使い分ける必要があります。中でも「履歴事項全部証明書」の提出が多いと思いますが他との違いが分かりづらく、初めての方は戸惑うことも少なくありません。
この記事では、登記事項証明書の種類とそれぞれの特徴、よく登場する「履歴事項全部証明書」についてと証明書の取得方法や注意点について、初心者にもわかりやすく解説します。
📘動画での解説はこちら
出典元:行政書士畠中初恵のかんたん解説チャンネル → https://www.youtube.com/@hojyokin
📘 登記事項証明書とは?
登記事項証明書とは、法人や不動産などの登記情報を証明するための公的な書類です。会社の設立や変更、所在地、代表者などの情報が法務局に登記されており、その内容を第三者に証明するために発行されます。
登記事項証明書は、契約や融資申請、補助金申請など、さまざまな場面で必要とされる重要な書類です。
🗂 登記事項証明書の種類と特徴
登記事項証明書には「全部事項証明書」と「一部事項証明書」があります。そして、それぞれに表に記載のものがあります。
まず、「履歴事項証明書」は、法人の登記している内容のすべてを現時点から約3年分記載した証明書です。補助金などの手続きにおいて会社の実在を確認する際に使用されます。
一方、「現在事項証明書」は、現在有効な登記情報のみを記載した証明書です。過去の変更履歴は含まれておらず、現在の会社情報だけを確認したい場合に適しています。
また、「閉鎖事項証明書」は、履歴事項証明書に記載のない古い情報(閉鎖事項)を証明するものです。会社の設立時からの状態が法務局に残っている範囲でわかるため、会社の沿革等の証明に使用できます。
| 証明書の種類 | 記載内容の範囲 | 主な用途・特徴 |
|---|---|---|
| 履歴事項証明書 | 現在から約3年前までの全ての登記事項 | 会社の実在や現在状態を確認したいとき |
| 現在事項証明書 | 現在有効な登記事項のみ | 現在の会社情報(代表者・所在地など)を確認したいとき |
| 閉鎖事項証明書 | 履歴事項証明書で記載されない古い登記事項 | 会社設立などまでさかのぼって確認したいとき |
つまり、よく使用される「履歴事項全部証明書」とは、「現在から約3年前までの全ての登記事項の全部」が記載されている証明書となります。
これらの証明書はすべて「登記事項証明書」という総称のもとに分類されており、目的に応じて適切な種類を選ぶことが重要です。
📄 履歴事項全部証明書の役割と記載内容
履歴事項全部証明書は、直近3年の会社の“履歴書”のような役割を果たします。所在地の変更、代表者の交代、資本金の増減など、約3年間の会社の「動き」が記録されています。
記載される主な項目には、商号(会社名)、本店所在地、会社の目的、資本金の額、役員の氏名と任期、設立年月日などがあります。これらの情報は、融資審査や補助金申請、M&Aなどの場面で、会社の信頼性や沿革を確認するために使用されます。
履歴事項全部証明書は情報量が多いため、提出先によっては不要な情報が含まれてしまうこともあります。そのため、提出先の指示に従って、「一部」にする、あるいは「現在事項のみ」にするなど、必要な種類の証明書を選ぶことが大切です。
🔍 他の証明書との違いと使い分け方
「履歴事項全部証明書」と「現在事項証明書」の違いは、直近約3年の過去の履歴が記載されているかどうかです。書き換えられた古い事項にはアンダーラインが入っています。「履歴事項全部証明書」は、「現在事項証明書」に比べて変更履歴を含むため、より詳細な情報が必要な場面に適しています。
一部事項証明書は、特定の項目だけを抜粋して記載するため、必要最小限の情報で済む場合に便利です。例えば、代表者の氏名だけを確認したい場合などに使用されます。代表者の変更の前後を証明したい場合などに「一部事項証明書」の取得が考えられます。
証明書の種類を誤って提出すると、再提出を求められることもあるため、事前に提出先に確認することが重要です。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
🏛 証明書の取得方法と注意点
登記事項証明書は、法務局の窓口または郵送で取得することができます。
取得手数料は、登記所の窓口で登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料は600円のところ、オンライン請求をご利用いただくと、請求書を郵送で受け取る場合の手数料は520円、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合の手数料は490円となります。(2025年10月現在)
💡ご注意ください:オンライン請求について
公的な説明には「オンライン請求」と記載されていますが、これにより、登記事項証明書の請求・支払い・取得までをすべてインターネット上で完結できるように誤解される可能性があります。
しかし実際には、オンラインで可能なのは「請求」だけで、証明書は「紙」で発行されます。※2025年時点
証明書の受け取りは、以下のいずれかの方法が必要です:
・窓口での受領
・郵送による受領
「オンライン請求=すべてオンラインで完了」ではありません。ご利用の際はご注意ください。

証明書の有効期限について
証明書には、提出先の行政機関や団体によって有効期限が定められている場合があります。一般的には「発行日から3か月以内」の証明書の提出を求められることが多く、これが現在の主流となっています。
そのため、有効期限を過ぎた証明書を提出してしまうと、再取得が必要となる場合があります。こうしたトラブルを避けるためにも、提出前に証明書の発行日を必ず確認するようにしましょう。
なお、「発行日から3か月以内」といった期限は、証明書を受け取る側が独自に定めた社内ルールであることがほとんどです。したがって、証明書を提出する際は、必ず事前に提出先のルールを確認することが重要です。
⚠️ よくある誤解と提出時のポイント
「登記事項証明書」と言われた場合、どの種類を指しているかは確認することが重要です。その際は以下の内容に注目するとよいでしょう。
・「全部」か「一部」なのか
・「履歴」を含むのか「現在」だけなのか
また、「履歴事項全部証明書」は情報量が多いため、個人情報保護の観点から提出先によっては不要な場合もあります。必要以上の情報を提出しないよう、指示に従って適切な種類を選びましょう。
📌 まとめ:目的に応じた証明書選びが重要
「履歴事項全部証明書」は手続きにおいて、よく登場する書類です。
証明書の種類を正しく理解し、目的に応じて適切なものを選ぶことで、手続きがスムーズに進み、余計な手間や再提出を防ぐことができます。
補助金や融資申請においても、登記情報の正確な提出は信頼性の証となります。これから申請を検討されている方は、証明書の種類と取得方法をしっかり把握しておきましょう。
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
士業やコンサルとして中小・零細企業の社長様から要望の多い補助金支援業務について学びたい方はこちら。補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
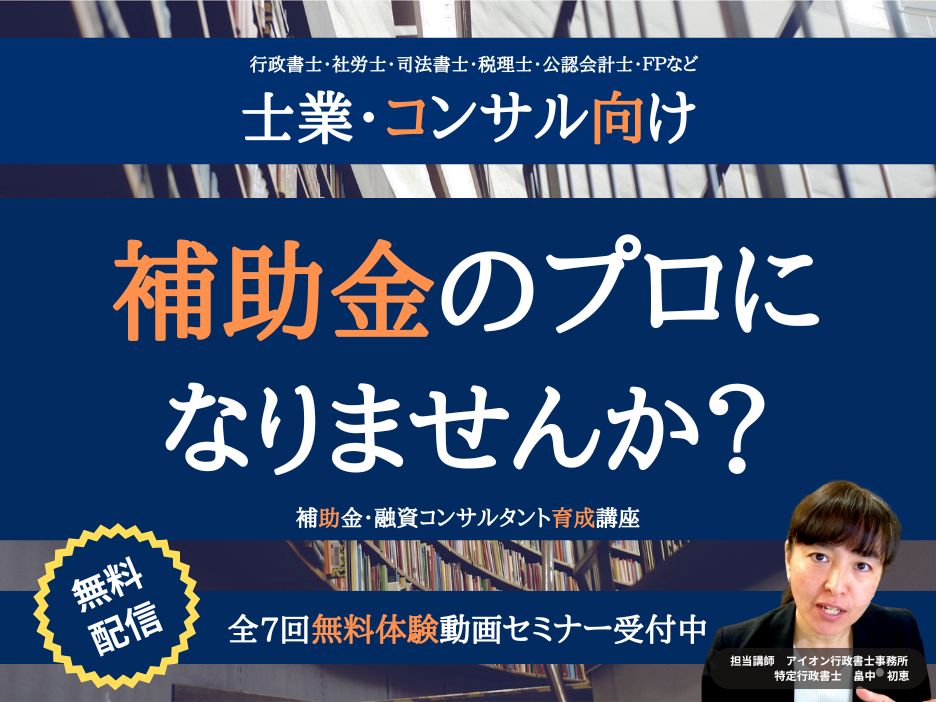
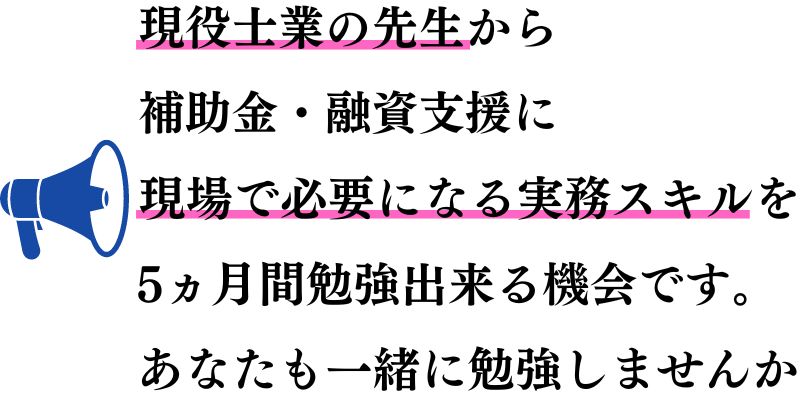

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。