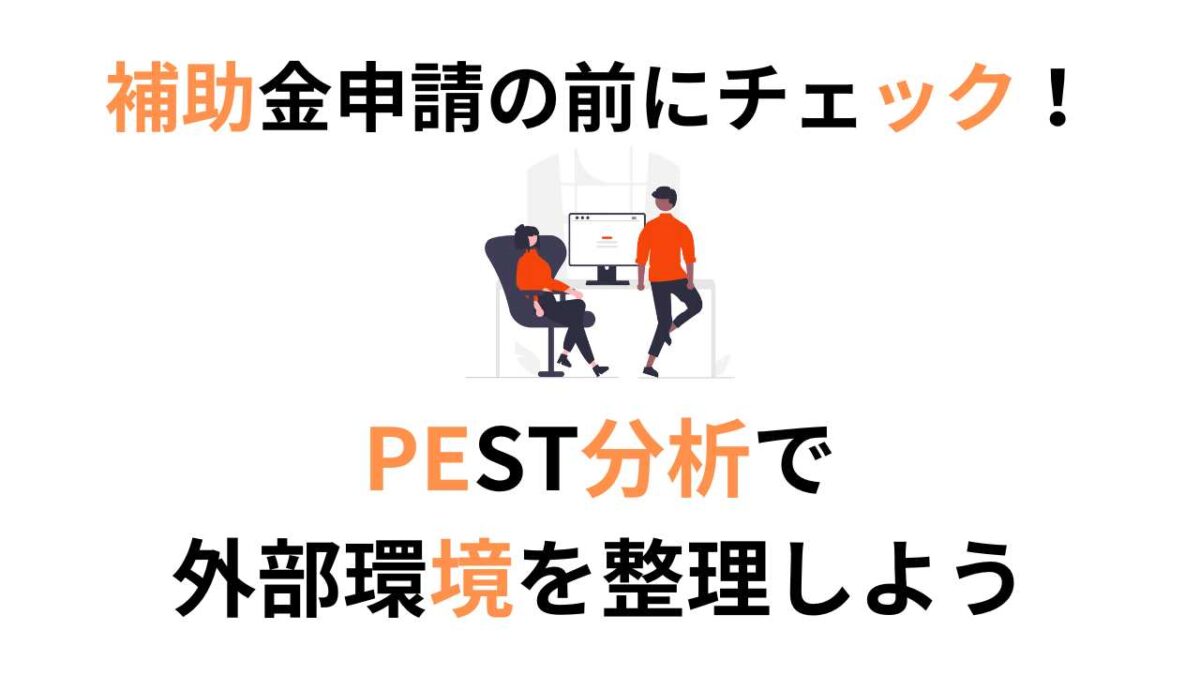1. PEST分析とは?
補助金申請や事業計画書の作成において、「自社を取り巻く環境」を的確に把握することは、審査員に納得感を与えるうえで非常に重要です。
その外部環境を体系的に整理するためのフレームワークが「PEST分析」です。
🔍 PEST分析の概要
PEST分析とは、企業や事業を取り巻く外部環境を以下の4つの視点から整理する手法です。
- P(Politics)政治的要因
- E(Economy)経済的要因
- S(Society)社会的要因
- T(Technology)技術的要因
これらの要素は、企業の努力では変えられない「マクロ環境」に該当します。つまり、PEST分析は「自社の外側で起きている変化」を読み解くためのツールなのです。
🧭 SWOT分析との違いと補完関係
PEST分析とよく比較されるのが「SWOT分析」です。両者の違いは以下の通りです。
| 分析手法 | 対象 | 目的 |
|---|---|---|
| PEST分析 | 外部環境(社会全体の変化) | 市場や業界の変化を把握する |
| SWOT分析 | 内部環境+外部環境 | 自社の強み・弱みと機会・脅威を整理する |
PEST分析は、SWOT分析の「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」を深掘りするための前段階として活用されることが多く、両者を組み合わせることで、より説得力のある事業計画書が作成できます。
📌 補助金申請におけるPEST分析の活用シーン
補助金申請では、事業計画書の中で「市場環境」や「社会的背景」について触れることが求められるケースが多くあります。たとえば:
- 「地域の高齢化により、介護サービスの需要が高まっている」
- 「政府の脱炭素政策により、環境対応型製品のニーズが増加している」
- 「コロナ禍を経て、非接触型サービスへの関心が高まっている」
こうした背景をPEST分析で整理することで、事業の必要性やタイミングの妥当性を論理的に説明できるようになります。審査員にとっても、「この事業は社会の流れに合っている」と納得しやすくなるのです。
2. PESTの4要素をわかりやすく解説
PEST分析では、外部環境を「政治」「経済」「社会」「技術」の4つの視点から整理します。それぞれの要素が事業にどのような影響を与えるかを理解することで、補助金申請における事業の必要性やタイミングを論理的に説明できるようになります。
🏛️ P(Politics)政治的要因
政治的要因とは、政府の政策、法制度、規制、補助金制度など、行政の動きによって事業に影響を与える要素です。たとえば、ある業種に対して国が重点支援を行っている場合、その業種に属する事業は補助金の対象となりやすくなります。
補助金申請では、以下のような視点が重要です:
- 自社の事業が国や自治体の重点施策に合致しているか
- 法改正や規制緩和が事業に追い風となっているか
- 地域振興や雇用創出など、政策的な目的に貢献しているか
こうした政治的背景を事業計画書に盛り込むことで、「この事業は社会的に意義がある」と伝えることができます。
💴 E(Economy)経済的要因
経済的要因は、景気の動向、物価の変動、金利、為替、雇用状況など、マクロ経済の変化が事業に与える影響を指します。たとえば、原材料価格の高騰や人件費の上昇は、事業の収益性に直結します。
補助金申請では、以下のような点に着目しましょう:
- 業界全体の市場規模や成長性
- 資金調達の難易度や金融環境
- 消費者の購買力や支出傾向
経済的要因を分析することで、事業の収益性や持続可能性を客観的に説明できるようになります。
🧑🤝🧑 S(Society)社会的要因
社会的要因は、人口構成、ライフスタイル、価値観、教育水準、地域性など、人々の生活や文化に関わる要素です。たとえば、高齢化が進む地域では、介護や健康関連のサービスに対するニーズが高まります。
補助金申請では、以下のような視点が有効です:
- 地域住民のニーズや課題に対応しているか
- 社会的なトレンド(例:SDGs、働き方改革)に合致しているか
- 顧客層の変化に対応した商品・サービスを提供しているか
社会的要因を踏まえることで、「この事業は地域や社会に貢献している」とアピールできます。
🧠 T(Technology)技術的要因
技術的要因は、ITの進化、製造技術の革新、研究開発、特許、技術の陳腐化など、技術面での変化が事業に与える影響です。たとえば、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、業務効率化や新たなサービス展開が可能になります。
補助金申請では、以下のような観点が重要です:
- 新技術の導入によって競争力が高まるか
- 業務の効率化やコスト削減につながるか
- 技術革新により新たな市場を開拓できるか
技術的要因を分析することで、「この事業は将来性がある」と伝えることができます。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
3. PEST分析の進め方:初心者でもできる3ステップ
PEST分析は、複雑そうに見えて実はシンプルなフレームワークです。以下の3ステップで進めることで、補助金申請に必要な「外部環境の理解」をしっかりと整理できます。
📝 ステップ1:情報収集
まずは、政治・経済・社会・技術の4つの視点で、自社の事業に影響を与える外部要因を洗い出します。情報源としては以下のようなものが有効です:
- 政府・自治体の公式サイト(重点施策や補助金情報)
- 業界団体のレポートや統計資料
- ニュース記事や専門誌
- 地域の課題やニーズに関する調査結果
この段階では、できるだけ広く情報を集め、気になるトピックをメモしておきましょう。
🧩 ステップ2:要因の整理と分類
集めた情報を、PESTの4分類に分けて整理します。たとえば:
| 要因 | 内容 | 事業への影響 |
|---|---|---|
| 政治 | 地域活性化を目的とした補助金制度 | 資金調達のチャンスが広がる |
| 経済 | 原材料価格の高騰 | コスト増加への対策が必要 |
| 社会 | 高齢化による介護ニーズの増加 | 新サービスの展開余地あり |
| 技術 | AI活用による業務効率化 | 生産性向上と差別化が可能 |
このように、事業にとってプラスかマイナスかを整理することで、補助金申請書に説得力を持たせることができます。
🎯 ステップ3:事業計画への反映
最後に、PEST分析で得られた知見を事業計画書に反映させます。具体的には:
- 外部環境の変化に対応した事業であることを明記
- 社会的・政策的な意義を強調
- 技術革新や市場ニーズに基づく将来性を示す
これにより、審査員に「この事業は今やるべき価値がある」と納得してもらいやすくなります。

補助金向け事業計画書作成に伴うご注意
マーケティング手法などを始めて活用する際、初心者の方はよく下記のような流れを考えます。例えば・・・
・日本は高齢化が進んでいる
↓
・高齢者向け商品の需要が高まる
↓
・【結論】その為、高齢者向け新サービスの開発・提供に取組めば良い
日本全国の消費者に向けてすでに自社商品の流通網などを確保している大手企業の場合、日本全体について分析をすることは成功への第一歩です。
しかし、例えば個人事業主として自社店舗から半径2KM以内の客をターゲットとしているような小規模事業者の場合は、日本全体の需要分析ではなく、地元地域の人に向けた手書きのアンケート用紙などによる調査を行ったほうが、実際に自身が向き合うターゲットはどのような状況にあり、どのようなニーズがあるのかが正確にわかります。つまり最初の分析手法を用い、日本全体を分析したような手法を自社に適用した場合、誤った分析結果をもたらす可能性が高いです。
(例:自社店舗周辺は、他の地域と異なり、まだ高齢化が進んでいない可能性もある)
そのため、マーケティング分析を行う際は、自社に合う手法を選ぶことがとても重要です。
4. PEST分析を活用した補助金申請のサンプル事例
ここでは、PEST分析の活用方法を具体的にイメージしていただくためために架空の設定で2つの事例をご紹介致します。どちらも、外部環境の変化を的確に捉え、事業の必要性と社会的意義を明確に示したことで採択につながったという設定です。
🏥 事例①:地方の介護事業者による訪問看護サービスの拡充
背景と課題
地方都市で介護事業を営むA社は、高齢化の進行に伴い、訪問看護のニーズが急増していることを実感していました。しかし、設備投資や人材確保には多額の資金が必要であり、事業拡大には補助金の活用が不可欠でした。
PEST分析の活用
- 政治(P):地域包括ケア推進の国策に合致
- 経済(E):医療費抑制のため在宅医療が注目されている
- 社会(S):高齢者人口の増加と在宅志向の高まり
- 技術(T):遠隔診療や電子カルテの導入による効率化
結果
PEST分析をもとに事業計画書を作成し、「地域医療の充実」「高齢者のQOL向上」「医療費削減への貢献」といった社会的意義を強調。
🧪 事例②:製造業によるAI活用型検査システムの導入
背景と課題
B社は部品製造を行う中小企業で、品質検査に多くの人手と時間を要していました。AIを活用した自動検査システムの導入により、生産性向上と人手不足の解消を目指していました。
PEST分析の活用
- 政治(P):中小企業のDX推進を支援する補助金制度あり
- 経済(E):人件費の高騰と生産効率の向上ニーズ
- 社会(S):若手技術者の確保が困難な状況
- 技術(T):AI・画像認識技術の進化と実用化
結果
PEST分析を通じて、技術革新による競争力強化と社会的課題への対応を明確に提示。
5. PEST分析を補助金申請書に落とし込む書き方のコツ
PEST分析で得られた外部環境の情報は、単なる背景説明ではなく、「この事業がなぜ今必要なのか」を論理的に示す材料になります。以下のポイントを押さえて、説得力のある申請書を作成しましょう。
✍️ コツ①:冒頭で「社会的背景」を簡潔に示す
申請書の冒頭では、事業の背景としてPESTの要素を簡潔にまとめます。たとえば:
「近年、地域の高齢化が進み、在宅医療のニーズが高まっています(社会的要因)。また、国の地域包括ケア推進政策により、訪問看護体制の整備が求められています(政治的要因)。」
このように、社会的・政策的な背景を明示することで、事業の必要性が伝わりやすくなります。
📌 コツ②:事業の目的と外部環境のつながりを明確にする
PEST分析で得た要因が、事業の目的や内容とどう関係しているかを具体的に記述します。たとえば:
「本事業では、AIを活用した自動検査システムを導入することで、生産性向上と人手不足の解消を図ります。これは、技術革新(技術的要因)と人件費高騰(経済的要因)への対応策として位置づけられます。」
このように、外部環境と事業内容の接点を示すことで、計画の妥当性が高まります。
📈 コツ③:将来性や波及効果をPEST視点で展開する
補助金申請では、事業の「将来性」や「地域・社会への波及効果」も重要な評価ポイントです。PESTの視点を活用して、以下のように展開しましょう:
- 政治:国の施策と連動した事業展開が可能
- 経済:地域経済の活性化や雇用創出につながる
- 社会:地域住民の生活の質向上に貢献
- 技術:新技術の普及促進や業界全体の底上げ
これらを文章に盛り込むことで、「この事業は補助金を使う価値がある」と審査員に納得してもらいやすくなります。
6. PEST分析とSWOT分析の組み合わせ方
PEST分析は「外部環境」に焦点を当てるのに対し、SWOT分析は「内部環境(Strength=強み、Weakness=弱み)」と「外部環境(Opportunity=機会、Threat=脅威)」を統合的に整理するフレームワークです。両者を組み合わせることで、補助金申請における説得力が格段に高まります。
🔄 ステップ①:PEST分析で外部環境を整理
前章までで行ったように、政治・経済・社会・技術の4要素から、事業に影響を与える外部要因を洗い出します。
🧭 ステップ②:SWOT分析で内部環境と照合
PESTで得た外部要因を、SWOTの「機会(O)」と「脅威(T)」に分類し、自社の「強み(S)」と「弱み(W)」と照らし合わせます。
たとえば、以下のようなマトリクスが作成できます:
| 分析軸 | 内容 |
|---|---|
| 強み(S) | 地域密着型のサービス展開、経験豊富なスタッフ |
| 弱み(W) | IT活用が遅れている、設備が老朽化している |
| 機会(O) | 高齢化による介護ニーズの増加、補助金制度の拡充 |
| 脅威(T) | 競合の増加、人材確保の困難さ |
このように整理することで、「自社の強みを活かして機会を捉える」「弱みを補助金で補う」といった戦略が明確になります。
🧠 ステップ③:クロス分析で戦略を導く
SWOTの4要素を掛け合わせて、具体的な戦略を導きます。補助金申請書には、以下のような形で記述できます:
「本事業では、地域密着型の強み(S)を活かし、高齢化による介護ニーズの増加(O)に対応します。また、IT活用の遅れ(W)を補うため、補助金を活用して遠隔診療システムを導入し、競合との差別化(T)を図ります。」
このように、PESTとSWOTを組み合わせることで、事業の必要性・実現可能性・将来性を一貫して説明できるようになります。
7. 審査員の視点から考えるアピールポイントの整理
補助金の審査員は、限られた時間で多くの申請書を読みます。そのため、以下のような視点で「読みやすく、納得しやすい」構成を意識することが重要です。
🎯 ポイント①:「社会的意義」と「政策との整合性」
審査員は、「この事業が社会にとって必要か」「国や自治体の施策と合っているか」を重視します。PEST分析で得た政治・社会的要因を活用し、以下のように記述しましょう:
「本事業は、国が推進する地域包括ケアの方針に沿っており、高齢者の在宅医療ニーズに応えるものです。」
このように、政策との整合性を明示することで、事業の公共性が伝わります。
📊 ポイント②:「課題の明確化」と「解決策の妥当性」
事業が解決しようとしている課題が明確であり、その解決策が現実的かどうかも重要です。SWOT分析で整理した「弱み」や「脅威」に対して、補助金を活用してどう対応するかを示しましょう:
「人材不足という課題に対し、AIを活用した自動化を進めることで、業務効率を高め、持続可能な体制を構築します。」
課題と解決策が論理的につながっていることが、審査員の納得につながります。
📈 ポイント③:「成果の見える化」と「波及効果」
補助金は「投資」です。審査員は、その投資がどのような成果を生むかを知りたいと考えています。以下のような視点で成果を具体的に示しましょう:
- 数値目標(例:売上○%増、利用者数○人増)
- 地域への波及効果(例:雇用創出、他事業者への技術展開)
- 持続可能性(例:補助金終了後も継続可能な収益モデル)
「本事業により、年間100件の訪問看護を新規に提供できる見込みであり、地域の医療体制強化に貢献します。」
このように、成果が具体的であればあるほど、審査員の評価は高まります。
8. PEST分析を活用した補助金申請書のテンプレート例
PEST分析を活用した申請書は、論理的で説得力があり、審査員に「この事業は今、社会に必要だ」と感じてもらえる構成が重要です。以下は、補助金申請書の基本構成と、それぞれのパートにPESTの要素をどう盛り込むかのテンプレート例です。
🧩 ① 事業の背景と目的
本事業は、〇〇地域における高齢化の進行(社会的要因)と、国の地域包括ケア推進政策(政治的要因)を背景に、在宅医療体制の強化を目的としています。
ここでは、PESTの「S」と「P」を活用して、社会的意義と政策との整合性を示します。
💡 ② 現状の課題と事業の必要性
現在、訪問看護の需要が高まる一方で、看護師不足や業務負担の増加(経済的・社会的要因)が課題となっています。これに対し、ICTを活用した業務効率化(技術的要因)により、持続可能なサービス提供体制を構築する必要があります。
ここでは、「E」「S」「T」の要素を組み合わせて、課題と解決策の妥当性を説明します。
🚀 ③ 事業の内容と実施方法
本事業では、遠隔診療システムの導入、訪問看護スタッフの育成、地域医療機関との連携強化を図ります。これにより、地域住民の健康維持と医療費の抑制(政治的・経済的要因)に貢献します。
事業内容と外部環境のつながりを明示することで、計画の具体性と社会的効果を強調します。
📈 ④ 期待される成果と波及効果
本事業により、年間〇〇件の訪問看護サービス提供が可能となり、地域医療体制の充実と雇用創出(社会的・経済的要因)が期待されます。また、ICT技術の活用により、他事業者への展開も視野に入れています(技術的要因)。
成果を具体的な数値や波及効果で示すことで、補助金の「投資価値」を明確にします。
9. 申請書作成時にありがちな失敗例とその回避策
補助金申請書は、事業の魅力を伝えるプレゼン資料のようなものです。以下のような失敗を避けることで、採択率を高めることができます。
❌ 失敗①:抽象的な表現ばかりで具体性がない
例:「地域に貢献する事業です」「業務効率化を図ります」
これでは、何をどう貢献するのか、どのように効率化するのかが伝わりません。
✅ 回避策:数値や事例を交えて具体的に記述
「年間100件の訪問看護を新規提供し、地域の医療アクセスを20%改善します」
❌ 失敗②:PEST分析を活かしきれていない
例:外部環境の記述が単なる情報の羅列になっている
PEST分析は、事業との関連性を示してこそ意味があります。
✅ 回避策:外部要因と事業内容の接点を明確にする
「高齢化(社会的要因)に対応するため、訪問看護体制を強化する事業を展開します」
❌ 失敗③:審査員の視点を意識していない
例:自社の都合ばかりを強調し、社会的意義が薄い
補助金は「公的資金」であるため、社会への貢献が重視されます。
✅ 回避策:政策との整合性や地域への波及効果を明示
「本事業は、国の地域包括ケア政策に沿っており、地域医療体制の強化と雇用創出に貢献します」
❌ 失敗④:文章が長すぎて読みづらい
例:1文が100文字以上、段落がなく詰まっている
審査員は多くの申請書を読むため、読みやすさも評価に影響します。
✅ 回避策:1文は60文字程度、段落や箇条書きを活用
「本事業の目的は以下の通りです:
① 地域医療体制の強化
② ICT導入による業務効率化
③ 雇用創出による地域活性化」
10. PEST分析を活用した補助金申請書のチェックリスト ✅
以下のチェックリストを使って、申請書の内容を最終確認しましょう。各項目に「はい」と答えられれば、説得力のある申請書が完成しているはずです。
| チェック項目 | 内容 | チェック |
|---|---|---|
| 社会的背景の明示 | PESTの「政治・社会」要因を使って、事業の背景が説明されているか | ☐ |
| 課題の具体性 | 現状の課題が数値や事例を交えて具体的に記述されているか | ☐ |
| 外部環境との接点 | PEST分析の要因と事業内容が論理的につながっているか | ☐ |
| 成果の見える化 | 事業の成果が数値や波及効果で明確に示されているか | ☐ |
| 政策との整合性 | 国や自治体の施策と事業が一致していることが示されているか | ☐ |
| 読みやすさ | 文章が簡潔で、段落や箇条書きが適切に使われているか | ☐ |
| SWOTとの連携 | 自社の強み・弱みとPESTの機会・脅威が整理されているか | ☐ |
| 審査員視点の配慮 | 公的資金の使途として妥当性・公益性が伝わっているか | ☐ |
🎁 まとめ:PEST分析は「説得力の武器」
PEST分析は、単なる環境整理ではなく、「なぜこの事業が今必要なのか」を論理的に伝えるための強力な武器です。補助金申請においては、社会的意義・政策との整合性・将来性を示すことが採択のカギとなります。
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
士業やコンサルとして中小・零細企業の社長様から要望の多い補助金支援業務について学びたい方はこちら。補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
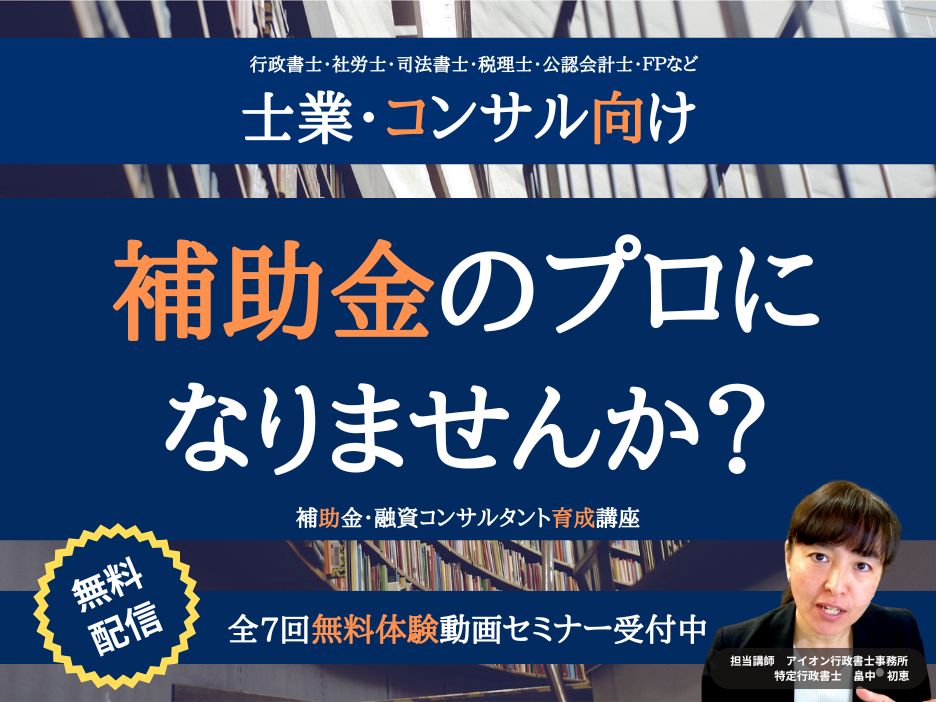
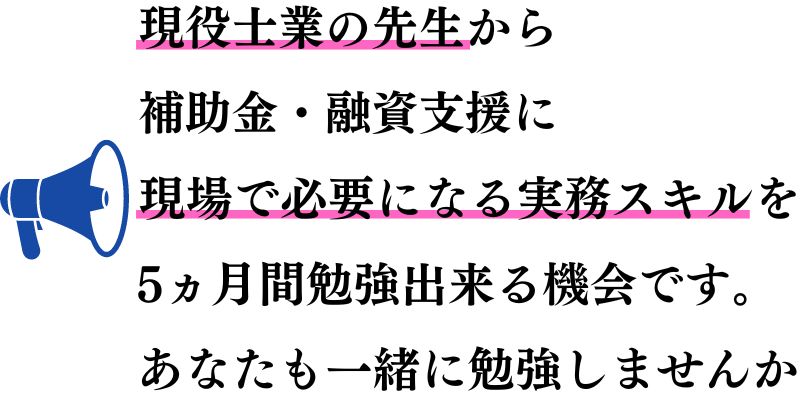

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。