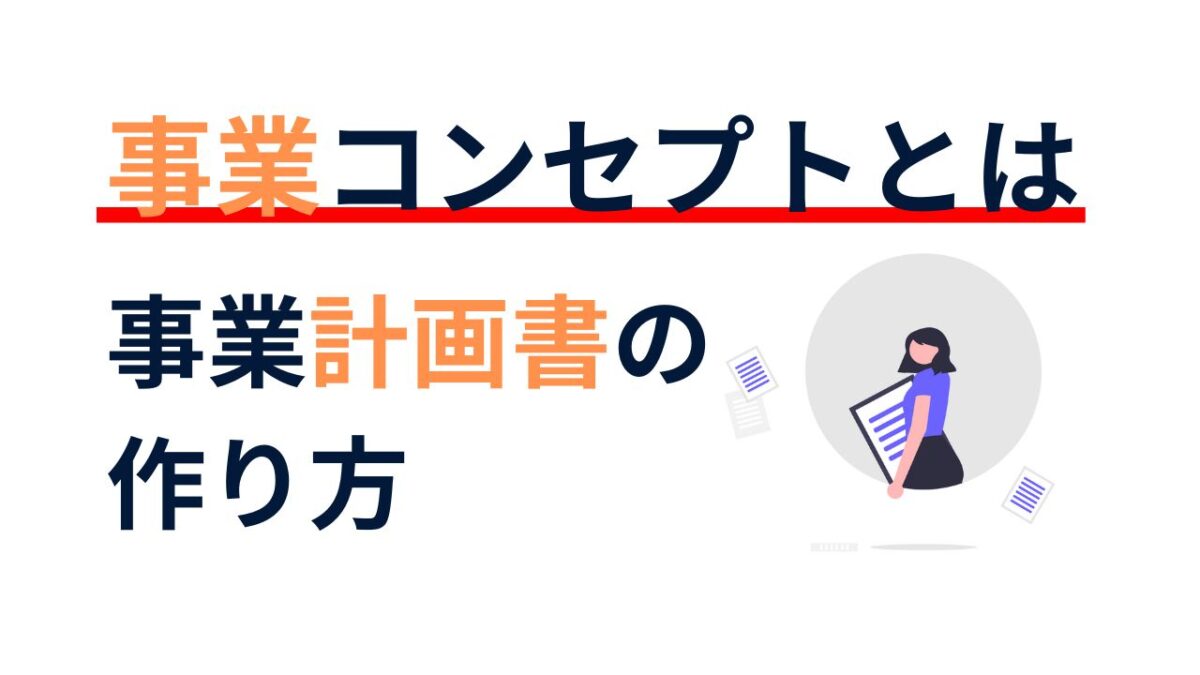この記事は3部構成です
1)事業計画書の作り方|事業コンセプトとは
→ https://hojyokin-hiroba.com/business-concept-guide/
2)事業計画書の作り方|事業計画書のサンプル&雛形解説
→ https://hojyokin-hiroba.com/business-plan-writing-guide/
3)事業計画書の作り方|「ビジョン・目標」の作り方と考え方
→ https://hojyokin-hiroba.com/business-plan-vision-goals/
事業コンセプトとは、単なるアイデアやキャッチコピーではなく、事業の核となる価値と方向性を明確に言語化したものです。顧客視点に立ち、競合や自社の強みを踏まえて構築することで、事業の成功確率が格段に高まります。
1️⃣ コンセプトとは何か?
事業コンセプトとは、事業の核となる考え方であり、方向性や提供価値を明確にするものです。
「コンセプト」という言葉はよく使われますが、実際には曖昧なまま使われていることが多く、キャッチコピーやアイデア、テーマと混同されがちです。ここでは、それぞれの違いを明確にし、コンセプトの本質に迫ります。
| 概念 | 定義・役割 |
|---|---|
| コンセプト | 事業の核となる考え方。方向性や価値を示す。 具体例:ユニクロ「LifeWear」 |
| キャッチコピー | 魅力を端的に伝える広告表現。 具体例:ヒートテック「あったかいは力だ」 |
| アイディア | 着想段階の抽象的な発想。 具体例:「移動中に音楽を聴く」 |
| テーマ | 事業の領域や分野。 具体例:「健康」「教育」 |

コンセプトは、事業の“答え”であり、実行の指針となるものです。
事業計画書などを初めて作成される方は「コンセプト」と「事業計画」をよく混同されますので、次のその違いについて解説致します。
2️⃣ コンセプトと事業計画の違い
コンセプトは目的地、事業計画はその道筋です。
事業計画はコンセプトを実現するための手段であり、コンセプトが不明確なままでは計画が場当たり的になり、事業の失敗リスクが高まります。
| 項目 | 新規事業コンセプト | 事業計画 |
|---|---|---|
| 目的 | 事業の方向性を定義 | コンセプトを実現する具体的な方法を定義 |
| 内容 | 提供価値、顧客像、解決すべき課題など | 市場分析、販売戦略、財務計画など |
| 作成時期 | 事業計画策定前 | コンセプト確定後 |
| 重要性 | 事業の羅針盤 | 実行の地図 |
3️⃣ コンセプト構築の7要素(エッセンス)
事業の独自性を明確にするための7つの視点です。
これらの要素を整理することで、他社と差別化された、魅力的な事業コンセプトが生まれます。
- 背景要素:技術、人材、歴史など事業の強みの源泉
- パーソナリティ:事業を擬人化した性格(優しさ、強さなど)
- シンボル:ロゴやネームなど価値を象徴するもの
- 機能価値:顧客が得る具体的な便益(例:美味しいコーヒー)
- 顧客像:価値観やライフスタイルを重視したターゲット設定
- 情緒価値:体験によって得られる感情(例:映える、自慢したい)
- 関係性:顧客との理想的な関係(仲間、相棒など)
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
4️⃣ 顧客視点で考えるコンセプト|顧客インサイトと3C分析
顧客の“本音”を捉えることで、真に響くコンセプトが生まれます。
🔍顧客インサイトとは?
顧客インサイトとは、顧客自身も気づいていない潜在的な欲求や深層心理を読み解き、商品やサービスの本質的な価値を導き出すための概念です。単なるニーズとは異なり、行動の裏にある“本音”を探ることが目的です。
🔍顧客インサイトとは何か?
顧客インサイトは、アンケートやインタビューでは表面化しない、無意識の欲求や感情を指します。たとえば「この商品を選んだ理由は?」と聞いて「なんとなく」と答える顧客の背後には、「安心感が欲しい」「家族に褒められたい」といった深層心理が隠れていることがあります。
顧客インサイトとニーズの違い
| 項目 | 顧客インサイト | ニーズ |
|---|---|---|
| 意識レベル | 無意識・潜在的 | 顕在的・自覚あり |
| 表出方法 | 行動や感情の裏に隠れている | 質問やアンケートで表現される |
| 価値創造 | 新しい価値や体験を生む | 既存の課題を解決する |
🧠顧客インサイトの重要性
- 競合との差別化:表面的なニーズではなく、深層心理に訴えることで独自性を確立
- マーケティング精度の向上:顧客の本音に基づいた訴求が可能
- 商品・サービスの改善:本当に求められている価値を提供できる
- 顧客満足度の向上:期待を超える体験を設計できる
🔎顧客インサイトの見つけ方
1. 行動観察
顧客の購買行動や使用シーンを観察し、言葉にされない動機を探る。
2. インタビュー
「なぜそう思ったのか」「それはいつからか」など、深掘り質問で本音を引き出す。
3. ソーシャルリスニング
SNSやレビュー、検索ワードから顧客の感情や不満を分析する。
4. 共感マップ・ジャーニーマップ
顧客の「思考・感情・行動」を可視化し、体験全体からインサイトを抽出する。
🧰顧客インサイトの活用ステップ
- データ収集:定性・定量調査で顧客の声を集める
- 仮説構築:行動の背景にある心理を推測
- 検証:インタビューやテストマーケティングで仮説を確認
- 施策設計:商品開発・広告・UXに反映
- 改善と再発見:継続的にインサイトを磨く
✅成功事例の一例
- 動画配信サービス:単なる「暇つぶし」ではなく、「家族と一緒に過ごす安心感」がインサイトだったことで、家族向けプランを開発し利用者数が増加。
顧客インサイトは、事業コンセプトの核を形成する重要な要素です。顧客の“まだ満たされていない欲求”を探り、共感と発見を言語化することで、真に響く価値提供が可能になります。
📊3C分析によるコンセプト設計
3C分析とは、「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から市場環境を分析し、事業の成功要因(KSF)を導き出すためのマーケティングフレームワークです。
🔍3C分析とは?
3C分析は、戦略コンサルタントの大前研一氏が提唱したフレームワークで、事業を取り巻く環境を多角的に把握し、競争優位性を築くための出発点として活用されます。
この分析は、BtoB・BtoC問わず、商品開発、事業戦略、マーケティング施策の立案など、幅広い場面で使われます。
🧩3つのCの分析内容
1. Customer(顧客・市場)
- 市場規模・成長性:どれだけの需要があり、今後伸びる可能性があるか
- 顧客ニーズ・インサイト:顕在・潜在ニーズ、購買動機、ライフスタイル
- 購買行動・属性:誰が、いつ、どこで、どのように買うか
👉 顧客の“困りごと”や“満たされていない欲求”を深掘りすることで、提供すべき価値が見えてきます。
2. Competitor(競合)
- 競合の強み・弱み:技術力、ブランド力、価格、流通網など
- 戦略・ポジショニング:どの顧客層を狙っているか、どんな価値を提供しているか
- 市場シェア・評判:競合の影響力や顧客からの評価
👉 「誰も助けていない領域」を見つけることで、差別化のヒントになります。
3. Company(自社)
- 自社の強み・資源:技術、人材、ブランド、ネットワーク
- 弱み・制約:資金、認知度、組織体制など
- 提供価値・ビジョン:顧客にどんな価値を届けたいか
👉 自社が「手を差し伸べられる領域」を明確にすることで、戦略の軸が定まります。
🧠3C分析の目的と活用法
- KSF(Key Success Factors)=成功要因の発見
- 市場ニーズと自社の強みの接点を見つける
- 競合との差別化ポイントを明確にする
- 事業コンセプトやマーケティング戦略の土台を築く
🛠3C分析の進め方
- 情報収集(市場データ、顧客調査、競合分析)
- 各Cの現状を整理(SWOT分析と併用も有効)
- 接点を見つけてKSFを抽出
- コンセプトや戦略に落とし込む
✅3C分析の注意点
- 主観を排除し、客観的なデータに基づく
- 分析の順番は柔軟に(Customer→Competitor→Companyが基本)
- 定期的に見直し、環境変化に対応する
3C分析は、事業コンセプトを構築するうえで不可欠なフレームワークです。顧客の本音、競合の盲点、自社の強みをつなぎ合わせることで、唯一無二の価値提供が可能になります。
| 要素 | 分析内容 | コンセプトへの接続 |
|---|---|---|
| Customer | ニーズ、ウォンツ、ライフスタイル、購買行動 | ユーザーが困っている |
| Competitor | 競合の強み・弱み、戦略、価格、シェア | 誰も助けていない |
| Company | 自社の強み、技術、ブランド、資源 | 私たちが手を差し伸べることができる |
この3つを接続詞でつなげることで、「私たちが、誰も助けていない困っているユーザーに価値を届ける」というコンセプトストーリーが完成します。
5️⃣ コンセプト作成の手法
体系的に整理することで、ブレないコンセプトが生まれます。
- コンセプトハウス:目的・提供価値・ターゲット・独自性を整理
- 言語化のポイント:簡潔・顧客視点・実現可能性を意識
6️⃣ コンセプトの検証とブラッシュアップ
作って終わりではなく、磨き続けることが重要です。
| 調査方法 | 目的 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| アンケート調査 | 共感度やニーズの数値化 | 多くのデータ収集が可能 | 回答率が低い場合も |
| グループインタビュー | 潜在ニーズの深掘り | 多様な視点が得られる | 時間と費用がかかる |
| データ分析 | 市場・競合・顧客行動の把握 | 客観的な評価が可能 | 解釈が難しい場合もある |
✅まとめ|事業の成功はコンセプトから始まる
明確なコンセプトが、事業の羅針盤となり、成功への道を照らします。
市場調査と顧客理解を重ね、骨太なコンセプトを築くことで、社内の意思統一、顧客との信頼構築、投資家からの評価など、あらゆる面で事業の成功確率が高まります。
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
士業やコンサルとして中小・零細企業の社長様から要望の多い補助金支援業務について学びたい方はこちら。補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
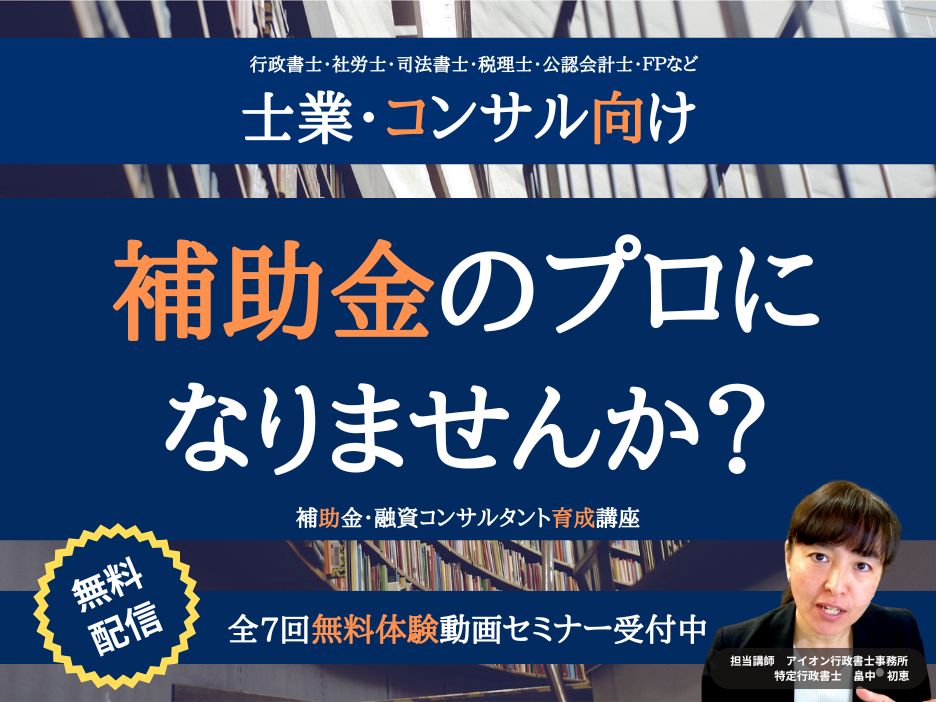
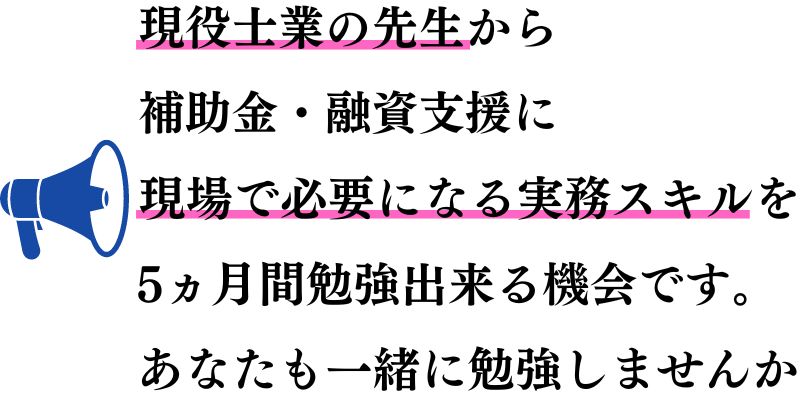

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。