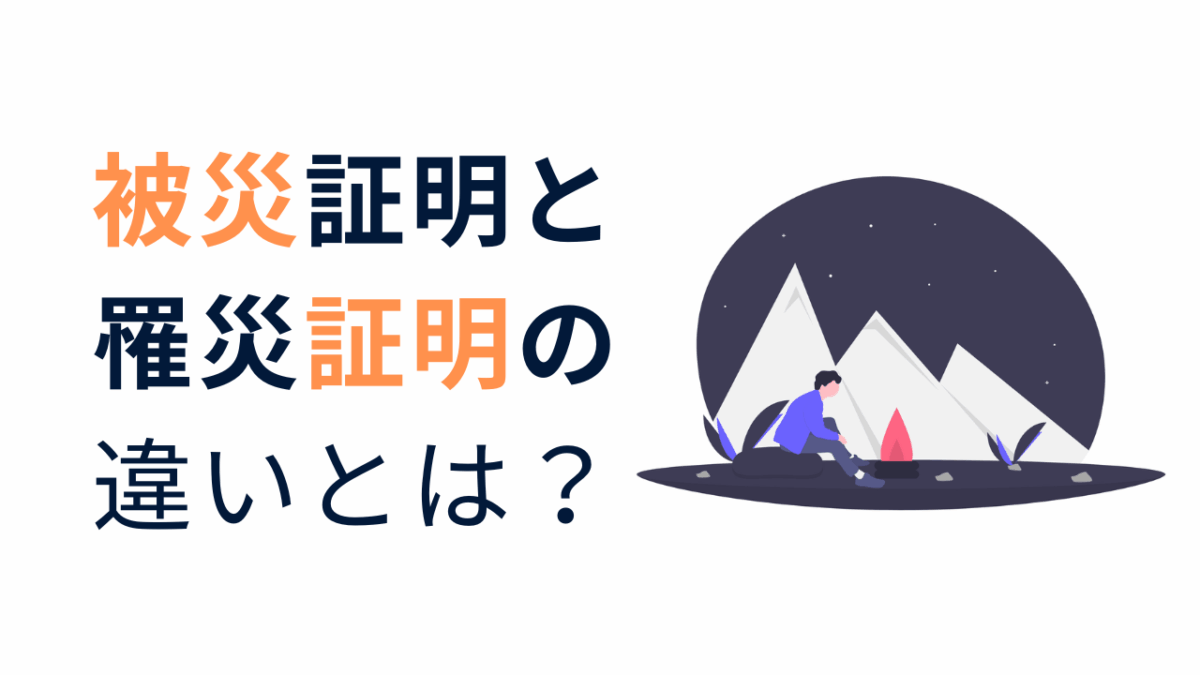本記事では、災害時に行政から支援を受ける際に必要となる「被災証明書」と「罹災証明書」について、違いや取得の際の注意点をわかりやすく解説します。
動画による解説 講師:特定行政書士 畠中 初恵先生
「被災証明書」と「罹災証明書」は別物です
災害に遭った際、行政からの支援を受けるために必要な証明書として「被災証明書」と「罹災証明書」があります。名前が似ているため混同されがちですが、実は用途が異なる別の証明書です。
- 罹災証明書:居住用の家屋が被害を受けたことを証明するもの。住民が住んでいた住宅が対象です。
- 被災証明書:店舗、工場、倉庫、事務所など、居住用以外の資産が被害を受けたことを証明するものです。
更に詳しく解説
罹災証明書と被災証明書は、どちらも災害による被害を証明するための公的書類ですが、対象や目的が異なるため、使い分けが重要です。以下にその違いをわかりやすくまとめます。
🏠 罹災証明書とは
- 対象:居住用の建物(住家)
- 目的:建物の被害の「程度」を証明する
- 発行元:市区町村
- 使用例:
- 被災者生活再建支援金の申請
- 公費による家屋解体
- 税金や公共料金の減免
- 災害援護資金の貸付
- 被害区分:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊など
🏢 被災証明書とは
- 対象:非住家(店舗、事務所、倉庫、門、塀、車両など)や動産
- 目的:災害によって被害を受けた「事実」を証明する
- 発行元:市区町村
- 使用例:
- 火災保険・地震保険の請求
- 被災ローン減免制度の補完的証明
- 自治体による支援制度の申請
- 被害の程度は記載されない:被害の有無のみを証明
✅ 違いのまとめ
| 項目 | 罹災証明書 | 被災証明書 |
|---|---|---|
| 対象 | 居住用建物 | 非住家・動産など |
| 証明内容 | 被害の程度 | 被害の事実 |
| 使用目的 | 支援金・減免・修繕など | 保険請求・補完的証明など |
| 被害区分 | あり(全壊~一部損壊) | なし(被害の有無のみ) |
※上記は概要を分かりやすくまとめたものです、例外もございますので最終的には使用目的の管理責任者(行政等)の担当者にご確認下さい。
どちらも市区町村に申請して取得します。例えば横浜市に住んでいる方は、横浜市役所に申請する必要があります。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
罹災証明書は復旧や補助金申請に必須
罹災証明書は、住宅の復旧や公費による解体、補助金申請などに必要不可欠です。
特に、石川県などでは「公費解体制度」があり、住めなくなった家屋を国や自治体の費用で取り壊す支援が行われています。その申請には罹災証明書が必要です。
また、罹災証明書には被害の程度に応じて「半壊」「全壊」などの区分があり、補助金の額にも影響します。申請時には正確な被害状況の把握と証明が重要です。
災害直後にまずやるべきこと:写真を撮る
災害に遭った直後は混乱しがちですが、支援を受けるためには「証拠となる写真の撮影」が非常に重要です。
石川県の公式サイトでも「住まいが被害を受けた時にまずやること」として写真撮影が推奨されています。
撮影のポイント
- 外観を四方向から撮影:建物全体がわかるように、遠くから引いた写真を撮る。
- 周囲の位置関係がわかるように:電柱の住所表示、交差点名など、場所を特定できる情報も一緒に写す。
- 表札が残っていれば必ず撮影。
- 室内も全方向から撮影:被害箇所だけでなく、部屋全体を四隅から撮る。
- 天井・床も撮影:部屋の広さや構造がわかるように、上下の面も記録。
- 動画も有効:写真に加えて動画でぐるっと撮影しておくと、見落としを補えます。
スマートフォンがあれば、避難先でも撮影が可能です。証明書の申請に必要な資料となるので、必ず記録しておきましょう。
まとめ:証明書の違いと備えの大切さ
災害時に必要な証明書は2種類あります。
- 罹災証明書:住宅用
- 被災証明書:住宅以外の資産用
どちらも行政支援を受けるために重要で、申請には写真や動画などの記録が必要です。
災害直後は気持ちが落ち着かないかもしれませんが、復旧や再建のために、ぜひこの知識を覚えておいてください。
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
士業やコンサルとして中小・零細企業の社長様から要望の多い補助金支援業務について学びたい方はこちら。補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
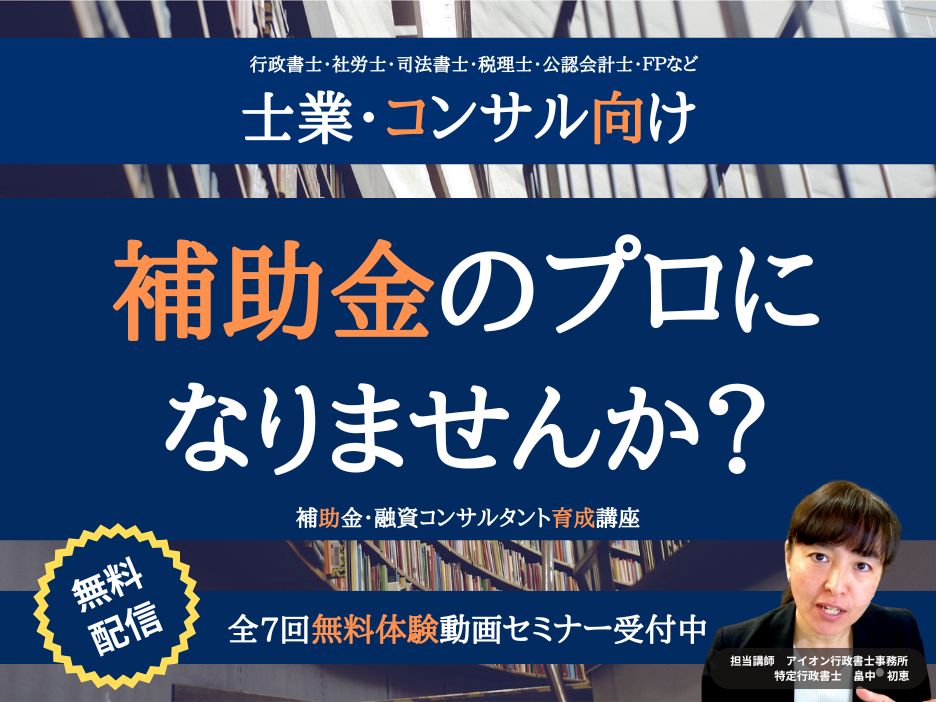
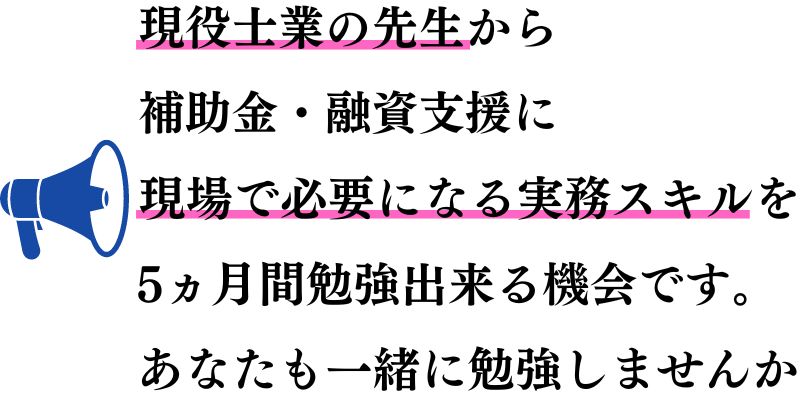

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。