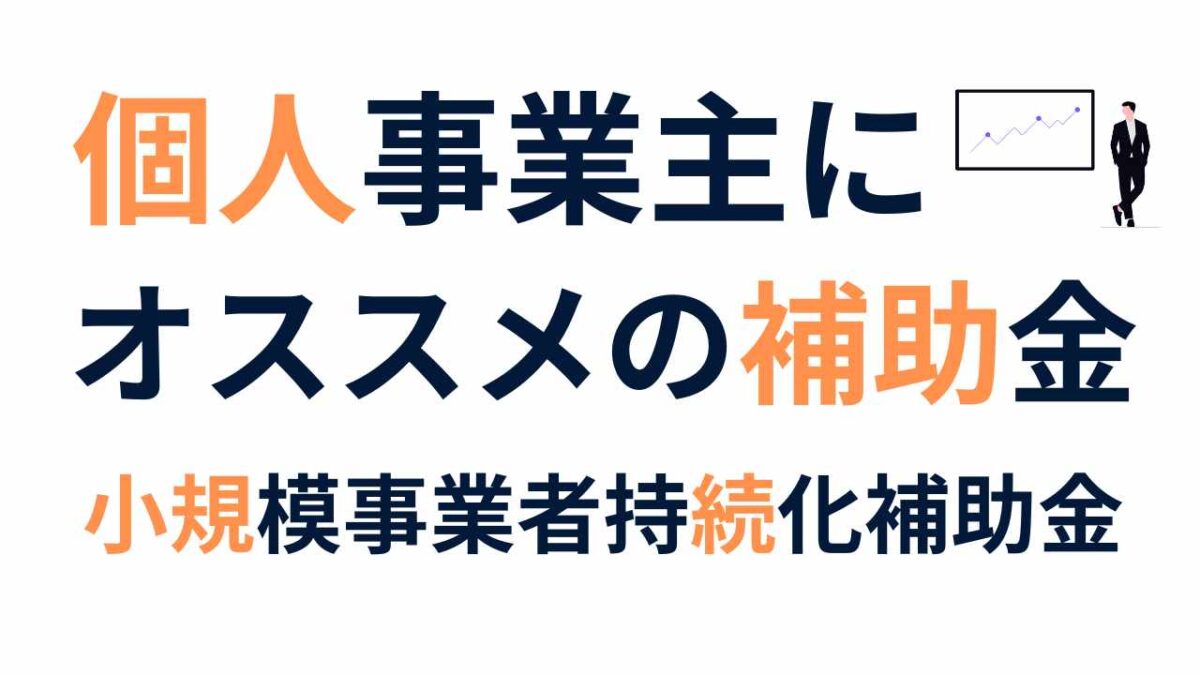小規模事業者持続化補助金は個人事業主や零細企業向きに補助金です
小規模事業者持続化補助金は、経済産業省が中小企業庁を通じて実施している補助金制度で、個人事業主やフリーランスといった小規模な事業者も対象となる点が大きな特徴です。本記事では、補助金の概要から対象者、申請の流れ、申請時の注意点までを、補助金申請が初めての方にもわかりやすく解説します。また、この小規模事業者持続化補助金を活用してビジネスを「儲かる体質」へと成長させるためのヒントや、専門家のサポートを受ける重要性についても触れています。さらに、記事の最後では、無料で学べる「小規模事業者持続化補助金の教科書」へのご案内もありますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 小規模事業者持続化補助金とは?
🧾 小規模事業者向けの支援制度とは
小規模事業者持続化補助金とは、販路開拓や業務効率化など、事業の持続的な発展を目的とした取り組みに対して、経費の一部を補助する制度です。経済産業省の予算に基づき、中小企業庁が所管し、全国の商工会・商工会議所が窓口となって運営されています。
👥 対象となる事業者の定義

この補助金の最大の特徴は、個人事業主や従業員数が少ない零細企業など、いわゆる「小規模事業者」を主な対象としている点です。たとえば、製造業や建設業であれば常時使用する従業員が20人以下、卸売業やサービス業であれば5人以下であることが条件となります。つまり、法人格の有無に関係なく、個人で事業を営んでいる方も対象となるのです。
🔄 他の補助金制度との違い
同じ経済産業省の補助金である「ものづくり補助金」や「新事業進出補助金」は、主に中小企業を支援する制度ですが、小規模事業者持続化補助金は、より小規模な事業者に焦点を当てている点で異なります。この補助金の申請手続きを実施することにより、日々の業務に追われがちな個人事業主でも、自社の事業計画の策定や財務状況の分析を通して事業の見直しや成長戦略の構築に取り組むきっかけを得ることができます。

当社からのアドバイス:
小規模事業者持続化補助金は全国の商工会・商工会議所が本申請の前に、一度申請内容を事前チェックするという、他の補助金とは異なる手続きが必要な補助金です。稀に、本申請の期限に間に合うように申請書は作成できたにも関わらず、商工会・商工会議所の事前チェック最終日に間に合わず申請が出来なかったという話を聞きます。
必要な手続きの申請スケジュールは事前によく確認しましょう。
2. 小規模事業者持続化補助金の対象経費と補助額の仕組み
💰 補助対象となる主な経費
小規模事業者持続化補助金では、事業の持続的な発展を目的とした取り組みにかかる経費の一部が補助されます。具体的には、販路開拓や業務効率化に関連する経費が対象となり、たとえば以下のような費用が該当します。
📢 広告宣伝費の活用例
まず、広告宣伝費が代表的な対象経費です。チラシの作成や配布、新聞・雑誌・インターネット広告の掲載費用などが含まれます。また、ウェブサイトの制作やリニューアル費用も対象となるため、オンラインでの集客を強化したい事業者にとっては非常に有効です。

🛠 業務効率化に向けた設備投資
次に、展示会への出展費用や、業務効率化のための設備導入費も補助対象です。たとえば、POSレジの導入や業務管理ソフトの購入など、業務の生産性を高めるための投資が認められています。
🏠 内装工事も対象になるケース
また、あるレストランが付加価値UPを目指し、それまで提供していたメニューをリニューアルし、高額メニューを導入する事業計画を立てた際に、メニューの高級化に合わせて店内リニューアルを計画。それまで和式だった店内トイレを洋式にする内装工事の計画を立て補助金を申請し、実際に採択されたという事例もあります。
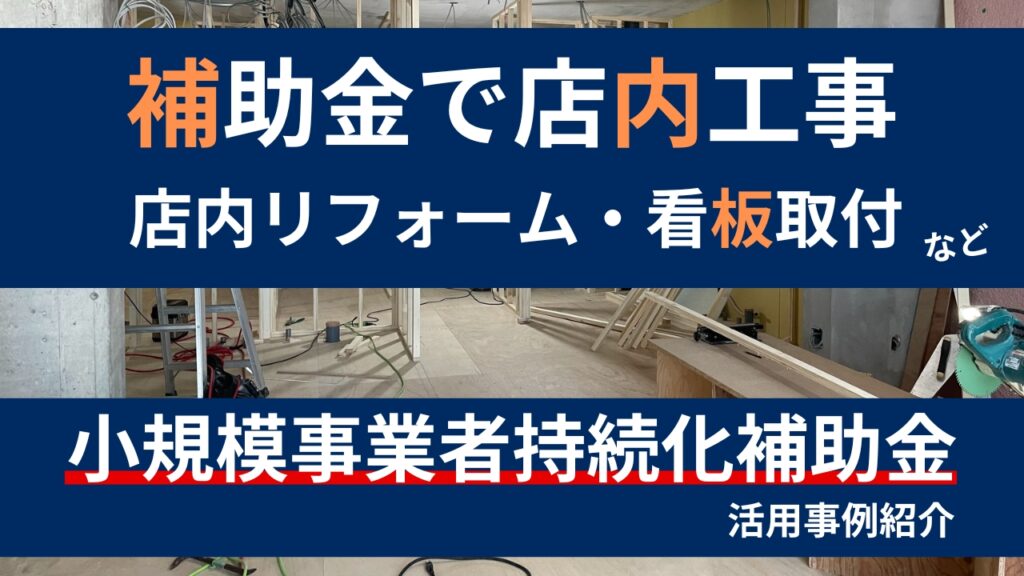
※内装工事に小規模事業者持続化補助金を活用する方法を解説しているページはこちら
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/small-business-interior-work-subsidy
📊 補助額と補助率の基本ルール
補助額については、通常枠では最大50万円(補助率は2/3)までが支給されます。つまり、75万円の経費をかけた場合、そのうち50万円が補助されるという仕組みです。また、特別枠やインボイス枠など、条件に応じて補助上限が200万円に引き上げられるケースもあります。
このような、小規模事業者持続化補助金の対象経費を理解し、自社の取り組みに合った経費を計画的に申請することで、事業の成長を加速させることが可能になります。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
3. 申請の流れと必要書類
📅 申請前に商工会・商工会議所へ相談
小規模事業者持続化補助金の申請は、他の補助金制度と比べて比較的シンプルですが、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。まず最初に行うべきは、事業所が所在する地域の商工会または商工会議所への相談予約です。補助金の申請には、これらの団体からの「事業支援計画書」の発行が必要となるため、早めに連絡を取り、補助金事務局へ提出予定の補助事業計画書等の書類が完成した際には、スムーズに商工会の審査が受けられるように事前に話を通しておくことをオススメします。
📂 必要書類の一覧と作成ポイント

次に、申請に必要な書類を準備します。主な書類としては、「経営計画書」と「補助事業計画書」があります。経営計画書では、現在の事業の状況や課題、今後の展望などを記載し、補助事業計画書では、補助金を活用してどのような取り組みを行うのか、その具体的な内容やスケジュール、期待される効果などを記述します。これらの書類は、単なる形式的なものではなく、審査の際に非常に重視されるため、丁寧かつ論理的に作成する必要があります。
📉 財務書類の整備とその意義
また、事業の財務状況を示す書類として、直近の損益計算書や貸借対照表、資金繰り表なども求められる場合があります。株式会社など法人と異なり個人事業主の方の中には、日々の業務に追われ、こうした財務書類を整備する時間がなかなか取れないという方も多いかもしれません。しかし、この補助金の申請を機に、自身のビジネスの財務状況を見直し、必要に応じて税理士などの専門家の意見を取り入れることで、より健全で持続可能な経営体制を築くことができます。尚、実際に個人事業主が提出する書類には、直近の確定申告書の写しがあります。第一表及び第二表及び収支内訳書1・2面、または所得税青色申告決算書1~4面(税務署受付印のあるもの)、または開業届(税務署受付印のあるもの)を提出することとなります。
💻 電子申請「jGrants」の利用方法
申請は、原則として「jGrants(ジェイグランツ)」という電子申請システムを通じて行います。jGrantsを利用するには、事前に「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。アカウントの取得には数日かかる場合があるため、申請を検討している段階で早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。なお、商工会地区に所在する事業者については、紙での申請も可能な場合がありますので、詳細は地域の商工会に確認してください。
4. 個人事業主が補助金を活用するメリットと注意点
🚀 補助金活用による事業の可能性拡大
小規模事業者持続化補助金は、個人事業主にとって非常に有益な制度です。最大のメリットは、自己資金だけでは実現が難しい販路開拓や業務改善の取り組みを、国の支援を受けながら実行できる点にあります。たとえば、これまで費用面で躊躇していたホームページのリニューアルや、SNS広告の出稿、業務効率化のためのシステム導入なども、補助金を活用することで実現可能になります。
🧭 経営計画の見直しと成長戦略の構築
また、この補助金の申請プロセス自体が、事業の現状を見直し、将来の方向性を明確にする良い機会となります。普段は目の前の業務に追われ、じっくりと経営計画を立てる時間が取れないという個人事業主の方も多いでしょう。しかし、補助金の申請にあたっては、事業の強みや弱み、外部環境の変化、今後の成長戦略などを整理し、文章としてまとめる必要があります。このプロセスを通じて、自分のビジネスを客観的に見つめ直すことができ、結果として「儲かる体質」への転換につながる可能性が高まります。
💸 補助金の「後払い」方式に注意
ただし、補助金にはいくつかの注意点もあります。まず、補助金はあくまで「後払い」であるため、事業者自身が一度全額を立て替える必要があります。資金繰りに不安がある場合は、事前に金融機関と相談しておくと安心です。また、補助対象となる経費には細かなルールがあり、対象外の支出については補助が受けられません。たとえば、既存の設備の修理費や、日常的な運転資金などは対象外となるため、事前に公募要領をよく読み、対象経費を正確に把握しておくことが重要です。
📑 実績報告書の提出と証拠書類の準備
さらに、補助事業の実施後には、実績報告書の提出が求められます。報告書には、実施内容や支出の詳細、成果などを記載し、領収書や請求書などの証拠書類を添付する必要があります。これらの手続きが煩雑に感じられる場合は、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。補助金の申請支援を行っている中小企業診断士や行政書士などに相談することで、申請の精度が高まり、採択率の向上にもつながります。
5. 補助金申請でよくある失敗とその対策
⚠️ 書類不備・記載漏れによる不採択
小規模事業者持続化補助金は、比較的申請しやすい制度とはいえ、申請者の中には不採択となってしまうケースも少なくありません。よくある失敗の一つが、提出書類の不備や記載漏れです。特に、事業計画書の内容が曖昧であったり、補助対象経費の使途が不明確であったりすると、審査の段階でマイナス評価となる可能性があります。補助金は限られた予算の中で配分されるため、審査員に「この事業は本当に効果がある」と納得してもらえるような説得力のある計画書が求められます。
⏰ スケジュール管理の甘さが招くリスク
また、スケジュール管理の甘さも失敗の原因となります。補助金の公募期間は限られており、締切直前に慌てて書類を作成すると、内容が不十分になったり、必要な添付書類を忘れたりするリスクが高まります。特に、商工会・商工会議所の確認や、GビズIDの取得には時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。
❌ 対象外経費の申請ミス
さらに、補助対象外の経費を含めてしまうケースも見受けられます。たとえば、補助金の対象となるのはあくまで「今後の事業発展に資する取り組み」であり、日常的な経費や既存設備の修繕費などは対象外です。公募要領をしっかりと読み込み、対象経費の範囲を正確に理解することが、失敗を防ぐ第一歩となります。
🧑⚖️ 専門家に相談するタイミングと効果
こうした失敗を避けるためには、早い段階で専門家に相談することが効果的です。中小企業診断士や行政書士など、補助金申請の支援実績がある専門家にアドバイスを求めることで、書類の完成度を高め、採択の可能性を大きく引き上げることができます。

6. 補助金を活用して“儲かる体質”へ変革するには?
🔍 補助金をきっかけに経営を見直す
小規模事業者持続化補助金は、単なる資金援助にとどまらず、事業者が自らのビジネスを見直し、持続的な成長を実現するための「きっかけ」として活用することができます。特に個人事業主にとっては、日々の業務に追われる中で、経営戦略や財務状況をじっくりと分析する機会は限られています。しかし、この補助金の申請を通じて、事業の強みや課題を明確にし、今後の方向性を再構築することが可能になります。
🌐 新たな販路開拓と売上拡大の可能性
たとえば、補助金を活用して新たな販路を開拓することで、これまでとは異なる顧客層にアプローチできるようになります。オンラインショップの開設やSNS広告の活用など、デジタルマーケティングに投資することで、売上の安定化や拡大が期待できます。また、業務効率化のための設備導入やシステム化によって、人的リソースの最適化やコスト削減にもつながります。
💼 財務体制の見直しと健全化
さらに、補助金の申請にあたっては、損益計算書や貸借対照表、資金繰り表などの財務資料を整備する必要があります。これを機に、財務の健全性を見直し、利益率の改善や資金繰りの安定化を図ることができれば、補助金の効果は一過性のものではなく、長期的な経営改善へとつながります。
重要なのは、補助金を「もらって終わり」にしないことです。補助金を活用して得た成果を次の成長戦略にどうつなげるかを考えることで、事業はより強く、持続可能なものへと進化していきます。
7. 【無料】補助金活用を学べる「小規模事業者持続化補助金の教科書」へご案内

小規模事業者持続化補助金の申請、何から始めればいいか分からない・・そんなあなたに更に詳しく解説した記事ページをご紹介します。
「小規模事業者持続化補助金の教科書」は、補助金申請が初めての方でも安心して取り組めるよう、制度の基礎から採択されるための実践的なノウハウまでを網羅した無料記事です。
補助金申請は、正しい知識と準備があれば決して難しくありません。
まずは「小規模事業者持続化補助金の教科書」で全体像をつかみ、採択への第一歩を踏み出しましょう。
8. まとめ:補助金を味方に、個人事業主の未来を切り拓こう

小規模事業者持続化補助金は、個人事業主やフリーランスといった小規模な事業者にとって、事業の成長を後押しする強力な支援制度です。補助金を活用することで、販路拡大や業務効率化といった取り組みを実現し、経営の安定化と持続的な発展を目指すことができます。
また、申請プロセスを通じて、自身のビジネスを客観的に見直し、財務や戦略の面から「儲かる体質」への転換を図ることも可能です。補助金は単なる資金援助ではなく、経営者としての視野を広げ、次のステージへと進むための貴重なチャンスなのです。
これから補助金の申請を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしながら、早めの準備と計画的な行動を心がけてください。そして、必要に応じて専門家の力を借りながら、補助金を最大限に活用して、あなたのビジネスをさらに飛躍させていきましょう。
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
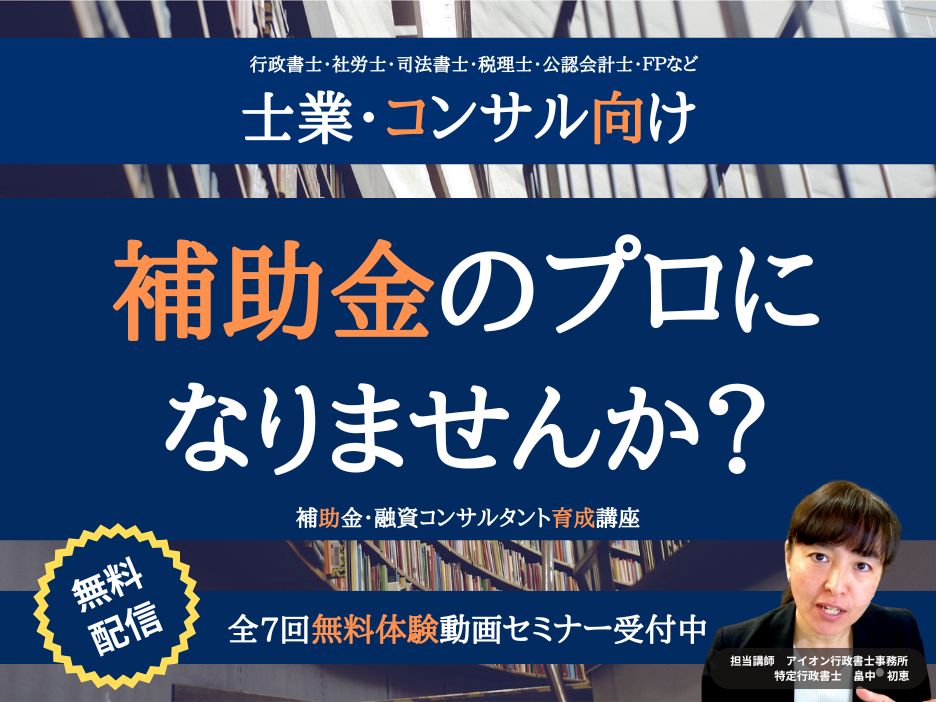
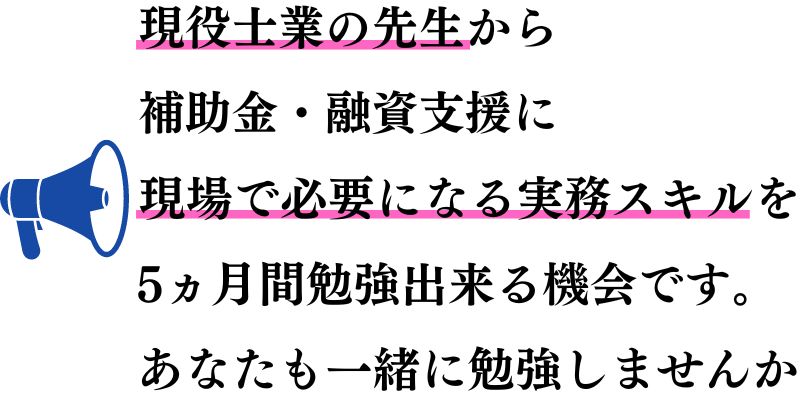

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。