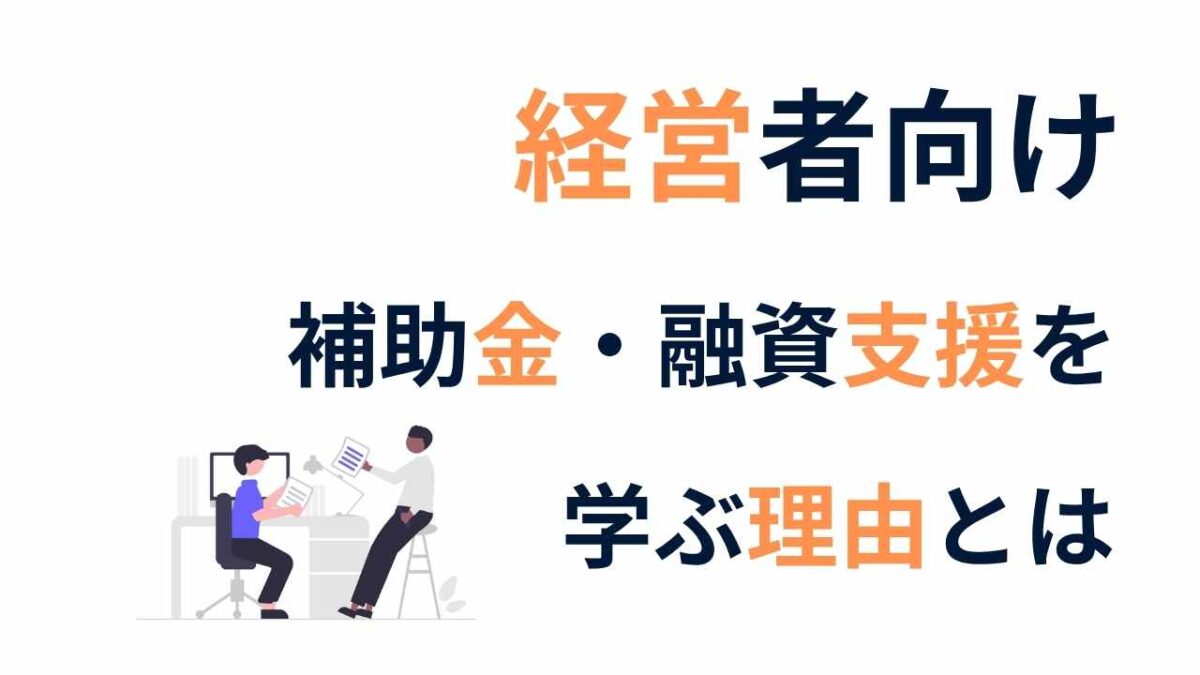この記事を読んでほしい方
- 中小企業・小規模事業者の経営者
- 補助金や融資制度に関心があるが、申請に踏み出せていない方
- 補助金申請を部下や外部に任せきりにしている経営者
- 自社の成長戦略に公的支援を活用したいと考えている方
- 補助金・融資コンサルタントとしてのスキルを経営に活かしたい方
目次

1. 補助金・融資制度の現状と最近の注目ポイント
2024年度の補正予算案では、総額約13.9兆円が閣議決定され、そのうち経済産業省関連の中小企業・小規模事業者向け補助金に約4.4兆円が充てられています(出典:経済産業省 令和5年度補正予算案 概要資料)。これは、過去の補正予算と比較しても非常に大きな規模であり、国が中小企業支援に本腰を入れていることを示しています。
🔍 補助金制度の主な目的
補助金制度は、単なる資金援助ではありません。国や自治体が掲げる政策目標(例:地域経済の活性化、デジタル化の推進、カーボンニュートラルの実現など)を民間企業と連携して実現するための「政策誘導型の投資支援制度」です。
たとえば、以下のような補助金が2025年度も注目されています:
- ものづくり補助金:中小企業の設備投資や新製品開発を支援
- 新事業進出補助金:業態転換や新分野展開を支援
- IT導入補助金:業務効率化やDX推進のためのITツール導入を支援
- 省エネ補助金:エネルギー効率の高い設備導入を支援
これらの制度は、単に「お金がもらえる」ものではなく、経営戦略と密接に関係しています。補助金を活用することで、企業は本来であれば躊躇していた投資を前倒しで実行でき、競争力を高めることが可能になります。

補助金について、どのくらいご存じですか?
たとえば、大型の製造機器を導入する場合には「ものづくり補助金」、ホテルなどの宿泊業で数年ごとに空調機(エアコンなど)を更新する場合には「省エネ補助金」、新たな事業にチャレンジする場合には「新事業進出補助金」など、行政はさまざまな企業支援のための補助金制度を用意しています。
ご自身の会社にぴったり合った補助金制度を見つけ出し、活用することも、経営者として重要な手腕のひとつと言えるのではないでしょうか。
📈 補助金活用の現状
一方で、補助金制度の存在を知っていても「申請が難しそう」「手間がかかる」「専門家に任せればいい」といった理由で、制度を十分に活用できていない企業も少なくありません。実際、補助金の採択率は制度によって異なりますが、書類の完成度や事業計画の説得力が大きく影響します。
このような状況下で、経営者自身が制度の仕組みや申請のポイントを理解しているかどうかが、補助金活用の成否を分ける重要な要素となっているのです。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
2. なぜ今、経営者自身が補助金制度を学ぶべきなのか
補助金申請は、単なる「事務作業」ではありません。むしろ、企業の将来を左右する重要な経営判断の一部です。これまで多くの企業では、補助金申請を総務や経理、あるいは外部の士業やコンサルタントに任せるケースが一般的でした。しかし、近年の補助金制度の複雑化と戦略的性質の高まりにより、「経営者自身が制度を理解し、判断する」ことの重要性が増しています。
✅ 経営者が補助金を学ぶべき理由
① 補助金は「経営戦略」と直結している
補助金の多くは、単なる資金援助ではなく、企業の成長戦略や事業再構築、デジタル化、脱炭素化など、将来の方向性に沿った投資を支援するものです。つまり、補助金の申請には「どのような未来を描くか」という経営者のビジョンが不可欠です。
外部に任せきりにしてしまうと、事業の本質を理解しないまま形式的な申請になり、採択率が下がるリスクもあります。
② 制度の変化に即応し、判断できるのは経営者だけ
補助金制度は毎年のように改正され、要件や対象事業、評価基準が変化します。特に近年は、賃上げ要件やインボイス制度対応、GX(グリーントランスフォーメーション)など、経営全体に関わる要素が盛り込まれる傾向にあります。
こうした変化に柔軟に対応し、戦略的に制度を活用できるのは、企業の全体像を把握している経営者自身です。
③ 社内の補助金リテラシー向上にもつながる
経営者が補助金制度に精通していれば、社内での情報共有や教育もスムーズになります。補助金を単なる「一時的な資金調達手段」ではなく、「経営の武器」として活用する文化を社内に根付かせることができます。

◆補助金制度は利益率100%に近づける魅力的な仕組みです
御社の原価率・利益率はどの程度でしょうか?
多くの事業では、製品やサービスを提供するにあたって必ず一定の原価が発生します。しかし、補助金制度を活用する場合、この点が大きく変わります。
補助金は、申請者自身で手続きを行えば、基本的にその受給額がそのまま利益として手元に残る、非常に魅力的な制度です。仮に御社の売上が1,000万円の場合、通常の事業であれば原価を差し引いた金額が利益となりますが、補助金であれば(人件費を除き)ほぼ全額が純粋な利益になります。
これほど効率よく資金を確保できる仕組みは他に多くはありません。ぜひ積極的にご活用ください。
④ 外注依存のリスクを回避できる
外部の専門家に依頼する場合でも、経営者が制度を理解していれば、適切なパートナー選定や成果物のチェックが可能になります。逆に、知識がないまま丸投げしてしまうと、誤った申請や不正リスク、費用対効果の低下を招く恐れがあります。
3. 経営者が補助金を理解することで得られる5つのメリット
補助金制度を理解し、戦略的に活用できる経営者は、単に資金調達の幅を広げるだけでなく、企業の競争力そのものを高めることができます。ここでは、経営者が補助金制度を学ぶことで得られる具体的な5つのメリットをご紹介します。
① 設備投資や新規事業への挑戦がしやすくなる
補助金は、通常であればリスクが高くて踏み出せないような設備投資や新規事業への挑戦を後押ししてくれます。たとえば、1,000万円の設備投資に対して3分の2の補助が出る場合、実質的な自己負担は約330万円で済みます。これにより、資金繰りの不安を軽減しながら、競争力のある投資判断が可能になります。
② 金融機関との信頼関係が強化される

補助金の採択実績は、企業の信用力を高める材料になります。
補助金を受けるには、事業計画の妥当性や将来性が審査されるため、採択されたという事実自体が「第三者による事業評価」として機能します。
これにより、金融機関からの融資や取引先との信頼関係にも好影響を与えることができます。
③ 経営計画の精度が高まる
補助金申請には、事業の目的、課題、解決策、数値目標などを明確に記載する必要があります。これにより、経営者自身が自社の現状と将来像を客観的に見つめ直す機会となり、経営計画の精度が格段に向上します。補助金申請は、単なる書類作成ではなく「経営の棚卸し」としても非常に有効です。
④ 社内の意識改革につながる
補助金を活用したプロジェクトは、従業員にとっても「会社が本気で変革に取り組んでいる」というメッセージになります。特に、賃上げ要件や生産性向上を伴う補助金では、従業員のモチベーション向上や業務改善への意識改革にもつながります。
⑤ 外部依存からの脱却とコスト削減
補助金申請を外部に依頼する場合、成功報酬型で数十万円〜数百万円の費用が発生することもあります。経営者自身が制度を理解し、社内で対応できる体制を整えることで、こうしたコストを削減し、より多くの資金を本来の事業投資に充てることが可能になります。
4. 補助金申請を「外注任せ」にするリスクとは?
補助金申請を外部の専門家に依頼することは、時間や手間を省くうえで一定のメリットがあります。しかし、すべてを「丸投げ」してしまうことには、見過ごせないリスクが潜んでいます。ここでは、外注依存によって生じる主なリスクを整理します。
⚠️ リスク①:事業の本質が伝わらない
補助金申請において最も重要なのは、「なぜこの事業を行うのか」「どのような成果が期待できるのか」という事業の本質を、審査員に明確に伝えることです。外部の専門家が申請書を作成する場合、ヒアリングを通じて情報を得ることになりますが、経営者の思いや戦略の細部までは伝わりにくいのが現実です。
その結果、表面的な申請書になってしまい、採択率が下がる可能性があります。
⚠️ リスク②:制度変更への対応が遅れる
補助金制度は頻繁に見直され、要件や評価基準が変化します。外部に依頼している場合、制度変更のたびに情報を待つ立場になり、対応が後手に回ることがあります。経営者自身が制度に精通していれば、変化に即応し、戦略的な判断が可能になります。
⚠️ リスク③:不適切な申請によるトラブル
一部のコンサルタントや代行業者の中には、採択率を上げるために誇張した内容を記載したり、実態と異なる事業計画を提出したりするケースも報告されています。こうした申請が発覚した場合、補助金の返還やペナルティ、最悪の場合は不正受給として法的責任を問われることもあります。
経営者が制度を理解していれば、こうしたリスクを未然に防ぐことができます。
⚠️ リスク④:社内にノウハウが蓄積されない
外部に任せきりにしていると、社内に補助金申請のノウハウが蓄積されません。その結果、次回以降も外注に頼らざるを得ず、コストがかさむだけでなく、社内の成長機会も失われます。経営者が主導して制度を学び、社内に知識を共有することで、持続的な活用体制を築くことができます。

専門家からのアドバイス
補助金申請支援業務に携わる立場として、このようなお話をするのは少し気が引けるのですが、本来、補助金申請は申請者ご自身で行うべき手続きです。
外部の専門家に支援を依頼する場合は、「何を、どこまで依頼するのか」を事前に明確にしておくことをおすすめします。
これにより、不要なトラブルを防ぎ、スムーズに申請を進めることができます。
5. 補助金制度の変化と「経営視点」の必要性
近年の補助金制度は、単なる資金支援から「政策誘導型の経営支援」へと大きく変化しています。特に2024年度以降の補正予算では、DX(デジタルトランスフォーメーション)、GX(グリーントランスフォーメーション)、地域創生、スタートアップ支援など、国の成長戦略と密接に連動した補助金が増加しています。
こうした制度の変化に対応するには、現場任せではなく、経営者自身の視点と判断が不可欠です。
🔄 補助金制度の変化とは?
- コロナ禍初期:資金繰り支援や売上減少への一時的対応が中心
- 現在:中長期的な成長支援(DX・GX・地域活性化・新事業創出など)へシフト
- 今後:補助金は「社会課題の解決」と「企業の持続的成長」の両立を求める方向へ
このように、補助金は「経営の未来をどう描くか」を問う制度へと進化しています。
👓 経営視点が求められる理由
① 投資判断の優先順位を見極める力
補助金があるからといって、すべての投資が正解とは限りません。むしろ、「補助金があるからやる」のではなく、「やるべき投資に補助金を活用する」という視点が重要です。経営者でなければ、こうした判断はできません。
② 補助金を「目的化」しないために
補助金の採択をゴールにしてしまうと、本来の経営戦略が歪むリスクがあります。補助金はあくまで「手段」であり、「補助金を活かして何を実現するか」が問われます。経営者が主導することで、制度の本質を見失わずに済みます。
③ 社会的要請への対応力
近年の補助金は、賃上げ、環境対応、地域貢献、女性活躍など、社会的要請を反映した要件が増えています。これらは単なる条件ではなく、企業の社会的責任(CSR)やESG経営にも直結するテーマです。経営者の視点で全体最適を図る必要があります。
6. 補助金と賃上げ要件:経営戦略との連動がカギ
近年の補助金制度では、「賃上げ要件」が採択や交付の条件として組み込まれるケースが急増しています。これは単なる形式的な条件ではなく、企業の経営戦略と密接に関係する重要な要素です。
💡 賃上げ要件とは?
たとえば「新事業進出補助金」では、以下のいずれかの要件を満たす必要があります:
- 一人当たり給与支給総額の年平均成長率が、都道府県別の最低賃金年平均成長率以上であること
- 給与支給総額の年平均成長率が2.5%以上であること
これらの要件は、補助事業終了後3〜5年の事業計画期間にわたって達成する必要があり、未達成の場合は補助金の一部または全額返還が求められることもあります。
📊 なぜ賃上げが求められるのか?
政府は「成長と分配の好循環」を掲げ、企業の成長によって得られた利益を従業員に還元することを強く促しています。補助金はその実現を後押しする政策ツールであり、企業に対して「生産性向上」と「賃上げ」の両立を求めているのです。
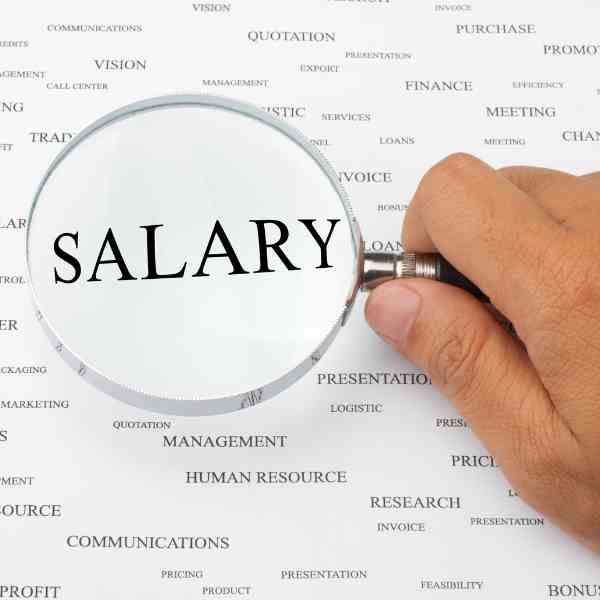
🧭 経営戦略と賃上げ要件の連動が不可欠
補助金を活用するには、単に「賃金を上げる」といった表面的な対応では不十分です。以下のような戦略的視点が求められます:
- 設備投資やDXによる生産性向上 → 賃上げ原資の確保
- 新規事業による収益拡大 → 従業員への利益還元
- 人材定着・採用力強化 → 賃上げによる職場環境改善
つまり、補助金を活用することで「稼ぐ力」を高め、その成果を「人材への投資」として還元するという循環を描くことが、経営者に求められるのです。
⚠️ 賃上げ要件を軽視するとどうなるか?
- 要件未達成による補助金返還リスク
- 採択審査での減点や不採択
- 社内外からの信頼低下
このようなリスクを回避するためにも、経営者自身が制度の趣旨と要件を理解し、実現可能かつ戦略的な賃上げ計画を立てることが不可欠です。

行政による賃上げ・生産性向上支援について
行政では様々な昨今の急激な賃上げや人手不足等の対応として様々な支援制度を用意しています。
お困りの方はこちらもご覧下さい。
2025年下旬発表|全29施策|中小企業・小規模事業者向け賃上げ・生産性向上支援施策まとめ【厚労省・中小企業庁】
→ https://hojyokin-hiroba.com/2025-chusho-kigyo-shien-saisin/
7. 補助金・融資支援スキルは「経営資源」になる
補助金や融資の知識は、単なる「制度理解」にとどまりません。実はそれ自体が、企業の持続的成長を支える「経営資源」として機能します。経営資源とは、一般に「ヒト・モノ・カネ・情報」の4つに分類されますが、補助金・融資支援スキルはこれらすべてに関わる横断的な力を持っています。
🧠 経営者の「知的資産」としての価値
補助金制度は年々複雑化し、政策誘導型の色合いを強めています。経営者がこの制度を理解し、適切に活用できるようになることで、以下のような知的資産が蓄積されます:
- 国の政策動向を読み解く力
- 自社の経営課題を制度に照らして整理する力
- 投資判断の精度を高める力
- 社内外のステークホルダーと連携する力
これらはすべて、企業の競争力を高める「見えない資産」として機能します。
🔄 補助金スキルがもたらす経営資源への波及効果
| 経営資源 | 補助金スキルが与える影響 |
|---|---|
| ヒト(人材) | 社員のスキルアップ、採用力・定着率の向上 |
| モノ(設備) | 最新設備の導入による生産性向上 |
| カネ(資金) | 自己資金の温存、資金繰りの安定化 |
| 情報(知識) | 政策・市場動向の把握、戦略的意思決定 |
補助金を活用することで、単なる資金調達にとどまらず、企業全体の経営資源を強化することが可能になります。
📚 補助金・融資支援スキルは「再現性のある武器」
一度補助金を活用した経験があれば、次回以降の申請や制度選定もスムーズになります。さらに、社内にノウハウを蓄積すれば、外部に依存せずに継続的な制度活用が可能になります。
このスキルは、経営者自身の武器であると同時に、企業の「組織的な資産」としても価値を持ちます。
8. 補助金・融資コンサルタント育成講座のご紹介
補助金制度を理解し、経営に活かすためには、実務に即した体系的な学習が不可欠です。そこでおすすめしたいのが、【補助金・融資コンサルタント育成講座】です。この講座は、補助金や融資支援の実務を体系的に学びたい経営者や士業、コンサルタントの方に向けて設計されています。
🎓 講座の特徴
- 実務に直結したカリキュラム
補助金・融資支援の全体像から、申請書の作成、事業計画の立案、着金後のフォローアップまで、現場で必要なスキルを網羅。 - 初心者でも安心の設計
補助金業務未経験者を対象に、基礎から丁寧に指導。Zoomによるオンライン講義で全国どこからでも受講可能。 - 実践的な演習と課題
小規模事業者持続化補助金を題材に、実際の申請書作成を体験。自社の事業計画を講義内でブラッシュアップすることも可能。 - 講師は現役の行政書士・経営者
補助金支援の現場経験が豊富な講師が担当。経営者目線でのアドバイスが受けられるのも大きな魅力です。 - 受講後のフォローも充実
卒業後には、WEB集客講座や事務所見学会、懇親会など、実務に活かせるサポート体制が整っています。
📅 講座スケジュール(例)
- 全10回(1回あたり約4時間)+追加講義1回
- 2025年2月〜7月にかけて開催
- プレ講義や無料体験動画もあり
💬 受講者の声(一部抜粋)
「補助金の仕組みだけでなく、実際の業務の流れや注意点まで学べた」
「講師の熱意と実務経験に裏打ちされた内容で、すぐに現場で活かせた」
「補助金支援を業務の柱にできる自信がついた」
📌 こんな方におすすめ
- 自社の補助金申請を自力で進めたい経営者
- 顧客からの補助金相談に対応したい士業・コンサルタント
- 補助金・融資支援を新たな事業の柱にしたい方
9. まとめ:補助金を「経営の武器」にするために
補助金制度は、単なる「もらえるお金」ではありません。それは、企業の未来を切り拓くための「経営戦略ツール」であり、正しく理解し活用することで、事業の成長を加速させる強力な武器になります。
✅ 経営者が補助金を学ぶべき理由の再確認

◆補助金は経営戦略と直結しており、経営者の判断が不可欠
◆制度の変化に即応できるのは、企業全体を見渡せる経営者だけ
◆賃上げ要件や社会的要請に対応するには、経営視点が必要
◆外注任せではノウハウが蓄積されず、リスクも高まる
◆補助金スキルは、ヒト・モノ・カネ・情報すべてに波及する「経営資源」
🚀 今こそ、経営者が一歩踏み出すとき
2024年度の補正予算では、経済産業省関連だけで約4.4兆円もの予算が中小企業支援に充てられています。このチャンスを活かすかどうかは、経営者の行動次第です。
補助金制度を「難しそう」「誰かに任せればいい」と敬遠するのではなく、「経営の武器」として自らの手で使いこなす。その姿勢こそが、これからの時代の経営者に求められる資質です。
📌 最後に
補助金制度は、知っているか知らないか、活かせるか活かせないかで、企業の未来に大きな差を生みます。
「補助金は経営者が学ぶ時代」——その第一歩を、今ここから踏み出してみませんか?
補助金・融資コンサルタント育成講座
補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
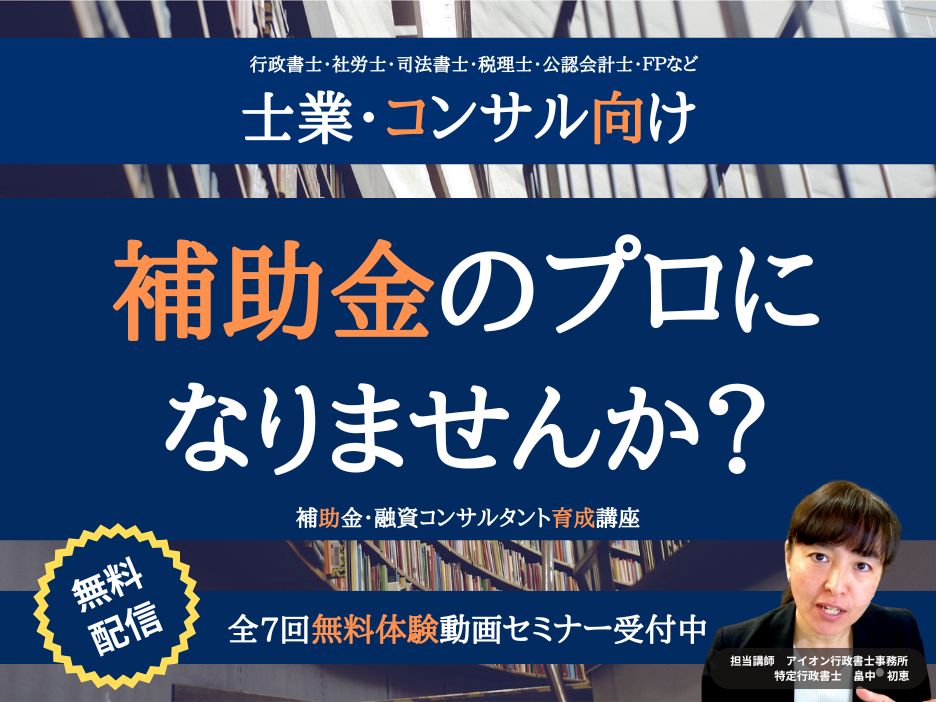
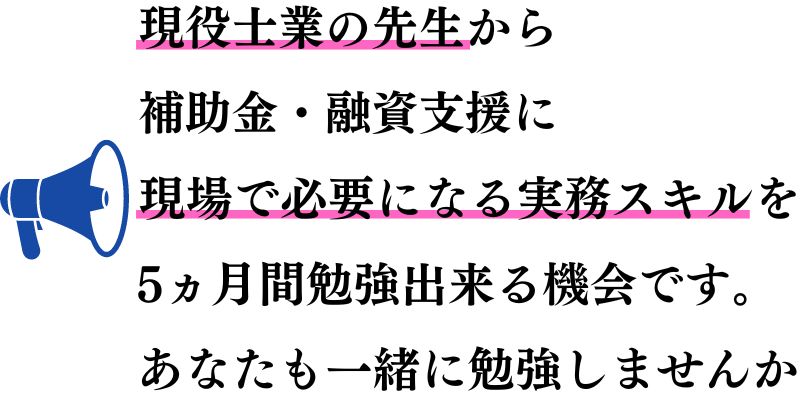

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。