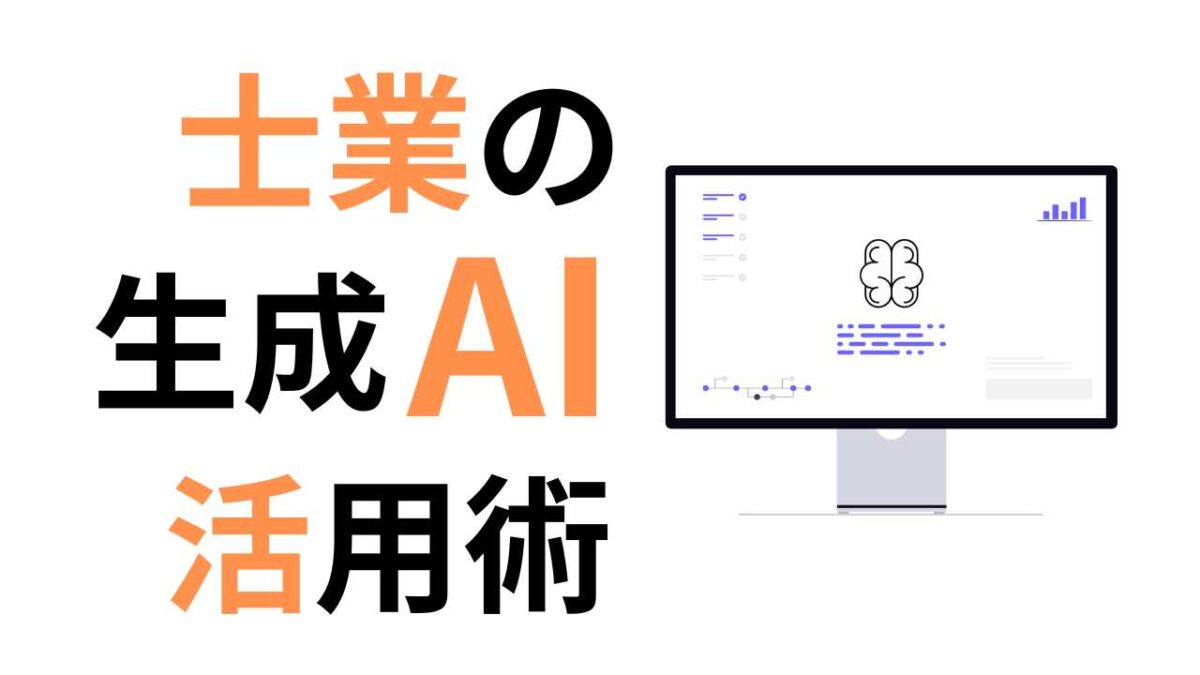🧭 はじめに|士業とAIの関係性とは
近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、士業(税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士・中小企業診断士・弁護士・公認会計士など)の業務に大きな変化が生まれています。
「AIに仕事を奪われるのではないか」と不安に感じる声がある一方で、「業務効率化の強力なツールになる」と期待する声も少なくありません。
実際、AIは士業の日常業務においてどのように活用できるのでしょうか?
そして、導入する際にどのような点に注意すべきなのでしょうか?
本記事では、士業として生成AIを活用する具体的な方法や注意点、さらに当社が実際に各士業の先生方から伺った活用事例も交えながら、AI活用のリアルをわかりやすく解説します。
✅ 目次
- はじめに|士業とAIの関係性とは
- 生成AIの基本と士業における活用可能性
- 士業が押さえておきたいプロンプトの基礎知識と活用のコツ
- 初心者向け士業別プロンプトテンプレート集
- テンプレート利用時の注意点
- 現場の先生方から伺った実際の現場とAI活用事例
- 生成AIの活用例まとめ|書類作成・調査・議事録
- 今後の展望|AIと士業の共存戦略
- まとめ|AIは士業の味方か?
🤖 生成AIの基本と士業における活用可能性

近年、急速に注目を集めている「生成AI」とは、自然言語処理技術を活用し、文章や画像、音声、プログラムコードなどを自動で生成できる人工知能のことを指します。代表的な生成AIとして、ChatGPT(OpenAI)、Claude(Anthropic)、Gemini(Google)などが知られています。
これらの生成AIは、膨大なデータをもとに人間と自然に会話できるほど高精度な回答を作成する能力を持ち、既にビジネスのさまざまな場面で活用が進んでいます。
士業においても、生成AIは単なる話題に留まらず、「業務効率化」「生産性向上」「サービス品質の向上」といった具体的な成果につながる強力なツールとして活用され始めています。
ここでは、士業での主な活用領域を詳しくご紹介します。
📄 1. 書類作成の草案生成
契約書、議事録、提案書、申請書類、顧問先への報告書など、士業が日々作成する文章は非常に多岐にわたります。
生成AIを活用すれば、こうした書類の「たたき台(初稿)」を短時間で作成することが可能です。
例えば、税理士が顧問先に提出する業績報告書のドラフトを生成AIに作成させ、内容を確認・修正することで、大幅な時短につながります。

当社からのアドバイス:士業として生成AI活用する際の注意点
完全にAI任せにするのではなく、「60〜70%までAIで作成し、残りは専門家が仕上げる」という使い方が成果物が正確、かつ作業効率が高いAI活用手法です。
🗣 2. 音声データの文字起こしと要約
最近では、面談や会議の録音データをAIで文字起こしし、さらに要点を自動でまとめるツールも増えています。
これにより、議事録作成や面談記録の作成時間を大幅に短縮できます。
例えば、社会保険労務士が顧問先とのヒアリング内容をAIに文字起こしさせ、その要約を作成することで、効率的に資料を整えることが可能です。

アドバイス:オススメ無料サイト
弊社では、ユーチューブ等の動画を作成した際、収録した動画の音声をテキストデータに文字起こしする必要がある場合は下記のサイトを利用して音声を文字に変換しています。(2025年11月現在)毎日3件まで無料で処理してくれます。
TurboScribe → https://turboscribe.ai/ja/dashboard
🔍 3. 法令・税制・労務関連の事前リサーチ
生成AIは、膨大な知識をもとに、法改正の背景や制度の概要をスピーディーに整理することができます。
例えば、「電子帳簿保存法の改正ポイント」「最新の雇用調整助成金の概要」といった事前情報の収集に活用できます。
ただし、AIの知識は必ずしも最新の法令を反映しているとは限らないため、最終的な法的根拠は必ず一次情報で確認する必要があります。
📚 4. FAQ・説明資料の作成補助
顧問先からよくある質問(FAQ)の回答例や、業務フローを説明する資料の作成を生成AIで効率化することも可能です。
例えば、司法書士が「相続登記に関するよくある質問」をAIに作成させれば、顧問先対応の品質向上につながります。また、担当者が不特定多数から受ける同じ内容の質問に回答する接客時間を大幅に減らすことが可能です。
🛠 5. 業務マニュアル・ナレッジの整理
事務所内での業務マニュアル作成や、過去の事例整理にも生成AIは有効です。
たとえば、過去の顧問先対応履歴をもとに、「似たようなケースの対処法をまとめる」など、ナレッジ共有を加速できます。
⚠️ 活用時の重要な注意点
生成AIは非常に便利なツールですが、出力された内容は「必ず正しい」とは限りません。
特に法律・税務・労務といった分野では、AIの誤った情報をそのまま使用すると、重大なミスや顧客トラブルにつながる可能性があります。
生成AIの回答はあくまで「参考情報」として活用し、最終的な確認・判断は必ず士業本人が行うことが大前提です。
また、顧客情報や機密情報を入力する場合は、利用規約や情報管理のリスクも十分に確認する必要があります。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
💬 士業が押さえておきたいプロンプトの基礎知識と活用のコツ
生成AIを効果的に活用するためには、「プロンプト(AIへの指示文)」の設計が非常に重要です。
特に士業が業務で生成AIを活用する場合、正確で実用的なアウトプットを得るためのプロンプトの書き方を理解しておく必要があります。ここでは、士業が押さえるべきプロンプトの基本と、活用する際の具体例・注意点について詳しく解説します。
📝 プロンプトとは何か?

プロンプトとは、AIに対して「どのようなアウトプットを求めるのか」を具体的に伝える指示文のことを指します。
生成AIは、このプロンプトの内容に従って文章を作成したり、質問に回答したりします。
同じテーマであっても、プロンプトの書き方次第でAIが出力する回答の質は大きく変わります。
最近では、プロンプトの設計を専門に行う「プロンプトエンジニア」と呼ばれる新たな職種も登場しており、いかに適切なプロンプトを作成するかが、生成AIを効果的に活用するための重要なポイントとなっています。
✅ 良いプロンプトを作る4つのポイント
士業が実務で使う場合、次のポイントを意識すると、より正確で実務的な回答を引き出すことができます。
- 目的を明確に伝える
例:「契約書の草案を作成してください」「〇〇についての法令概要をまとめてください」 - 対象者・前提条件を伝える
例:「中小企業の経営者向けに」「専門家ではない顧客向けに」 - 形式を指定する
例:「箇条書きで」「A4一枚程度で」「表形式で」 - 除外事項・注意点を伝える
例:「最新の法改正が反映されているかを確認する必要があります」「法的根拠は必ず別途確認すること」
💡 士業で使える具体的なプロンプト例
ケース1|契約書のたたき台作成
プロンプト例:
「業務委託契約書の草案を作成してください。対象はITシステム開発の委託で、委託内容はアプリケーション開発、契約期間は1年、報酬は月額固定です。法的な正確性は必ず専門家が確認する前提で、まずは一般的な構成で作成してください。」
ケース2|顧問先向けFAQ作成
プロンプト例:
「相続登記の手続きについて、一般の顧客向けに分かりやすく、よくある質問と回答の例を5つ作成してください。専門用語は可能な限り避け、初学者にも理解できる表現にしてください。」
ケース3|最新法改正の概要整理
プロンプト例:
「令和6年施行の電子帳簿保存法改正について、中小企業の経営者向けに、A4一枚程度で簡潔に説明文を作成してください。詳細は必ず一次情報で確認する前提で、ポイントを絞って整理してください。」
ケース4|議事録作成補助
プロンプト例:
「以下の面談メモを基に、議事録形式でまとめてください。重要事項は箇条書きで整理し、時系列順で構成してください。(面談メモ:……)」
⚠️ プロンプト活用時の注意点
士業がAIを使う際には、以下の点を特に意識する必要があります。
- AIの回答をそのまま使わない
AIは誤情報や不正確な内容を出力することがあります。必ず専門家自身が確認・修正を行いましょう。 - 最新情報が反映されているかを必ず確認する
AIは学習データの更新が遅れている場合があります。特に法改正などは最新の法令を必ず別途確認してください。 - 機密情報の取り扱いに注意する
AIツールによっては、入力した情報が学習に利用される可能性があります。利用規約や情報管理の観点を必ず事前に確認しましょう。 - AIが得意な業務と不得意な業務を見極める
AIは「文章の整理」「要点の抽出」「ひな形作成」には強い一方で、「法的判断」「最新法改正の厳密な確認」「事実確認」などは不得意です。
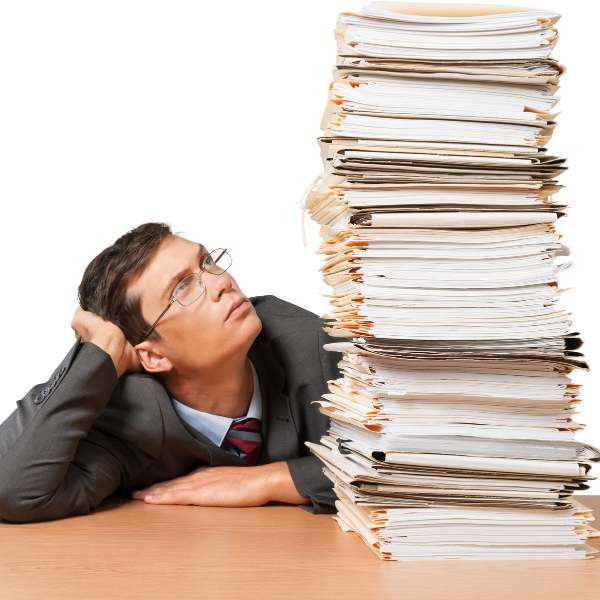
生成AIは、上手に活用すれば士業の業務を強力にサポートしてくれるツールです。
重要なのは、「何を求めるか」「どう使うか」を人間がしっかりコントロールすることです。
次のセクションでは、初心者向け士業別テンプレート集と題して、士業であれば誰でもすぐに活用できる、生成AI用の具体的なプロンプトテンプレートをいくつかご紹介します。
初めてAIを使う方でも取り組みやすいよう、実務に直結した内容を中心にまとめています。
是非ご活用下さい。
📂 初心者向け士業別プロンプトテンプレート集
ここでは、各士業の代表的な業務に対してすぐに使える生成AIのプロンプト例をご紹介します。
まずは以下のテンプレートを参考に、必要に応じて自分の業務内容に合わせてカスタマイズしてみてください。
🧮 税理士向けプロンプト例
① 税務顧問先への業績報告書(ドラフト作成)
プロンプト:
「以下の財務データを基に、中小企業向けの業績報告書のドラフトを作成してください。専門用語は使わず、分かりやすくまとめてください。(財務データ:〇〇〇)」
② 最新税制改正の概要まとめ
プロンプト:
「中小企業経営者向けに、令和6年度の税制改正の主要ポイントをA4一枚程度でわかりやすくまとめてください。法律用語はできるだけ避けてください。」
🏢 社会保険労務士向けプロンプト例
① 雇用契約書の草案作成
プロンプト:
「新入社員向けの雇用契約書の草案を作成してください。就業場所は本社、労働時間は9時〜18時、残業あり、雇用形態は正社員です。」
② 労務手続きの顧問先向け案内文
プロンプト:
「36協定の届出について、中小企業の顧問先に案内する文書を作成してください。専門用語は極力避け、わかりやすい説明にしてください。」
🖋 司法書士向けプロンプト例
① 相続登記の流れ説明資料
プロンプト:
「相続登記の手続きの流れを、一般の顧客向けにわかりやすく説明した資料を作成してください。図表は使用せず、文章で説明してください。」
② 議事録作成(合同会社の定時社員総会)
プロンプト:
「以下の会議内容を基に、合同会社の定時社員総会議事録を作成してください。(会議内容:〇〇〇)」
🖊 行政書士向けプロンプト例
① 建設業許可申請の必要書類案内
プロンプト:
「建設業許可申請に必要な書類と申請の流れについて、顧客向けの案内文を作成してください。専門用語はできるだけ避け、分かりやすく説明してください。」
② 契約書作成のたたき台
プロンプト:
「業務委託契約書のたたき台を作成してください。依頼内容はホームページ制作、契約期間は6ヶ月、報酬は納品後一括支払いです。」
📊 中小企業診断士向けプロンプト例
① 経営課題の整理と提案書作成
プロンプト:
「以下の経営課題に対して、中小企業経営者向けの改善提案書を作成してください。現状の課題と提案をセットで箇条書きにしてください。(課題:〇〇〇)」
② 事業計画書のドラフト作成
プロンプト:
「〇〇業界の新規事業計画書のドラフトを作成してください。事業内容、ターゲット市場、収支予測を簡潔にまとめてください。」
⚖️ 弁護士向けプロンプト例
① 委任契約書のひな形作成
プロンプト:
「弁護士と顧客間の委任契約書のひな形を作成してください。案件内容は交通事故の示談交渉、委任期間は案件解決までとしてください。」
② 相談者への回答文案作成
プロンプト:
「以下の法律相談内容に対する回答文を作成してください。相手は法律に詳しくない一般の方ですので、平易な表現でまとめてください。(相談内容:〇〇〇)」
🛑 テンプレート利用時の注意点
- AIの生成内容はあくまで参考とし、必ず専門家自身が法的・事実確認を行うこと
- プロンプトの指示が曖昧だと、AIは不十分な回答を出す場合があるため、できるだけ具体的に指示すること
- 機密情報や個人情報は不用意に入力しないこと(利用しているAIツールの情報管理規約を必ず確認)
※例えば、クライアントの決算書をAIに読み込ませる場合は、書面のクライアント名など、クライアントを特定できないように工夫するなどの必要があります。

生成AIは、正しく使えば、士業の業務負担を大きく軽減し、より価値の高い業務に集中できる時間を生み出してくれます。
本記事のテンプレートを参考に、自分の業務に合ったプロンプトをぜひ試してみてください。
現場の先生方から伺った実際の現場とAI活用

生成AIは理論上、士業の業務を大きく効率化できると期待されていますが、実際の現場では「思ったほど効果が出ない」「むしろ手間が増えた」という声も聞かれます。
AIはどのように活用されているのか、どのような課題があるのか——。ここでは、実際に士業として現場でAIを試行・導入された先生方から弊社が直接伺った具体的な事例をいくつかご紹介します。
税理士・社会保険労務士・行政書士、それぞれの現場でのAI活用のリアルな成果と、そこから見えてきた注意点をご紹介しますので、今後の事務所運営などの参考になさって下さい。
💼 税理士業務におけるAI活用事例と課題
税理士業務:会計処理におけるAI活用の実験結果
ある税理士がAIの活用状況について自身の顧問先へヒアリングを行ったところ、ある顧問先が経理業務においてAIを活用し、処理時間の短縮が可能か否かの実験を行った経緯と結果をお教え頂いたそうです。
この実験では、ある月の領収書や証憑書類を対象に、従来の方法とAIを活用した方法の二つを比較しました。一つ目は、従来どおり社内の事務員が証憑データを手入力しながら経理仕訳を行う方法です。もう一つは、すべての領収書をスキャンし、AIがデータを自動で読み取り、仕訳処理を行う方法でした。
実験の結果、ベテラン事務員が手入力で処理した方が、AIを活用した場合よりも早く正確に処理を終えることができたという結果になったそうです。
最近では「AIは万能」といったイメージを持たれることも少なくありませんが、実際の現場では、必ずしもAIが人間よりも優れているとは限りません。特に会計業務における仕訳処理のスピードや正確性については、現段階では人間の方が優れている場面がまだ多く存在していることがこの結果からも分かります。
比較内容:
| 処理方法 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 従来型 | 事務員が証憑データを手入力で仕訳 | 最も早く処理完了 |
| AI活用型 | 領収書をスキャンし、AIが自動仕訳 | 処理に時間がかかった |
この結果からわかったこと:現時点ではAIは必ずしも人間よりも優れているとは限らず、特に仕訳のスピードや正確性ではベテラン事務員に軍配が上がるケースもある。
税理士がAIを活用する際のポイント
- AIは「補助的ツール」として活用するべき
- 現状ではOCRによる証憑データの読み取りは精度やスピードに難あり
👥 社会保険労務士が実践するAI活用とおすすめツール
社会保険労務士業務:社労士とAI活用の現状
近年、社会保険労務士の業務にもChatGPTのような生成AIを活用する動きが見られています。たとえば、各種書類の作成や処理データの整理に生成AIを試験的に導入したケースもありますが、その出力結果は必ずしも正確とは言えず、現時点では注意が必要です。実際にAIを業務で繰り返し活用した社労士の先生方からは、「専門業務をAIに完全に任せるのはまだ難しい」といった声が多く聞かれています。

一方で、すでに社労士業務に特化したプログラムが組まれている有料の専用サービスについては、現在でも十分に実務で活用できるレベルに達していると評価されています。こうしたサービスは、正確性や法改正への対応もスピーディーで、実際の業務での導入も進んでいます。
ここで、実務で特に活用されているオススメの有料サービスをいくつかご紹介します。
実務で活用されている有料サービス
| サービス名 | 主な機能 | 特徴 |
|---|---|---|
| SmartHR | 労務手続き、年末調整、入退社管理 | UIが直感的で導入しやすい |
| Jinjer | 勤怠・給与・人事情報の一元管理 | 中小企業向けに人気 |
| freee人事労務 | 給与計算、マイナンバー管理 | 会計freeeとの連携が強み |
注意点
- 無料の生成AI(ChatGPTなど)は誤情報を含む可能性がある
- 法令解釈や制度変更への対応は専門家の判断が不可欠
- 有料サービスは法改正への対応が早く、実務向き
📝 行政書士業務における生成AIの活用と注意点
行政書士は補助金申請書や契約書、各種許認可申請など、文書作成が中心の業務です。生成AIの活用余地は大きい一方で、リスクも存在します。
実例:補助金申請書の草案作成
当社で試験的にChatGPTを使って補助金申請書の草案を作成したところ、過去の公募要領に基づいた古いルールが一部の記述で反映されてしまい、誤った内容が含まれた事業計画書が作成されてしまいました。
活用のポイント
- AIは「たたき台」を作るツールと割り切る
- 最新の公募要領や法令に基づいて専門家が必ず確認・修正
- 契約書や申請書の最終版は必ず人間がレビュー

当社からのアドバイス:AIとの適切な付き合い方
AIに、こちらが希望する完成度の高い成果物を作成させるためには、現時点では相応の時間をかけて、精度の高いプロンプト(指示文)を丁寧に作成する必要があります。
同じ作業を繰り返し行う場合であれば、プロンプト作成に時間を投資する価値は十分にありますが、私たちのような専門家の場合、クライアントごとに求められる成果物が依頼ごとに異なり、求められる成果の内容も非常に多様です。
こうした個別性の高い業務において、現在のAIの能力では、私たちの仕事を完全に代替するのはまだ難しいのが実情です。
現状では、AIはあくまで「補助的なツール」として、書類の草案作成や音声データの文字起こしといった、比較的重要度の低い業務に活用するのが現実的だと考えます。AIと自身の業務を賢く仕分けることで、私たちが本来集中すべき重要な業務に、より多くの時間が割けるようになることでしょう。
✍️ 生成AIの活用例まとめ|書類作成・調査・議事録
書類作成の草案生成
- 会議資料、提案書、銀行提出用事業計画書、補助金申請書など
- 書類の「骨子」を短時間で作成可能
音声データの文字起こしと要約
- 会議や面談の音声を文字起こしし、要点をAIで要約
- 議事録作成の時間を大幅に短縮
法律・会計・労務の事前調査
- 法令や制度の概要をAIに質問して把握
- 正確性に限界があるため、あくまで「下調べ」として活用
🔮 今後の展望|AIと士業の共存戦略
生成AIの進化は、士業の業務に確実に影響を与え始めています。
今後、AIの技術はさらに進化し、士業の働き方は大きく変わっていくことが予想されます。ここでは、これから士業がどのようにAIと向き合い、どのように価値を発揮していくべきか、未来の共存戦略について考察します。
AI時代に求められる士業の未来像
これからの士業は、「AIにできること」と「士業にしかできないこと」の明確な切り分けが求められます。
1. 定型業務はAIに任せ、士業は付加価値業務に集中する
帳票の作成、議事録の整理、申請書の草案作成といったルーティン業務は今後、ますますAIに置き換えられていくでしょう。
こうした業務をAIに効率よく任せることで、士業はより「提案型業務」「顧客課題解決型業務」といった高付加価値の仕事に集中できる時代になります。
2. クライアントとの対話力・提案力がより重要になる
生成AIは事実整理や文章作成は得意ですが、「相手に寄り添った提案」「顧客の背景を踏まえた判断」はできません。
だからこそ、士業はクライアントとの深いコミュニケーションを通じた信頼構築力、状況に応じた最適な提案力が今後ますます評価されるようになります。
3. AIを活用できる士業が「選ばれる専門家」となる
今後は、「AIに業務を奪われる士業」と「AIを使いこなす士業」に二極化すると考えられます。
単純作業に時間をかけ続ける士業は市場で淘汰されていく一方で、「AIを業務に上手に取り入れ、生産性を高めることができる士業が“選ばれる専門家”」となっていくでしょう。
士業が今から取り組むべきこと
- 生成AIの基本操作を身につける
まずは自分の業務で使えるAIツールに触れ、プロンプトの作り方やAIの特性を理解することが第一歩です。 - AI活用ルールを自分の事務所で整備する
機密情報の取り扱いや、AIと人間の責任範囲を明確にし、リスク管理を徹底することが重要です。 - 専門家としての判断力・提案力を磨く
AIに置き換えられない「人としての価値」を高める努力を続けることが、これからの時代の士業に求められる姿勢です。
生成AIは、士業にとって「敵」ではなく「強力なパートナー」です。
単純作業に追われるのではなく、AIを活用しながら士業として本来の専門性を発揮し、顧客に選ばれ続ける存在を目指すことが、これからの時代を生き抜くための共存戦略だといえるでしょう。
🧩 まとめ|AIは士業の味方か?
生成AIは、士業にとって「敵」ではなく、正しく使えば「最強の味方」になり得ます。
✅ AIは士業の業務をどう変えるか?
- 定型業務の効率化:書類作成や議事録、調査業務など、時間のかかる作業を短縮
- 情報整理と要約:膨大な法令・制度情報を整理し、要点を抽出
- たたき台の生成:契約書や申請書の草案を短時間で作成可能
- 専門性の強化:AIに任せられる部分を任せることで、士業本来の専門性に集中できる
⚠️ ただし、過信は禁物
- 出力内容の正確性には限界がある(ハルシネーションのリスク)
- 最新の法令や制度変更には対応できないこともある
- 個人情報や機密情報の取り扱いには細心の注意が必要
💡 専門家としての価値を高めるには?
- AIを「使いこなす」スキルを身につける
- 最終的な判断・修正は必ず自分で行う
- クライアントに対しては、AIでは提供できない「提案力」「信頼性」「人間的な対応力」で差別化する
📣 補助金や助成金の最新情報を知りたい方は、ぜひ「補助金の広場」もチェックしてみてください。
士業・コンサルタントの皆様に役立つ情報を随時発信しています!
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
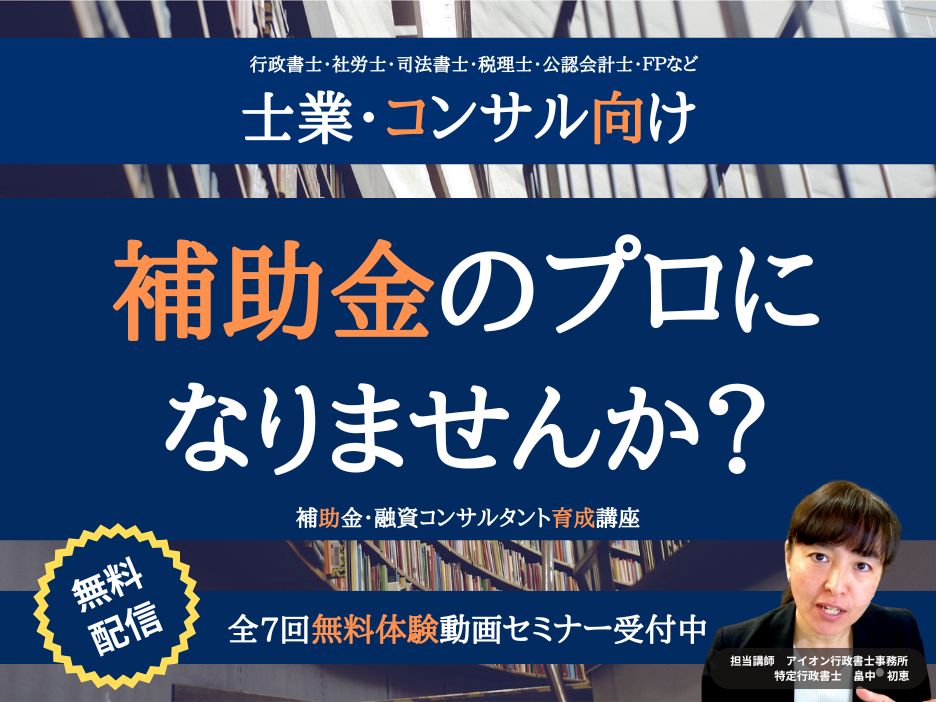
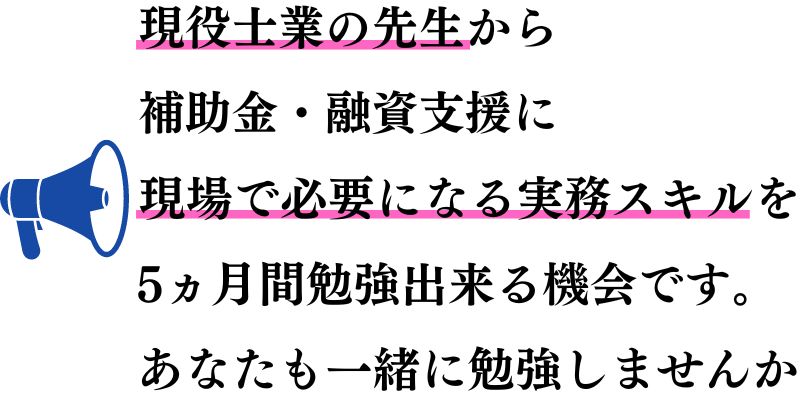

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。