🏢はじめに:事業承継・M&A補助金とは?
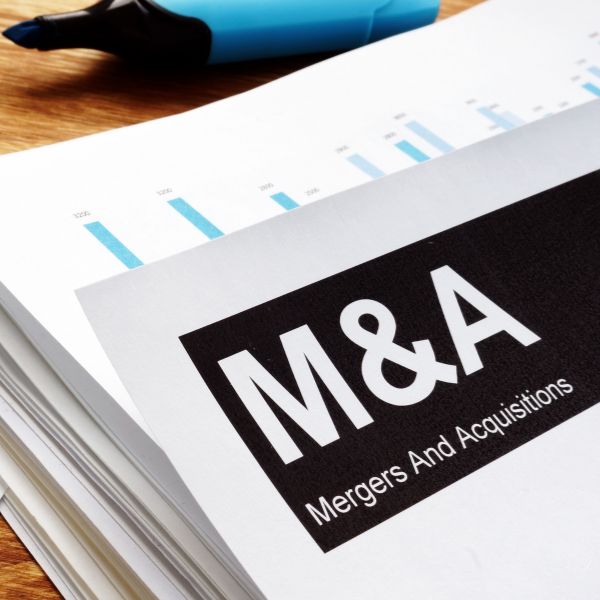
中小企業の事業承継やM&A(Mergers & Acquisitions:合併・買収)は、事業の持続と地域経済の活性化に欠かせない取り組みです。しかし、専門的な支援を必要とする場面も多く、費用面での負担も少なくありません。こうした課題に対応するため、国が支援する「事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)」は、中小企業者等が専門家を活用しながら事業再編・事業統合を進める際に、その経費の一部を補助する制度です。
2025年度の「11次公募」においては、「買い手支援類型」と「売り手支援類型」の2パターンが設定されており、それぞれの立場に応じて補助の対象や要件が定められています。この記事では、事業承継・M&A補助金について、その対象者、補助対象経費、申請の流れなどを11次公募の情報を元に網羅的に解説し、制度の正しい理解と活用方法をご紹介します。
🎯補助金の目的と背景
日本において、中小企業は経済の屋台骨を担う重要な存在です。しかし、少子高齢化や後継者不足が進む中、事業承継を円滑に進められない企業が年々増加しています。これは雇用の喪失や地域経済の衰退につながる深刻な課題でもあります。
こうした状況を踏まえ、経済産業省は中小企業の事業承継やM&Aを促進するため、「中小企業生産性革命推進事業」の一環として「事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)」を創設しました。制度の狙いは、経営資源(人材、ノウハウ、設備、顧客など)の円滑な引継ぎと、中小企業の持続的な成長の実現です。
この補助金には大きく2つの類型があります。
- 買い手支援類型(Ⅰ型)
事業再編や統合を通じて経営資源を譲り受ける企業を対象に支援を行います。シナジー効果による生産性向上や地域経済の牽引が期待される事業が対象です。 - 売り手支援類型(Ⅱ型)
経営資源の譲渡を通じて事業を第三者に承継し、地域の雇用や経済活動を継続させることを目的とした事業が対象です。
いずれも専門家の活用を前提としており、経営・法務・財務などの分野における支援を通じて、スムーズな事業承継・統合を目指します。
この補助金の根底にあるのは、企業価値を将来に引き継ぐという視点です。単なる事業譲渡ではなく、地域や社会との接点を持った経済活動の継続が重視されています。
👥対象者の条件と申請要件
「事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)」を活用するためには、一定の条件を満たすことが求められます。申請者は中小企業者等であることが前提となり、さらに事業の形態や内容によって細かい要件が設定されています。
対象者の基本条件
以下のような属性を持つ企業・事業者が申請可能です:
- 日本国内で事業を営む中小企業者または個人事業主
- 法人の場合:設立登記済で、3期分の決算と申告が完了していること
- 個人事業主の場合:「開業届」および「青色申告承認申請書」の提出日から5年以上が経過していること
- 法令遵守の体制が整っていること
- 暴力団など反社会的勢力との関係がないこと
- 他の補助金制度で重大な違反がないこと
- 補助金活用についての理解と適切な対応ができること
- 事務局からの問い合わせや追加資料の依頼に応じる姿勢があること
- 交付後の報告・審査対応などにも責任を持つこと
対象となる中小企業者の定義
中小企業基本法に基づき、資本金や従業員数などによって対象が以下のように分類されます:
| 業種 | 資本金または出資金 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下(※) | 100人以下(※) |
※業種によって特例があります。例:ソフトウェア業は従業員300人以下まで認められる等。
共同申請について
「売り手支援類型(Ⅱ型)」では、株主代表や支配株主との共同申請が認められる場合があります。申請の主体となる補助対象者が補助経費を負担することが必須で、契約主体も明確にする必要があります。
また、同一事業者による複数申請は原則として不可ですが、例外的に複数の対象会社を異なる承継者に引継ぐ場合は複数申請が認められます。
💰補助対象となる経費の詳細
事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)は、対象となる経費に対して「補助率」や「上限額」が設定されています。補助対象経費は事業再編・統合に直接必要なものであり、補助事業期間中に契約・支払が完了していることが条件です。
補助対象となる主な経費
補助金では、以下のような費目に対して支援が行われます。
🔹事業費として認められる経費
- 謝金
- 専門家(士業、大学教授等)への講義料・指導料
- 旅費
- 専門家による支援活動に伴う国内・海外出張費(公共交通機関利用に限る)
- 外注費
- 一定の成果を求める業務請負(契約の上、業務完遂が条件)
- 委託費
- M&A支援に関する専門家(FA、仲介者等)との契約費(着手金、成功報酬等含む)
- システム利用料
- M&Aマッチングプラットフォームへの登録料・利用料
- 保険料
- 表明保証保険の保険料(買い手・売り手支援類型に応じた手配)
※FA・仲介に係る委託費は、「M&A支援機関登録制度」に登録された専門業者による支援に限ります。
🔹売り手支援類型における廃業関連費用
- 廃業支援費
- 登記手続きや司法書士への費用
- 在庫廃棄費
- 自己所有の在庫処分にかかる費用(売却ではなく廃棄)
- 解体費
- 建物や設備の撤去費用(自己所有に限る)
- 原状回復費
- 借用物件の返却に伴う修繕費
- リース契約の解約費・移設費
- ファイナンスリース解約、設備の撤去・再配置などに要する費用
補助率と補助額
補助額は補助対象経費の最大2/3までとされ、上限・加算額も定められています。
| 類型 | 補助率 | 補助額(基本枠) | DD費用加算 | 廃業費加算 |
|---|---|---|---|---|
| 買い手支援類型(Ⅰ型) | 経費の2/3以内 | 最大600万円 | 最大200万円 | 最大150万円 |
| 売り手支援類型(Ⅱ型) | 経費の1/2~2/3以内※ | 最大600万円 | 最大200万円 | 最大150万円 |
※補助率2/3が適用されるのは営業利益低下や赤字企業など一部条件を満たす事業者のみ
注意事項
- 契約は交付決定後に締結する必要があります。事前契約・事前支払は補助対象外となります。
- 実績報告書にて経費の正当性・支払の完了を証明する必要があります。
- 契約相手との関係性(親族やグループ内)によっては、対象外となることがあります。
- 経費の計上にあたっては、原則として2社以上からの相見積取得が必須です。
🧩支援枠の種類とそれぞれの特徴

事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)は、「買い手支援類型(Ⅰ型)」と「売り手支援類型(Ⅱ型)」の2つの支援枠から構成されています。それぞれの類型は、M&Aにおける立場の違いに応じて、補助対象者や補助対象経費が異なるため、自身の状況に合った枠を選択することが重要です。
🔹買い手支援類型(Ⅰ型)
これは、M&Aなどによって他社から株式や事業資源を譲り受ける立場にある企業や個人事業主を対象としています。経営資源の獲得後に生産性向上や地域貢献が見込まれる事業が支援の対象になります。
主な特徴
- 補助率:経費の2/3以内
- 補助上限額:600万円まで(DD費用等加算で最大950万円まで)
- 支援対象:法人または個人事業主(一定の実績が必要)
- 経営資源引継ぎの形態:
◆株式譲渡、第三者割当増資、事業譲渡、吸収合併、吸収分割など
活用シーン例
- 地域の老舗企業を引き継ぎ、自社のサービスと統合
- 異業種の買収によって事業の多角化を図る
🔹売り手支援類型(Ⅱ型)
こちらは、自社の株式や事業資源を第三者に譲り渡す立場にある企業や株主を対象としています。M&Aによって地域の雇用や事業継続が確保される場合に支援を受けることができます。
主な特徴
- 補助率:原則1/2以内、一定の条件を満たすと2/3以内に引き上げ
◆例:営業利益率の低下、赤字決算など - 補助上限額:600万円まで(DD費用等加算で最大950万円まで)
- 支援対象:法人、個人事業主、支配株主、株主代表(共同申請可)
- 経営資源引継ぎの形態:
◆株式譲渡、第三者割当増資、事業譲渡、新設合併、株式交換、株式移転など
◆必要に応じて廃業が伴うケースも対象
活用シーン例
- 後継者のいない企業が、地元企業に事業を承継
- 株主が他社への譲渡を通じて会社の存続を図る
共通のポイント
- 経営資源の「実質的な引継ぎ」が条件
◆単なる不動産売買や親族内の承継は対象外 - 契約の当事者が中小企業であること
- M&Aの契約類型に応じて、申請形式や必要書類が細かく異なります
- 廃業関連経費を含める場合は、補助事業期間中に関連行為(設備撤去等)を完了している必要があります
これら2類型は、申請者の立場と事業の内容によって柔軟に活用できる設計となっており、正しい枠の選択が補助金活用の第一歩です。
📊採択率の傾向と最新データ
事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)は、申請件数に対して一定の採択率で交付が決定されます。採択率は年度や公募回によって変動しますが、過去の傾向を把握することで、申請の難易度や準備の重要性を理解することができます。
🔹最新の採択結果(第11次公募)
- 申請件数:590件
- 採択件数:359件
- 採択率:約60.8%
この採択率は、過去の公募回と比較しても平均的な水準であり、事業計画の完成度や専門家の選定が採択の可否に大きく影響することがうかがえます。
🔹過去の採択率の推移(専門家活用枠)
| 公募回 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
|---|---|---|---|
| 第7次 | 498件 | 299件 | 60.0% |
| 第8次 | 374件 | 229件 | 61.2% |
| 第9次 | 440件 | 275件 | 62.5% |
| 第10次 | 518件 | 318件 | 61.3% |
| 第11次 | 590件 | 359件 | 60.8% |
※出典:中小企業庁・中小機構による公式発表
🔹採択率から見えるポイント
- 採択率はおおむね60%前後で安定して推移
- 提出書類の不備や要件未達による不採択が多く、事前準備が重要
- 専門家の選定や事業計画の具体性が採択の鍵
- 【加点項目(地域貢献、雇用維持、デジタル化等)】を意識した計画が有利
採択率が高いとはいえ、申請すれば必ず通る補助金ではありません。しっかりとした準備と、制度への理解が成功のポイントです。
📝申請の流れと必要な準備
事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)を活用するには、事前準備から申請、事業実施、報告まで一連の流れを理解しておくことが重要です。以下では、申請のステップと必要な準備事項をわかりやすく整理します。

🔹申請の基本ステップ
- 公募要領の確認
- 中小企業庁や事務局が公開する最新の公募要領を熟読
- 類型ごとの要件や対象経費、補助率などを把握
- gBizIDプライムの取得
- 電子申請システム「jGrants」を利用するために必要
- 発行には2〜3週間かかるため、早めの取得が推奨されます
- 認定経営革新等支援機関への相談
- 税理士、公認会計士、商工会議所などが該当
- 事業計画の策定や申請書類の作成支援を受けることが可能
- 申請書類の準備と提出
- jGrants上で電子申請
- 必要書類(決算書、住民票、株主名簿など)を添付
- 審査・交付決定通知
- 書類審査を経て、採択された場合は交付決定通知が届く
- 補助事業の実施
- 交付決定後に契約・支払を行う
- 補助対象経費の範囲内で事業を遂行
- 実績報告・確定検査
- 事業終了後に報告書を提出
- 経費の妥当性や支払完了を証明する書類が必要
- 補助金の交付
- 検査通過後に補助金が支払われる
- 事業化状況報告(3〜5年間)
- 補助事業終了後も継続的な報告義務あり
📂申請時に必要な主な書類
| 類型 | 法人の場合 | 個人事業主の場合 |
|---|---|---|
| 買い手支援類型 | 履歴事項全部証明書、直近3期分の決算書、労働条件通知書 | 住民票、開業届、青色申告承認申請書、確定申告書 |
| 売り手支援類型 | 履歴事項全部証明書、株主名簿、直近3期分の決算書、住民票 | 同上 |
※加点項目に該当する場合は、認定証や計画書の写しも提出
⚠️注意点と準備のコツ
- 申請期間は短め:公募開始から締切まで約1ヶ月程度が多いため、早めの準備が必須
- 書類不備は不採択の原因:提出前に専門家とダブルチェックを推奨
- 加点項目の活用:地域貢献、賃上げ、健康経営などの加点要素を意識した計画が有利
- 契約・支払のタイミング:交付決定前の契約・支払は補助対象外となるため厳守
✅申請成功のためのポイントと注意事項
事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)は、制度の理解と準備の質によって採択率が大きく左右されます。ここでは、申請を成功に導くための重要なポイントと、よくある落とし穴を整理します。
🔹成功のためのポイント
- 事業計画の具体性と説得力
- 数値目標(売上、利益、雇用維持など)を明記
- M&Aによるシナジー効果や地域貢献を論理的に説明
- 専門家の適切な選定
- M&A支援機関登録制度に登録された専門家を選ぶ
- 実績や専門分野を確認し、信頼できるパートナーを確保
- 加点項目の活用
- 経営力向上計画、健康経営、賃上げ計画などの認定取得
- 加点項目は審査で有利に働くため、事前準備が重要
- 相見積の取得と契約のタイミング
- 原則2社以上からの見積書を取得
- 契約・支払は交付決定後に行う(事前契約は対象外)
- スケジュール管理
- 公募期間は短いため、gBizID取得や書類準備は早めに
- 事業実施期間も短いため、実行可能な計画を立てる
⚠️よくある注意点・落とし穴
| 落とし穴 | 内容 |
|---|---|
| 契約のタイミングミス | 交付決定前に契約・支払を行うと補助対象外になる |
| 見積書の不備 | 相見積がない、押印がない、金額が曖昧などは減額・不採択の原因 |
| 専門家が未登録 | M&A支援機関登録制度に未登録の業者は対象外になる可能性あり |
| 書類の不備 | 決算書の不足、株主名簿の未提出などで不採択になるケースが多い |
| 加点項目の未達 | 加点項目を申請して採択された場合、未達成だと次回以降減点対象になる |
| 承継計画の曖昧さ | 相手先未定、契約形態不明などは審査で不利になる |
📌専門家からのアドバイス(実務上のコツ)
- 事業承継の意思を明確に示す
- M&Aマッチングサイトへの登録、基本合意書の準備など、具体的な進捗を示す
- 補助金は後払いであることを意識
- 一旦自社で立替が必要。資金繰り計画も並行して立てる
- 他の補助金との併用に注意
- 同一経費の重複申請は不可。制度ごとの対象範囲を確認する
- 事業終了後の報告義務を忘れずに
- 3〜5年間の事業化状況報告が必要。継続的な対応体制を整えておく
申請は「書類勝負」と言われるほど、準備の質が問われます。補助金は単なる資金援助ではなく、事業の未来を切り拓くためのツールです。制度を正しく理解し、戦略的に活用することで、事業承継の成功率は格段に高まります。
🧭まとめと今後の展望

事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)は、単なる資金支援にとどまらず、中小企業の未来を支える戦略的な制度です。ここでは、これまでの内容を振り返りながら、今後の制度の方向性や活用の可能性について整理します。
🔹制度の総括
- 補助対象者の明確な定義:中小企業基本法に基づく分類により、対象者が明確化
- 補助対象経費の幅広さ:専門家費用、廃業関連費用、システム利用料など多岐にわたる
- 支援枠の柔軟性:買い手・売り手それぞれに対応した支援枠が用意されており、状況に応じた選択が可能
- 採択率の安定性:過去の公募では約60%前後で推移しており、準備次第で十分に採択が狙える
🔹今後の展望と制度の進化
2025年度からの制度改正により、以下のような動きが見られます:
- 支援枠の再編と拡充
- 「PMI推進枠」が新設され、M&A後の統合プロセス(人事制度・IT統合など)も補助対象に
- 「事業承継促進枠」では設備投資も対象となり、親族内承継にも対応
- 補助上限額の引き上げ
- 最大補助額が800万円〜1,000万円に拡大(賃上げ実施で加算)
- 専門家活用枠では、DD費用や廃業費用の加算により最大950万円まで支援可能
- 補助率の柔軟化
- 小規模事業者や赤字企業には補助率2/3が適用されるケースが増加
- 一部の大企業(100億円企業要件)には補助率1/3が適用される特例も導入
- 申請要件の厳格化と電子申請の標準化
- gBizIDプライムの取得が必須
- jGrantsによる電子申請が基本となり、書類の正確性がより重視される
🔹制度活用の可能性
- 事業承継の加速:後継者不在の企業が第三者承継を選択しやすくなる
- 地域経済の維持:雇用や取引関係を守りながら、企業の存続を支援
- M&Aの活性化:買い手企業が積極的に事業拡大を図るための後押しに
- 再チャレンジ支援:廃業後の新規創業や再スタートにも補助金が活用可能
補助金のプロを目指すなら
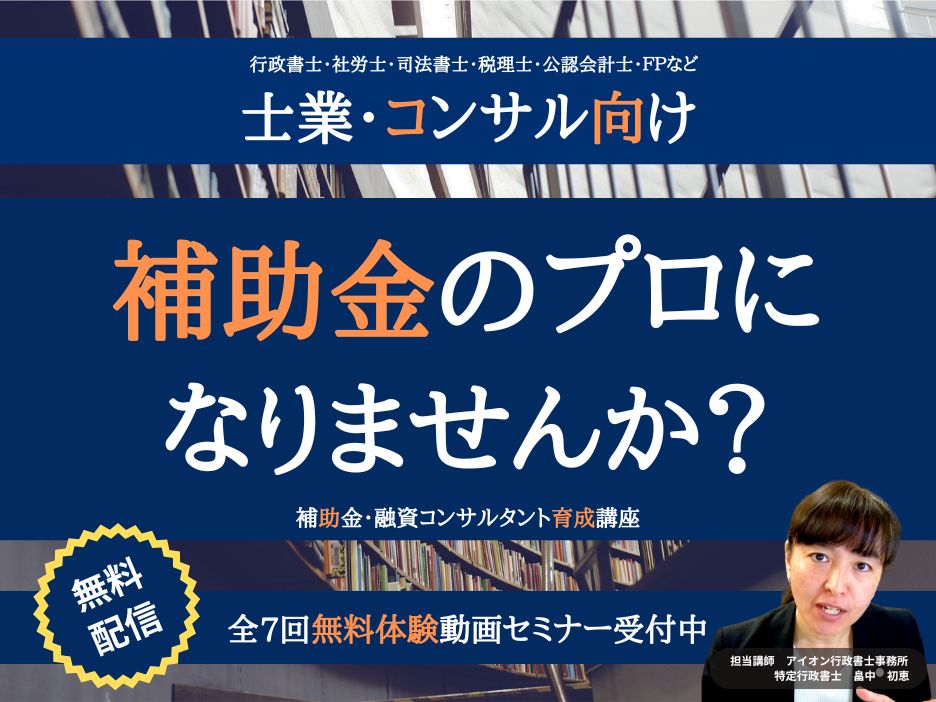
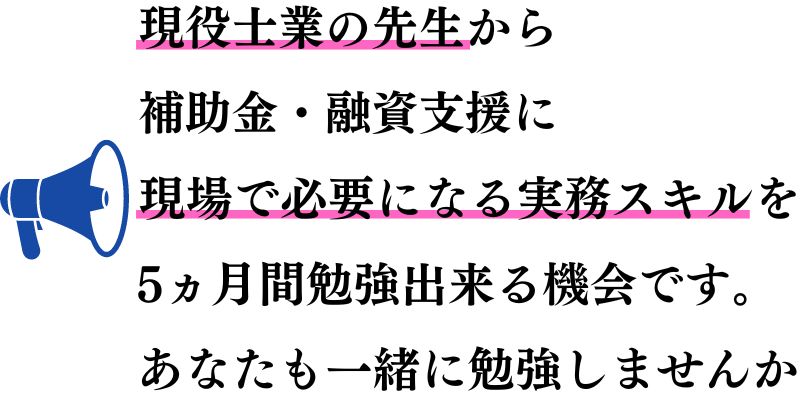

この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。

