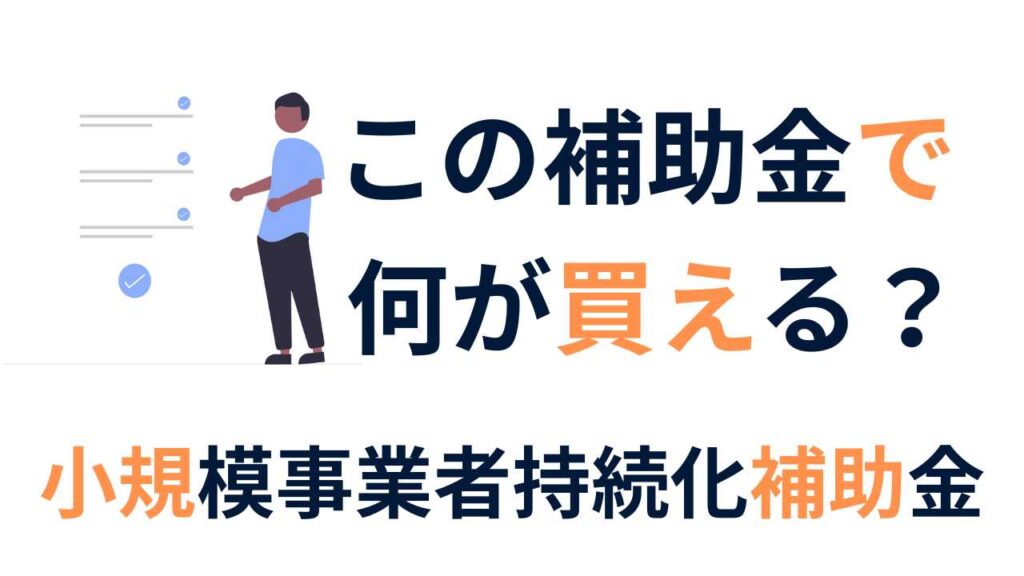小規模事業者持続化補助金で「何を購入できるか」を解説中
小規模事業者持続化補助金を聞いたことがあるけれど、実際にこの補助金を使って何が買えるのかよく分からない……そんな方、実は大変多いです。この補助金は、販路開拓や業務効率化に役立つ設備やツールへの投資を後押ししてくれる制度。たとえば、商品の鮮度を保つ冷凍庫や、会計と顧客管理を一元化するPOSレジ、アイデアを形にする3Dプリンター、魅力的なECサイト構築など、事業を次のステージに引き上げるアイテムが対象になります。
ただし申請のコツは「何を買って」「どう成果につなげるか」という計画をしっかり立てること。初心者の方もぜひこの補助金を活用して、自分の事業にぴったりの投資を実現してください!
この記事ではまず、補助対象事業と補助対象経費のルールをざっくり確認。その後、実際に購入できる8つのジャンル(機械装置・広報・Web関連・展示会出展……など)を具体例と注意点つきで深掘りします。初心者の方にもわかりやすくまとめたので、このガイドを参考に、ぜひ積極的に補助金を活用してください。
1.補助対象事業のポイント
このセクションでは、小規模事業者持続化補助金の「補助対象事業」として認められるために必要な3つの絶対条件をわかりやすく解説します。経営計画との整合性、商工会・商工会議所のサポート、そして事業完了までのスケジュール管理──いずれも採択を左右する大切な要素です。補助金を活用して機械やサービスを購入する際、これから説明する内容を網羅していることが採択される為の絶対条件となりますので、一度目を通して下さい。
1.1 絶対条件A:策定した経営計画に基づく取組
補助対象事業とは、自社があらかじめ策定した経営計画に沿って実施する「販路開拓」や「生産性向上」のための施策のみを指します。ただ単に機械や備品を買うのではなく、計画書の中で「いつ、どんな投資を行い、どのように売上げアップやコスト削減につなげるか」を具体的に示すことが求められます。購入後の効果を数字や根拠とともに説明できなければ、補助対象事業とは認められません。
当社からのアドバイス:
▶小規模事業者持続化補助金は「販路開拓」を支援する補助金です。
小規模事業者持続化補助金は販路開拓を後押しするための制度です。初めて利用される方の中には「この機械がほしい」と要望だけを掲げて申請されるケースがありますが、補助金は行政の「地域活性化」「産業振興」といった政策目的を実現するためのものです。
そのため、申請時には「自社がこんな投資を通じて、行政が求める○○という目的を達成します」という視点で計画を組み立てましょう。たとえば「この機械を導入し、販促活動を行うことで新市場を開拓するので補助金をお願いします」と示すのが、販路開拓支援を目的とする本補助金では最も効果的なアプローチです。
初心者の方も、この視点でぜひチャレンジしてみてください!
1.2 絶対条件B:商工会・商工会議所の支援
申請から事業完了までの間、必ず地元の商工会または商工会議所の支援を受けることが条件です。補助金申請の前には事前相談を行い、その記録を残すとともに、完成した経営計画書には担当者の押印や推薦文をもらいましょう。こうしたサポート証明があることで、本当に地域の事業者として認められ、審査で高い信頼を得られます。
当社からのアドバイス:
▶ 商工会・商工会議所の支援体制には地域差があります
持続化補助金の申請では、必ず地元の商工会または商工会議所で計画書のチェックを受ける必要があります。ここで受けられるアドバイスの質や申請後のフォロー体制、サポートの熱意は、地域によって大きく異なります。当社がヒアリングした限りでは、有料会員でなくても熱心に無償支援してくれるところは少数派という印象です。申請前には、あなたの地域でどんな支援が期待できるかをあらかじめ確認しておきましょう。
1.3 絶対条件C:期間内に完了
交付決定を受けた後は、概ね7か月の補助事業期間内にすべてを終えなければなりません。具体的には、設備の購入・導入工事から始まり、その後の効果検証と報告書作成まで。一つでも予定がずれ込んだり、報告が未完了のまま期限を過ぎたりすると、補助対象から外れてしまいます。スケジュール管理は余裕をもって計画し、適時進捗を確認することが大切です。
当社からのアドバイス:
▶ 採択を受けた補助額全額を獲得する為にスケジュール管理は重要です
交付決定後は、獲得した補助額を全て受け取るためにスケジュール管理が何より大切です。持続化補助金をはじめ多くの補助金は、決められた期間内に「実施証明書類の提出」や「機器・サービス代金の支払い」を完了しないと対象外になってしまいます。たとえば、Google広告の費用を銀行振込で支払えずクレジットカード決済を選ぶと、支払い完了とみなされるのは実際のクレジットカード代金引き落とし日です。請求から引き落としまで約1.5ヶ月以上かかることもあるため、この期間までを見越して逆算し、余裕をもって計画を立てましょう。細かな日程調整を忘れずに行うことが、補助金を無駄なく使い切るコツです。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
2. 補助対象経費の全体像
このセクションでは、小規模事業者持続化補助金で認められる経費を8つのジャンルに分けて詳しく解説します。設備投資から広告宣伝、ウェブ強化、外部委託まで幅広い支出が対象となりますが、一つひとつに申請時の注意点や適用条件がありますので、しっかり押さえておきましょう。
2.1 機械装置等費のポイント
機械装置等費は、「販路開拓」や「業務効率化」といった補助事業を進めるうえで欠かせない機械・装置・ソフトウェアの購入費用を指します。ただし、単に古くなった機械を取り換えるだけの更新費用や日常的なメンテナンス費用は対象外です。新たな仕組みを導入し、導入後に売上向上やコスト削減といった成果が見込めるかを計画書で明確に示すことが大切です。
2.1.1 処分制限財産の取り扱い
購入単価が50万円(税抜)以上の機械装置は、補助事業終了後も一定期間「処分制限財産」として扱われます。補助金を受け取った後に売却、譲渡、廃棄、担保提供などを行う際は、事前に補助金事務局の承認が必要です。承認を得ずに処分すると補助金の取消しや返還命令の対象となるため、要件を十分に確認してください。また、100万円(税込)を超える大きな設備を購入する場合は、価格の妥当性を示すために2社以上から見積書を取り、申請時に提出する必要があります。
2.1.2 中古機器の活用ルール
コストを抑えたい場合、中古機器の購入も可能ですが、以下の条件を満たすことが前提です。まず、購入価格が税抜50万円未満であること。個人やオークションからの調達は認められず、必ず中古品販売業者から同一機種の見積書を2社以上取得してください。見積書は交付決定前から実績報告書の提出まで一貫して保管し、随意契約での購入は一切認められません。購入後に故障した場合や使用できなかった場合は補助対象外となるため、購入前の状態確認を徹底しましょう。
2.1.3 具体的な対象・非対象機器例
たとえば、業務用オーブンや冷凍冷蔵庫、3Dプリンター、自走式作業機械(ブルドーザー、パワーショベルなど)は補助対象となる代表的な機械装置です。一方で、パソコン本体やタブレット、事務用プリンター、家庭用エアコンなど、事業以外にも使える汎用性の高い製品は補助対象外となります。また、既存設備の単なる入れ替えや廃棄費用、船舶・動植物といった特殊品も同様に対象外です。導入機器が対象か迷った際は、事前に商工会議所等へ相談することをおすすめします。
当社からのアドバイス:
▶中古機器購入には注意が必要です
補助金を有効活用するために中古機器を選ぶケースはありますが、事務局は価格の妥当性を厳しくチェックしたがります。申請時には同機種で最低2社から相見積を取り、最安値で購入したことを証明する書類が必須です。しかし、中古品は機能や状態がそれぞれ異なる場合もあり相見積が難しい事が多く、審査で認められないこともあります。ですから、中古機器購入の場合は、特に見積取得や調達先選びを早めに進めておきましょう。
2.2 広報費のポイント
広報費は、販路開拓を目的とした商品・サービスの宣伝活動に使う費用です。ここでは、何が対象となり、何を別枠で申請するのか、そして具体的な対象・非対象例を詳しく見ていきましょう。
2.2.1 対象となる広報活動
広報費には、チラシやパンフレットのデザイン・印刷費用、新聞・雑誌広告の掲載料、郵送DMの発送費用などが含まれます。ただし、販路拡大に直結する宣伝文句や商品・サービス名が必ず明記されていることが条件です。逆に、社名だけが載った企業PR用の看板や会社案内パンフレット、求人広告のように営業活動全般に使うものは補助対象外となります。
2.2.2 ウェブや動画制作費の切り分け
ウェブサイトの新規構築や動画コンテンツの制作費用は「ウェブサイト関連費」枠で申請します。一方、街頭ビジョン広告やデジタルサイネージの掲載料は広報費に含まれますので、映像や動画を使った屋外広告を行う場合は、素材制作費と掲載費をそれぞれ申請枠に分けて見積もりを用意しましょう。
2.2.3 具体的な対象・非対象経費
対象となるのは、チラシやカタログの外注・発送費用、看板の制作・設置費用、販促品や試供品の提供コスト(宣伝文句入りに限る)などです。これに対し、宣伝文句のない配布物、名刺や文房具、金券・商品券、配布予定がない未使用のチラシ、補助事業期間外の広告掲載分などは補助対象外です。申請前に見積書や請求書を整理し、対象経費かどうかをしっかり確認してください。
当社からのアドバイス:
▶ウエブサイト関連費か広報費かを注意
広報用に作成する動画コンテンツの制作費用は「ウエブサイト関連費」で処理します。ウエブサイト関連費に該当するか不明な場合は補助金事務局へ直接電話で問い合わせましょう。
2.3 ウェブサイト関連費
ウェブサイト関連費は、販路開拓や業務効率化を目的に、自社サイトやECサイト、顧客管理システムなどの開発・構築・更新・改修・運用にかかる経費を指します。ただし、ウェブサイト関連費だけで単独申請はできず、必ず他の経費と組み合わせる必要があります。また、交付申請総額の1/4以内(上限50万円)までがこの枠の上限です。
2.3.1 長期契約と按分計算
ソフトウェア使用権やホスティング契約が補助事業期間を超える場合は、補助期間中に対応する部分のみを費用とみなします。たとえば、12か月契約のうち補助事業期間が7か月であれば、7/12を按分して申請してください。
2.3.2 処分制限財産としての取り扱い
50万円(税抜)以上で制作・更新したウェブサイトは機械装置等と同様に「処分制限財産」となり、取得から通常5年間は目的外使用や譲渡などが制限されます。補助金事務局の承認を得ずに処分すると補助金取消や返還を命じられるケースがあるため、要注意です。ただし、機能強化や改良のためのアップデートは処分にはあたらず、事前承認は不要です。
2.3.3 対象経費と非対象経費
対象となるのは、商品販売用サイトの新規構築・スマホ対応化、ECモール登録作業、SEO対策ツール導入、SNS広告運用代行費などです。反対に、単なる会社紹介サイト、既存ソフトの更新料、外部コンサルティング費、有料教材制作、電子書籍発行などは補助対象外となります。サイトの目的と費用の使途が事業計画に明確につながっているかを、見積書や仕様書でしっかり示しましょう。
当社からのアドバイス:
▶補助上限50万円又は1/4ルールを理解しましょう
ウェブサイト関連費だけで単独申請はできず、必ず他の経費と組み合わせる必要があります。また、交付申請総額の1/4以内(上限50万円)までがこの枠の上限です。このルールがある為、補助額全額をホームページ作成費用にあてるこは出来ません。小規模事業者持続化補助金でホームぺージ作成を検討している方はご注意下さい。
2.4 展示会等出展費(オンライン含む)のポイント
展示会等出展費は、新商品やサービスを展示会や商談会へ出展・参加するために必要な経費をまとめたものです。リアル会場だけでなく、オンライン展示会やWeb商談システム利用料も含まれます。
2.4.1 対象となる費用
まず、展示会の出展料やブース設営費用が補助対象です。加えて、展示物や資材を運ぶための運搬費(荷物の宅配費用など。ただしレンタカー代・ガソリン代・駐車場代は除く)、通訳料やパンフレット・サンプルの翻訳費用も認められます。自社主催イベントの会場借料は「借料費」、必要機器の購入は「機械装置等費」として別枠で申請してください。
2.4.2 海外展示会の注意点
海外展示会に出展する場合、外国語で作成された見積書や領収書を実績報告に提出するときは、その内容を日本語で要約した資料も添付しましょう。これにより、審査担当者が正確に費用の妥当性を確認できます。
2.4.3 補助対象外となるケース
以下の費用は補助対象外ですのでご注意下さい。
- 国など第三者から同じ出展費助成を受ける場合
- 交付決定日前に支払いが完了している出展料
- 販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらない展示会
- 補助事業期間外の展示会出展費用
- 審査会や選考会への参加費用(賞の申込費など)
- 文房具など消耗品、飲食を伴う商談会参加費 など
2.5 旅費のポイント
旅費は、補助事業計画に基づいて販路開拓や展示会・商談会への参加に必要な出張費用だけが認められます。申請の際には、出張の目的・行き先・日程を明記した出張報告書を作成し、補助事業計画に記載のない出張は経費に含めないよう注意してください。
旅費の算定は国の旅費支給基準をベースに行います。交通費は公共交通機関を使った最も経済的かつ合理的なルートで実費を計算し、宿泊費も販売拡大に直接必要な分のみが対象です。朝食付きプランや温泉付きプランの付帯費用相当分、グリーン車やビジネスクラスへのアップグレード分は補助対象外となります。
海外出張時に外国語の領収書や請求書を実績報告で提出する場合は、その内容を日本語で要約した資料を必ず添付してください。翻訳を業者に依頼した費用自体は旅費に含まれませんのでご注意を。さらに、補助対象となるのは事業遂行に必要な最少人数のみです。複数名での参加を計画する場合は、必要性や妥当性を説明できる資料を用意し、事務局の確認に備えましょう。
具体例としては、販路開拓の展示会会場往復の新幹線指定席や航空券(エコノミークラス相当)、現地宿泊費が対象です。一方、ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代、旅費基準を超える支出、日当、パスポート取得料は対象外です。また、視察やセミナー参加のための旅費、補助事業期間外の出張、他の国の助成制度で支援を受けた分も補助対象外となる点にご注意下さい。
2.6 新商品開発費のポイント
新商品開発費は、補助事業計画に基づき新商品の試作品や包装パッケージを作る際に必要となる原材料費、設計・デザイン費、加工・製造費などが対象です。購入する原材料はサンプル用として必要最小限に抑え、補助事業終了時点で使い切ることが前提となります。完成品を大量に製造するための原材料や、デザイン改良を伴わない既存パッケージの印刷費は対象外なので注意しましょう。
原材料費を補助対象として申請する場合は、受払簿(任意様式)を用意し、材料の購入日・数量・単価・使用量を記録しておく必要があります。この帳簿は、実績報告書提出時に材料の使用状況を証明する大切な証憑資料となります。
◇ 対象となる経費例
– 新製品の試作に必要な生地や部品の購入費
– 新パッケージのデザイン外注費・試作加工費
◇ 対象とならない経費例
– 開発後の商品を包装・販売するための材料費
– デザイン改良を伴わない既存パッケージの印刷・購入費
– 文房具や一般的な消耗品費
– ウェブシステム開発費(③ウェブサイト関連費で申請)
試作段階のコストだからこそ、使途と数量の管理が成否を分けます。受払簿は申請前から準備し、実績報告までしっかり保管してください。
2.7 借料のポイント
借料は、補助事業の遂行に直接必要な機器や設備をリース・レンタルする際の費用を指します。たとえば、短期間だけプロ仕様の機材を借りて販促イベントを行ったり、成長拠点として新たに事務所スペースを賃借したりする場合に活用できます。申請時には、採択発表後から交付決定までの間に見積書を取得し、本事業に対応する費用であることを明示してください。
契約期間が補助事業期間を超える場合は、補助事業期間分の費用だけを按分算出し、実績報告時に契約書とともに提出します。逆に、通常の生産活動や補助事業以外で使う機材・スペースの賃料は補助対象外です。
なお、既存の事務所家賃は原則対象外ですが、新たに販路開拓の拠点として借りる場合は、床面積に応じた按分資料を添付すれば認められる可能性があります。また、展示会やPRイベント会場のレンタル料も、借料枠で申請できます。事前に計画書で使用目的と期間を明確にし、見積書・契約書の整理を忘れずに行いましょう。
2.8 委託・外注費のポイント
委託・外注費は、補助事業を進めるうえで自社だけでは対応が難しい専門的な業務を第三者に依頼する際の費用です。申請時には、委託内容・成果物・金額を明記した契約書を必ず用意し、成果物や工事完了証明を実績報告で提出できるように準備しましょう。
2.8.1 対象となるケース
店舗改装やバリアフリー化工事、製造ライン向けのガス・水道・排気設備工事など、専門業者でなければ実行が難しい工事が代表例です。ほかにも移動販売車の内装改造、従業員動線改善のための作業スペース改装、新たに借りた宿泊事業者用スペースの改装など、「補助事業計画」の生産性向上・販路開拓に直結する工事が該当します。
住宅宿泊事業者が改装を行う場合は、事業に使用する部分だけを面積按分し、採択後から交付決定までに平面図等を提出する必要があります。
2.8.2 抑えておきたい注意点
- 自社の通常業務は対象外
たとえば普段からデザインを手掛けている業者がロゴや販促素材を作る場合、補助対象にはなりません。 - 成果物の帰属を明示
契約書には「作成物の権利は発注者(補助事業者)に帰属する」ことを必ず記載しましょう。 - 再委託の禁止
一度委託した業務をさらに別の業者に丸ごと任せる形態は補助対象外です。 - 処分制限財産の取扱い
50万円(税抜)以上の外注工事を行った場合は、完成部分が「処分制限財産」となり、補助事業終了後も一定期間、譲渡・廃棄などが制限されます。 - 補助対象外となる主な費用
・申請書や報告書の作成・送付にかかる手数料
・販路拡大や効率化と結びつかない改装(単なる移転工事など)
・不動産取得に該当する増築・大規模設置工事
以上を踏まえ、必要な工事や改装を精査し、漏れなく契約書類を整えて申請してください。初心者の方も、専門業者との連携次第で効率的に補助金を活用できます。
当社からのアドバイス:
▶これは不動産の取得にあたり対象外なの?
申請予定者の方から何度か頂いたご質問に、建物の増築や物置を購入したいが小規模事業者持続化補助金の対象となるかというものがありました。
こちらに関しては、下記の考え方を参考にご検討下さい。
▶不動産の取得に該当する工事の要件
店舗の増築や物置など「小規模な建物」を新たに設置する場合、次の3つの要件をすべて満たすと「不動産の取得」とみなされ、補助対象外となります。固定資産税の課税対象である「家屋」の判定基準を準用するイメージですので、設計段階から要件該当の有無をよく確認しましょう。
1)外気遮断性
屋根と三方向以上の壁またはそれに類する構造を備え、独立して風雨をしのげること。
※柱と屋根だけのテラス席や、周囲に壁のないカーポートはこの要件を満たさず、家屋には該当しません。
2)土地への定着性
基礎などで物理的に地面に固定されていること。
※コンクリートブロック上に置かれただけの簡易物置等は、土地への定着性がないため家屋に該当しません。
3)用途性
建造物としての居住・作業・貯蔵等の利用空間が明確に形成され、本来の用途に供しうること。
※物置の内部が棚だけでなく、人や物が出入りして利用できる状態であれば、この要件に当てはまります。
上記3要件すべてをクリアする工事は「不動産取得」に該当し、補助対象外となるのでご注意ください。疑問がある場合は、早めに補助金事務局などへ相談し、事前確認を行うのがおすすめです。
2.9 最後にこちらのポイントも確認しましょう
これまでご説明しました8ジャンルのいずれも、以下の3つの共通条件をすべて満たす必要があります。
1)支出の目的が補助事業の遂行に必要なものとして明確に特定できる
2)交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了している
3)領収書や請求書などの証憑資料によって支払金額が確認できる
これらのポイントを押さえて、効率的かつ確実に補助対象経費を組み込みましょう。
3. まとめ
この記事では、小規模事業者持続化補助金が実際に「何を買えるか」に絞って解説しました。事業計画と連動させる機械装置から、チラシ・Webサイト、展示会出展、旅費、試作開発、借料、外注費まで、8つのカテゴリーで具体例と注意点をお伝えいたしました。
補助対象事業としては、策定した経営計画に基づき販路開拓や生産性向上を目指し、決められた期間内に補助事業を完了することが大前提です。これをクリアすると、初期投資を大幅に抑えつつ、事業の“次の一歩”を踏み出せます。
各経費には「支出目的の特定」「交付決定後の支払い完了」「領収書など証憑の保管」という共通ルールがあります。とくに中古機器の相見積や処分制限、長期契約の按分といった細かい要件は、事前に確認を。契約書・見積書・領収書をしっかりそろえ、事務局とのやりとりも余裕をもって進めましょう。
小規模事業者持続化補助金の全体の流れについてはこちらの記事でご確認下さい。
▶記事タイトル:小規模事業者持続化補助金のスケジュール完全ガイド|申請から補助金受け取りまでの流れをわかりやすく解説
→ https://hojyokin-hiroba.com/hojyokin-small-business-schedule/
初心者の方にも、この補助金は大きなチャンスです。あなたのアイデアを形にして、販路開拓と業務効率化を一気に実現してください!
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。