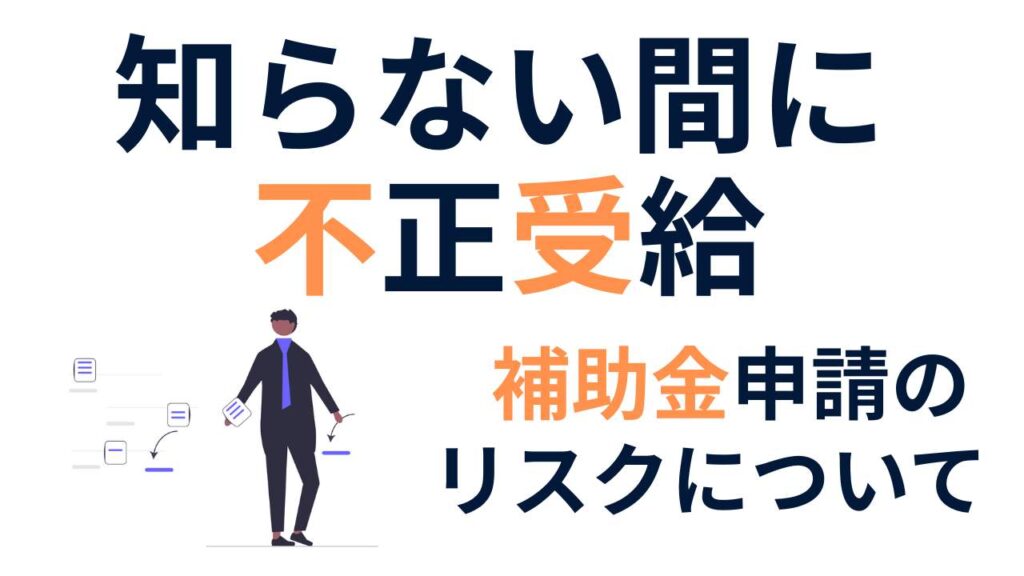🎯補助金の基本から不正受給の具体例・防止策などをわかりやすく解説
補助金は、事業の成長や新たな挑戦を後押ししてくれる非常に心強い制度です。しかしその一方で、制度の仕組みやルールを正しく理解していないと、知らず知らずのうちに「不正受給」とみなされてしまうリスクもあります。
この記事では、補助金の基本から不正受給の具体例、そして防止策までをわかりやすく解説します。補助金を安心して活用するための“完全ガイド”として、ぜひ最後までご覧ください。
この記事のお読み頂きたい方
- 補助金の申請を検討している中小企業経営者・個人事業主の方
- 補助金申請支援を行う行政書士・中小企業診断士・コンサルタントの方
- 「知らずに不正受給してしまうのでは」と不安を感じている方
- 補助金制度を正しく理解し、安心して活用したいすべての事業者の方
📑目次
- 補助金とは?制度の基本と目的を理解しよう
- 補助金の審査プロセスとチェックポイント
- 不正受給とは?定義とよくある事例
- 【悪意あり】意図的な不正受給の手口とは
- 【悪意なし】知らずに不正受給してしまうケース
- 不正受給が発覚した場合のリスクと罰則
- 実際にあった摘発事例とその教訓
- 不正受給を防ぐための3つの鉄則
- 補助金申請で迷ったら専門家に相談を
- まとめ:補助金は正しく使えば強力な味方
1. 補助金とは?制度の基本と目的を理解しよう
補助金とは、国や地方自治体が特定の政策目的を達成するために、民間企業や個人事業主に対して交付する「返済不要の資金」です。融資とは異なり、返済義務がないため、資金に余裕のない中小企業やスタートアップにとっては非常に魅力的な制度です。
🎯補助金の目的とは?
補助金の目的は、行政が掲げる政策目標を民間の力で実現することにあります。
たとえば:
- 地球温暖化対策の一環として、再生可能エネルギーの導入を促進する
- 地方創生を目的に、地域の観光資源を活用した事業を支援する
- 中小企業のIT化・DX推進を後押しする
つまり、補助金は「行政の政策を民間が実行するための資金的サポート」と言えます。
当社よりのアドバイス
上記の通り補助金は「行政が政策を実現する為の手段」ですから、行政が求める企業活動を実施しないと見なされる申請は不採択となります。
※よくある勘違い:補助金は資金に困っている事業者を支援する制度ではありませんのでご注意下さい。
💰補助金の財源はどこから?
補助金の原資は、私たちが納めている税金です。そのため、補助金の使い道や事業の進捗状況は、非常に厳しくチェックされます。
「もらったら終わり」ではなく、「適切に使い、報告する責任」が伴う制度なのです。
2. 補助金の審査プロセスとチェックポイント
補助金は、申請すれば誰でももらえるわけではありません。審査は大きく2段階に分かれています。
✅ステップ1:採択前審査
- 提出された申請者の概要や事業計画書をもとに、政策目的との整合性や実現可能性を審査
- 申請者が多い場合は、より効果が高いと判断された計画が優先される
- 申請者が少ない場合でも、基準に満たない計画は不採択になることも
✅ステップ2:採択後審査
- 採択された後も、事業の進捗や経費の使い方が厳しくチェックされる
- 補助対象期間外の支出や、申請内容と異なる使い方はNG
- 補助期間終了後には、実績報告書や証憑書類の提出が求められる
このように、補助金は「申請時」だけでなく「実施中」「終了後」まで一貫して審査される制度です。
3. 不正受給とは?定義とよくある事例
補助金の「不正受給」とは、虚偽の申請や不適切な経費処理などにより、本来受け取るべきでない補助金を受け取る行為を指します。
❌不正受給の定義(法律上)
「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた者は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方に処する」
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第29条)
🔍よくある不正受給の例
- 経費の水増し(実際より高額な請求書を提出)
- 架空の取引(実態のない業務委託や納品)
- 事業期間外の支出を日付改ざんでカバー
- 申請内容と異なる使途への無断変更
これらはすべて「不正受給」とみなされ、重大なペナルティの対象となります。
4. 【悪意あり】意図的な不正受給の手口とは
補助金の不正受給には、「悪意を持って意図的に行われるケース」が存在します。これは明確な違法行為であり、発覚すれば重い罰則が科されます。
💣代表的な悪意ある不正受給の手口
① 経費の水増し請求
- 実際には100万円の支出しかないにもかかわらず、取引先に150万円の請求書を発行させる
- 差額の50万円を裏でキックバックとして受け取る
これは典型的な「水増し請求型」の不正で、補助金制度を悪用した詐欺行為に該当します。
② 架空取引の計上
- 実際には存在しない業務委託や納品を装い、架空の請求書を作成
- 形式上の支出を装って補助金を受給
このようなケースでは、帳簿や証憑書類の整合性を精査されることで発覚することが多く、内部告発によって明るみに出ることもあります。
③ 書類の改ざん
- 実施期間外の支出に対して、請求書や領収書の日付を改ざん
- 補助対象期間内に見せかけて申請
補助金は「対象期間」が明確に定められており、その期間外の支出は原則として対象外です。日付の改ざんは明確な不正行為です。
5. 【悪意なし】知らずに不正受給してしまうケース
補助金の不正受給には、悪意がなくても「結果的に不正とみなされる」ケースがあります。これは特に補助金初心者に多く見られるパターンです。
⚠️よくある「悪意なき不正」の例
① 申請内容と異なる使途への変更
- 申請時:「チラシを印刷して駅前で配布する」
- 実際:「チラシ配布が効果的でなかったため、看板を設置することに変更」
このような変更は、たとえ広告宣伝費の範囲内であっても、事前に補助金事務局へ相談・承認を得ていない場合、不正受給と判断される可能性が高いです。なお、補助事業実施報告の際、上記のような変更が確認された場合は、この支出について補助金対象外=不支給となる可能性が高いです。
② 経費区分の誤認
- 「備品購入費」として申請したが、実際には「消耗品費」に該当する支出だった。
※経費の分類ミスにより、補助対象外とされることも
③ 事業計画の未達成
- 補助金を受けて事業を開始したが、途中で中止・縮小した
- 実績報告書に記載された成果が、申請時の計画と大きく乖離していた
このような場合も、補助金の一部返還や不支給の対象となることがあります。
💡ポイント
「同じ費目だから大丈夫だろう」「少しの変更なら報告しなくてもいいだろう」といった判断は非常に危険です。
少しでも不安がある場合は、必ず補助金事務局や専門家に相談しましょう。
6. 不正受給が発覚した場合のリスクと罰則
補助金の不正受給が発覚した場合、事業者には非常に重いペナルティが科されます。金銭的損失だけでなく、社会的信用の失墜にもつながります。
🔻主なリスクと罰則
| リスク内容 | 詳細 |
|---|---|
| 補助金の返還 | 受給した全額を返還する義務が生じます |
| 加算金の支払い | 年利10.95%の加算金が請求されることもあります |
| 企業名の公表 | 行政機関のHP等で「不正受給企業」として公表されます |
| 刑事告訴 | 悪質な場合は詐欺罪などで刑事告訴される可能性があります |
| 銀行融資の停止 | 信用情報に傷がつき、金融機関からの融資が停止されることも |
⚖️法的根拠
「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた者は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方に処する」
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第29条)
7. 実際にあった摘発事例とその教訓
📌IT導入補助金で発覚した1.5億円の不正受給(2024年 会計検査院)
- 調査対象:2020〜2022年度の補助金受給企業9万9908社のうち、376社・445案件を抽出
- 不正認定:30社・41案件で不正受給が確認
- 不正受給額:総額1億4755万円
- 不正率:抽出案件の約8%が不正と判定
🧾摘発された具体的な手口
事例:実質無料をうたう営業トークによる不正還流
- 企業名:製造業A社(仮名)
- 申請内容:ITツール導入費用として1500万円を申請し、920万円の補助金を受給
- 実態:ベンダーが「顧客紹介料」「コンサル料返金」などの名目でA社に1100万円を還元
- 結果:A社は自己負担ゼロどころか、180万円の利益を得る構図に
- 発覚経緯:内部告発と関連案件の調査により摘発
⚠️教訓
- 「実質無料」「自己負担ゼロ」などの営業トークには要注意
- 書類が整っていても、資金の流れが不自然であれば不正と判断される
- ベンダー任せにせず、契約内容や資金の流れを自社で把握することが重要
弊社の補助金担当が同業者から聞いたところでは、コロナ禍前後から事業再構築補助金などの高額な補助金において、自社の商品やサービスを販売する目的で、販売先の事業者の名前で虚偽の補助金申請支援を行う不正事業者が複数存在したようで、その結果、意図せず「知らないうちに不正受給者」となってしまった補助金申請事業者も実際に数多くいらっしゃったようです。
こうした事態を受け、現在、多くの補助金制度では審査手続きの中に「社長面談」が設けられるようになりました。この面談では、申請者本人である社長自らが申請内容について説明を行い、事業計画に対する理解度が確認されます。これにより、現在では申請者が知らないうちに不正受給に巻き込まれることを防ぐ仕組みが強化されています。
8. 不正受給を防ぐための3つの鉄則
補助金を安心して活用するためには、「知らなかった」では済まされないルールと責任を理解し、適切に対応することが重要です。ここでは、不正受給を未然に防ぐための3つの鉄則をご紹介します。
✅鉄則①:事実と異なる内容を申請書に書かない
- 申請書や事業計画書には、実際に行う予定の内容を正確に記載しましょう。
- 「とりあえず通ればいい」という考えで虚偽の内容を記載すると、後々の報告や実績との整合性が取れず、不正とみなされるリスクがあります。
✅鉄則②:偽装・偽造は絶対にしない
- 領収書や請求書の日付改ざん、架空の取引、経費の水増しなどは明確な不正行為です。
- たとえ「バレないだろう」と思っても、補助金の審査は非常に厳しく、後日発覚する可能性が高いです。
✅鉄則③:変更があれば必ず事務局に相談する
- 事業の途中で内容や経費の使い方に変更が生じた場合は、必ず補助金事務局に相談しましょう。
- 事前に承認を得ていれば、柔軟に対応してもらえるケースも多くあります。
- 自己判断で変更を行うと、結果的に不正受給とみなされることがあります。
9. 補助金申請で迷ったら専門家に相談を
補助金制度は非常に多岐にわたり、制度ごとにルールや審査基準も異なります。
「これって大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、補助金事務局や専門家に相談するのが最も確実です。
🧑💼相談先の例
- 士業や経営コンサルタントなどの補助金支援専門家
- 地方自治体の補助金窓口
- 商工会議所や中小企業支援センター
- 認定支援機関など経済産業省や中小企業庁が認める支援事業者
💡専門家に相談するメリット
- 制度の最新情報を把握している
- 書類作成や申請手続きのサポートが受けられる
- 不正受給リスクを未然に防ぐアドバイスがもらえる
補助金は「正しく使えば強力な味方」です。だからこそ、制度を正しく理解し、安心して活用するためのパートナーを持つことが大切です。
10. まとめ:補助金は正しく使えば強力な味方
補助金は、事業の成長や新たな挑戦を後押ししてくれる非常に有効な制度です。しかしその一方で、制度のルールを理解せずに申請・活用してしまうと、知らず知らずのうちに「不正受給」とみなされ、大きなリスクを背負うことになります。
✅この記事のまとめ
- 補助金は「返済不要」だが「自由に使えるお金」ではない
- 不正受給には悪意のあるものと、悪意のないものがある
- 発覚すれば返還・加算金・公表・刑事告訴などの重大なリスクがある
- 少しでも不安があれば、必ず事務局や専門家に相談すること
補助金は、正しく使えばあなたのビジネスを大きく飛躍させる「追い風」になります。
制度を正しく理解し、安心して活用していきましょう。
📞トラブルに巻き込まれていると感じたら
補助金申請に関連して「不正な申請に巻き込まれているかもしれない」と感じた場合は、以下のような対応をおすすめします。
- 補助金の事務局に速やかに相談する
- 最寄りの警察署に相談する
- 弁護士など法律の専門家に相談する
※弊社および提携する士業や経営コンサルタントは、補助金申請支援の専門家ですが、犯罪行為に関する対応は行っておりません。法的な問題が疑われる場合は、必ず警察など専門機関にご相談ください。
この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。