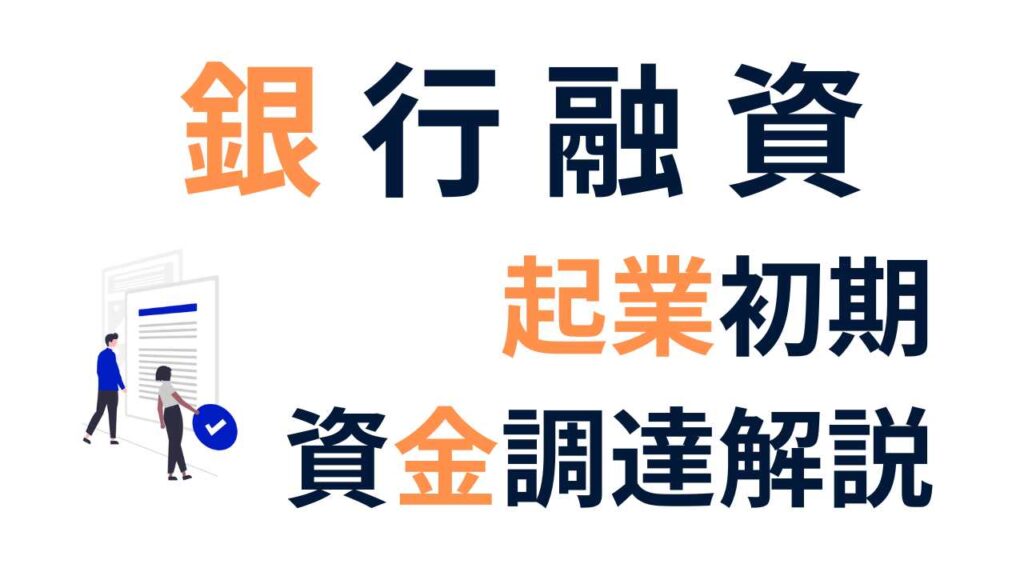起業と融資|なぜ創業段階で資金調達を考えるべきなのか?
起業に必要な準備は多岐にわたり、資金もそれに応じて膨らみがちです。特に法人設立や店舗開業、サービス提供のための設備導入など、初期の負担は大きくなりがちです。
自己資金でまかなうことができない場合、選択肢にあがるのが「補助金」と「融資」です。補助金は返済不要ですが、申請難易度が高く、採択されないリスクもあります。また申請から受給までの期間も長く、すぐに資金が必要な場面ではタイミングが合わないケースも。
そこで注目したいのが、創業初期でも利用できる「融資制度」です。審査があるものの、計画的に準備すれば通過も十分可能で、何より資金が手元に入るまでのスピード感があります。
融資は返済が必要な制度ですが、無担保や保証人不要で申請できる制度も多く、補助金と比べて柔軟性も高いため、多くの起業家が活用しています。
日本政策金融公庫の創業融資制度を活用しよう🏦
起業初期の資金調達において、最も信頼性が高く、かつ多くの起業家に利用されているのが「日本政策金融公庫(JFC)」の創業融資制度です。2025年現在の名称は「新規開業・スタートアップ支援資金」。是非有効活用したいものです。
この制度は、創業前後の事業者に対して、無担保・無保証で最大7,200万円までの融資を提供するもので、資金調達のハードルを大きく下げてくれる心強い制度です。
制度の概要と対象者
「新規開業・スタートアップ支援資金」は、以下のような方を対象にしています。
- 新たに事業を始める方
- 事業開始後おおむね7年以内の方
さらに、以下の条件に該当する方は、特別利率が適用され、通常よりも有利な条件で融資を受けることができます。
- 女性、若者(35歳未満)、シニア(55歳以上)の方
- 廃業歴があり、再チャレンジする方
- 中小会計を適用して創業する方
- 創業塾や創業セミナーを受講した方
- 地域おこし協力隊の任期終了後に創業する方
- 地方でUターン創業する方
- ベンチャーキャピタル等から出資を受けている方
- 起業支援金・移住支援金の交付決定を受けた方
- 技術・ノウハウに新規性がある事業を行う方
これらの条件に該当する場合、金利が優遇される「特別利率A・B・C」が適用される可能性があります。
当社からのアドバイス:
この融資制度は開業【後】にも利用できます。
以前は私自身勘違いをしていたのですが、この融資制度は事業開始後約7年以内の事業者も対象となる融資制度です。
運転資金や開業後新たに必要になった設備導入の費用なども対象になります。「新規開業・スタートアップ」との制度名称に惑わされず、必要な事業者様は是非ご活用下さい。
融資限度額と使途
- 融資限度額:最大7,200万円(うち運転資金は4,800万円まで)
- 資金使途:設備資金および運転資金
- 設備資金:店舗改装、機器購入など
- 運転資金:仕入れ、人件費、広告宣伝費など
特に「再チャレンジ型」の方は、前事業の債務返済にも運転資金を活用でき、返済期間も最大15年まで延長されます。
返済期間と据置期間
- 設備資金:最大20年(据置期間5年以内)
- 運転資金:最大10年(据置期間5年以内)
据置期間とは、元金の返済を開始するまでの猶予期間のことで、創業直後の資金繰りを安定させるために非常に有効です。
利率と特別利率の仕組み
基本的には「基準利率」が適用されますが、前述の条件に該当する方には「特別利率」が適用されます。
- 特別利率A:女性、若者、シニア、創業塾受講者など
- 特別利率B:過疎地域での創業、起業支援金の交付決定者など
- 特別利率C:技術・ノウハウに新規性がある事業者など
金利は融資の種類や返済期間、信用リスクによって異なりますが、特別利率が適用されることで、利息負担を大きく軽減できます。
担保・保証人について
この制度では、無担保・無保証人での融資が可能です。
ただし、申込者の希望や審査結果によっては、担保や保証人が必要になる場合もあります。事前に支店へ相談することで、柔軟な対応が可能です。
併用できる特例制度
以下のような特例制度と併用することで、さらに有利な条件で融資を受けることができます。
- 経営者保証免除特例制度
- 創業支援貸付利率特例制度
- 設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
- 賃上げ貸付利率特例制度
これらの制度は、事業の内容や地域、雇用状況などに応じて適用されるため、詳細は支店で確認するのが確実です。
審査と創業計画書の重要性
融資を受けるには、事業計画の内容が審査されます。
特に「創業計画書」は、事業の実現可能性や収益性、申込者の経験・スキルなどを示す重要な書類です。
審査では以下のようなポイントが見られます:
- 事業の具体性と市場性
- 自己資金の有無と使途
- 売上・利益の見通し
- 起業者の経歴とスキル
- 計画の実行力と継続性
創業計画書の作成に不安がある場合は、認定支援機関・税理士・行政書士・中小企業診断士・経営コンサルタント・商工会議所などに相談するのがおすすめです。
まとめ|創業融資制度は起業家の強力な味方
「新規開業・スタートアップ支援資金」は、起業家にとって非常に心強い制度です。
無担保・無保証で最大7,200万円までの融資が可能で、特別利率や長期返済などの優遇措置も充実しています。
制度の詳細は日本政策金融公庫の公式ページで確認できます。
👉 日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金
起業準備の段階から情報収集を始め、創業計画書の作成や支援機関との連携を通じて、確実な資金調達を目指しましょう。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
自治体や商工会議所の制度融資も見逃せない
日本政策金融公庫以外にも、都道府県や市町村が提供する「制度融資」も起業家にとって有力な選択肢です。
たとえば横浜市や東京都、大阪市などでは、創業者支援を目的とした特別融資制度が設けられており、民間金融機関での融資に「信用保証協会による保証」や「利子・保証料補助」などの支援がつくケースもあります。
また、商工会議所や商工会に相談することで、地域の制度融資を紹介してもらえるほか、創業計画書のブラッシュアップ支援や申請書類作成のサポートを受けられることもあります。
自治体の制度融資は、地域内に開業する事業者であることが条件となる場合が多いため、まずは所在地の自治体HPを確認するのがおすすめです。
自治体や商工会議所の制度融資は、公庫と併用できる場合もあるので、資金調達の選択肢を広げる意味でも積極的に調べておく価値があります。
具体例紹介:横浜市「創業おうえん資金」の活用法
先ほどよりご説明している通り起業初期の資金調達では、日本政策金融公庫の創業融資が広く知られていますが、自治体が提供する制度融資も非常に有力な選択肢です。例えば横浜市では、創業者向けに「創業おうえん資金」という独自の融資制度を展開しており、地元で起業を目指す方にとっては見逃せない支援策となっています。
この制度は、横浜市・取扱金融機関・横浜市信用保証協会の三者が連携して提供するもので、金利や保証料の助成、無担保・保証人不要の条件など、創業者にとって非常に優しい設計がされています。
具体例紹介:横浜市「創業おうえん資金」の概要
横浜市の創業支援融資は、以下の2つのタイプに分かれています。
① 創業おうえん資金(経営者保証有)
- 融資対象者:創業前または創業後5年未満の中小企業者
- 融資額:最大3,500万円
- 金利:固定金利2.3%以内
- 返済期間:最大10年(据置最大12ヶ月)
- 担保:原則不要
- 保証料率:助成後0.3%(横浜市が0.1%助成)
このタイプは、法人代表者の連帯保証が必要になる場合がありますが、条件を満たせば保証料の助成が受けられ、金利も低く設定されています。
② 創業おうえん資金(経営者保証不要特別)
- 融資対象者:創業前または創業後5年未満の中小企業者(自己資金1/10以上が必要)
- 融資額:最大3,500万円
- 金利:固定金利2.3%以内
- 返済期間:最大10年(据置最大12ヶ月〜36ヶ月)
- 担保・保証人:不要
- 保証料率:助成後0.5%(横浜市が0.1%助成)
当社からのアドバイス:
こちらは、保証人不要・担保不要で利用できるため、個人事業主やスタートアップ企業にとって非常に魅力的です。さらに、創業支援セミナーなどを受講して「特定創業支援等事業」の証明書を取得すれば、申込期限が延長されるなどの優遇措置もあります。
なお、特定創業支援等事業の対象になると
1)創業時の登録免許税が減免される
2)空き店舗開業助成事業の対象となる
3)小規模事業者持続化補助金の創業枠(補助上限額が通常の50万円から200万円の大幅UP)の対象となる
などのメリットもあります。
利用までの流れと必要書類
融資を受けるまでの流れは以下の通りです:
- 取扱金融機関に相談・申込み
- 金融機関が横浜市信用保証協会に保証依頼
- 保証協会が審査・保証決定
- 金融機関が融資を実行
必要書類には、創業計画書、印鑑証明書、納税証明書、決算書(創業後の場合)、設備資金の見積書などが含まれます。創業計画書は、横浜市信用保証協会の様式に沿って作成する必要があり、横浜企業経営支援財団で無料相談も可能です。
横浜市の制度融資を活用するメリット
- 地元密着型の支援で、相談しやすく審査も柔軟
- 保証料の助成により、実質負担が軽減される
- 無担保・保証人不要の選択肢があるため、創業者のリスクが低い
- 創業支援セミナーとの連携で、申込期限や条件が緩和される
- 取扱金融機関が豊富(横浜銀行、みずほ銀行、信用金庫など)
この制度は、横浜市内で起業を考えている方にとって、資金調達だけでなく事業計画のブラッシュアップや経営支援の面でも大きなメリットがあります。
横浜市「創業おうえん資金」のまとめ|自治体の制度融資は“地域密着型の安心サポート”
自治体や商工会議所が提供する制度融資は、単なる資金調達手段ではなく、地域での事業成功を支える伴走型支援です。横浜市の「創業おうえん資金」はその代表例であり、創業者が安心して第一歩を踏み出せるよう設計されています。
◆起業を検討している方は、まずは地元自治体の制度融資を調べてみることをおすすめします。
👉 横浜市|創業おうえん資金の公式ページはこちら
銀行融資は創業後の資金調達の柱に
民間の金融機関、特に都市銀行・地方銀行・信用金庫などからの融資も創業後には検討すべき資金調達手段です。
ただし、起業直後は実績がないため、銀行側は慎重な姿勢を示すことが多く、一定の条件や信用力がないと融資が難しいケースもあります。
銀行融資には、以下のような種類があります:
- 信用保証協会付き融資:保証協会が信用を補完することで融資を通しやすくする
- ノンバンクのビジネスローン:短期資金として使えるが金利は高め
- プロパー融資(保証なしの融資):信用力がないと実行は難しいが将来的には目指すべき形
銀行融資は公庫と比べると審査が厳しく時間もかかりますが、一度実績を作ると今後の追加融資や企業成長時の資金調達が格段にスムーズになります。
開業から半年~1年ほど経過し、売上や取引先が安定してきたタイミングで銀行融資を検討するのが一般的です。その際も創業計画書や月次試算表、資金繰り表などが必要になるため、開業直後から帳簿管理はしっかり行いましょう。
創業融資を成功させるための3つの準備ポイント
資金調達には「書類の準備」が何より重要です。とはいえ単に提出すれば通るものではなく、内容に「納得感」があるかが鍵を握ります。
1つ目は創業計画書の完成度です。審査官が理解しやすい構成と、現実的な収益見通しを組み立てているかをチェックされます。数字だけを並べるのではなく、収入の根拠や支出の裏付けをきちんと説明することが大切です。
2つ目は自己資金の証明と活用計画です。通帳の写しで資金を証明するだけでなく、その資金をどう使うか明記し、「事業に本気で取り組んでいる姿勢」を見せることが重要です。
3つ目は見積書や参考資料の提出です。設備投資費や開業時に必要なモノ・サービスの価格感があいまいだと審査に不安を抱かれることがあります。実在する見積書を添えて客観的な資料を揃えておきましょう。
融資申請は「書類審査がすべて」とも言われるほど、準備が勝負の分かれ目です。支援機関や専門家のアドバイスを受けながら、時間をかけて取り組む姿勢が成功につながります。
よくある疑問にお答えします(初心者向けFAQ)
Q:起業前でも融資を受けられるのですか?
A:はい、日本政策金融公庫の創業融資などは、法人設立前や個人事業開始前でも申請可能です。ただし、開業が確定している必要があり、事業の計画が明確であることが求められます。申請時期や提出書類は事前にチェックしましょう。
Q:フリーランスや士業でも融資は使えますか?
A:可能です。個人事業主でも融資制度を活用できます。ただし、事業の具体性や継続性をきちんと説明する必要があります。士業の場合は業務内容や収入見込が審査のポイントになります。
Q:保証人なしでも融資は通るのでしょうか?
A:はい。日本政策金融公庫の新創業融資制度は、無担保・保証人なしでも利用可能です。ただし、自己資金や事業計画の精度がより重視される傾向があります。信用力を補完する資料提出を心がけましょう。
Q:信用情報に不安がある場合はどうしたら?
A:信用情報の内容によりますが、過去の延滞などがある場合は正直に申告し、現在の経済状況が安定していることを示すことで審査官の理解を得られる場合があります。事前に信用情報を開示して確認しておくと安心です。
融資制度を使うと事業がどう変わるか
融資制度をうまく活用できれば、事業のスタートダッシュに大きな違いが生まれます。例えば、設備投資や広告宣伝に十分な予算を確保できることで、顧客獲得や売上成長のスピードが加速します。
また、手元資金に余裕があることで、焦りや不安が減り、じっくりと長期的な戦略を練ることができます。起業初期は不安定な時期だからこそ、資金面の支援が精神的にも大きな支えになるのです。
さらに、金融機関との関係を築くことができれば、今後の追加融資や新規事業展開時にも力強いサポートが得られるようになります。最初の一歩で信用を積むことが、次のステージを切り拓く鍵となるでしょう。
まとめ|融資制度は「知っているか」で差がつく起業支援の柱
起業は、夢やアイデアだけでなく「現実的な準備」がなければ継続できません。資金調達はその準備の中でも最も重要な要素であり、融資制度は初心者にとって非常に頼れる選択肢です。
特に日本政策金融公庫の創業融資は、審査こそあるものの、丁寧に準備すれば十分に通過可能です。自治体や商工会議所の制度も合わせて活用すれば、より有利な条件で資金を調達することができます。
まずは自分がどの制度を使えるかを知り、必要な書類や計画書を整えること。支援機関のアドバイスを受けながら進めることで、安心して融資に挑戦できます。
資金が調達できれば、あなたの事業は「スタートする」だけでなく「成功へと加速する」準備が整います。ぜひ、この記事をきっかけに一歩踏み出してみてください。
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。