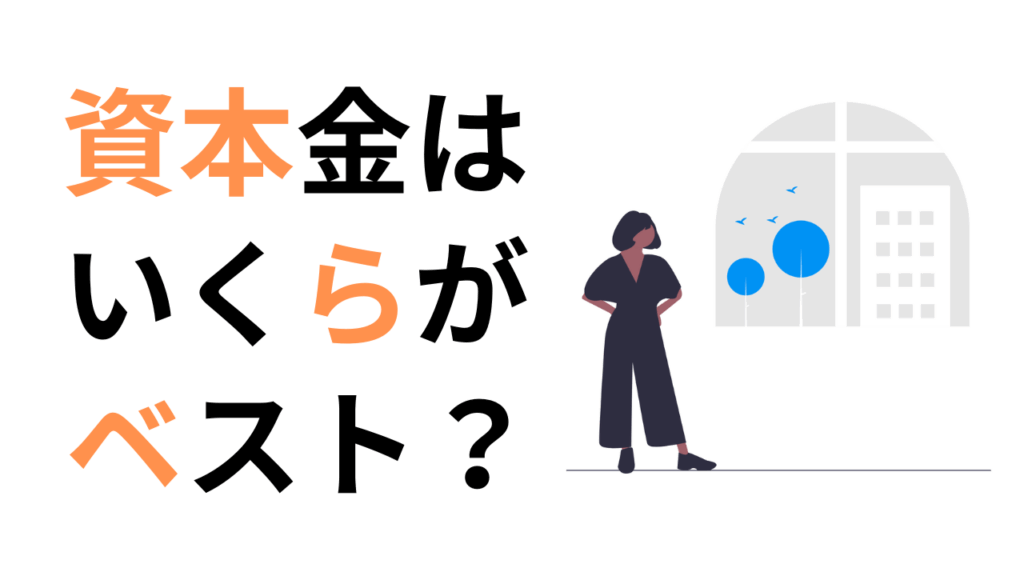🏢はじめに:資本金とは?会社設立時に考えるべき理由
会社を設立する際、最初に直面する大きな決断のひとつが「資本金をいくらにするか」という問題です。資本金とは、会社が事業を始めるための元手であり、設立時に出資される金額のことを指します。これは単なるスタート資金ではなく、会社の信用力や税務負担、融資の可否、さらには補助金の対象かどうかにも影響する、非常に重要な要素です。
2006年の会社法改正により、資本金1円からでも会社設立が可能となりましたが、実際には「いくらでもいい」というわけではありません。資本金が少なすぎると、事業の継続性や外部からの信用に不安が生じることもあります。一方で、資本金が多すぎると税金や手数料の負担が重くなる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
この記事では、資本金の適正額を見極めるためのポイントや、実際の企業の傾向、税務・許認可・補助金との関係などをわかりやすく解説していきます。これから会社設立を考えている方が、資本金設定で後悔しないための判断材料を提供することが目的です。
📊資本金の現状と傾向:多くの企業が選ぶ金額帯とは
会社設立時に設定される資本金額には、ある程度の傾向があります。弊社へ創業支援に来られる方の場合、最も多い資本金額は「100万円〜299万円」で、全体の約3分の1を占めています。さらに、約2/3の会社が「300万円未満」で設立されていらっしゃいます。つまり、実社会においてはこれが実務上の現実的なラインだということです。
また、総務省の「令和3年経済センサス‐活動調査」によれば、資本金300万円未満の会社は年々増加傾向にあります。特に常用雇用者が0〜4名の小規模企業では、資本金300万円未満の割合が前回調査から約2倍に増えており、設立時の資本金を抑える流れが強まっていることがわかります。
一方で、資本金100万円未満で設立される会社も約30%存在しています。これは、すでに個人事業主として事業経験がある方や、ネットショップ・コンサル業など初期投資が少ない業種に多く見られます。自宅で事業を行う場合や、スマホ・パソコン1台で完結する業態では、資本金を抑えても十分に事業が成立するケースもあるのです。
しかし、資本金が少ないからといって安易に設定してしまうと、後々の融資申請や信用調査、税務負担などに影響が出る可能性があります。次章では、資本金を決める際に考慮すべき4つの基準について詳しく解説していきます。
🎯資本金の決め方:4つの基準で考える
資本金は「とりあえず決める」ものではありません。事業の安定性、税務負担、許認可の取得、補助金の活用など、さまざまな要素に影響するため、戦略的に設定する必要があります。ここでは、資本金を決める際に押さえておきたい4つの基準について解説します。
①運転資金・初期投資額から逆算する
会社設立後、すぐに売上が立つとは限りません。特に創業初期は「利益が出にくい期間」が続くこともあります。そのため、資本金は初期投資額に加えて、最低でも3〜6ヶ月分の運転資金を見込んで設定するのが理想です。
例えば、事務所の賃料、従業員の給与、光熱費、通信費など、毎月かかる固定費を計算し、それに初期設備投資(パソコン、什器など)を加えた金額が資本金の目安になります。
資本金が不足すると、経営者が個人資金を会社に融通する「役員借入金」が発生し、貸借対照表上の負債が増加。結果として自己資本比率が下がり、会社の信用力に悪影響を及ぼす可能性があります。
②税金・手数料の負担を見越す
資本金の額によって、会社設立時や運営中にかかる税金・手数料が変わります。たとえば:
- 定款認証手数料:100万円未満なら3万円、300万円以上なら一律5万円
- 登録免許税:株式会社は資本金の0.7%(最低15万円)
- 消費税:資本金1,000万円以上だと設立初年度から課税対象
- 法人税:資本金1億円以下なら800万円までの所得に軽減税率(15%)が適用
- 法人住民税・事業税:資本金額と従業員数に応じて均等割が変動
つまり、資本金が高すぎると税務負担が増える可能性があるため、事業規模に見合った金額設定が重要です。
③許認可の取得要件を確認する
特定の業種では、行政からの許認可を得るために一定以上の資本金が必要です。たとえば:
- 人材派遣業:2,000万円以上
- 有料職業紹介業:500万円以上
- 旅行業(第1種):3,000万円以上
- 建設業(特定):2,000万円以上+自己資本4,000万円以上
許認可の取得が事業のスタートに不可欠な場合は、資本金額がその条件を満たしているか事前に確認しておきましょう。
④補助金・助成金の対象条件を満たす
行政が提供する補助金や助成金の中には、資本金額によって対象企業が限定されるものがあります。特に中小企業向け制度では、業種ごとに資本金の上限が定められています。
例として:
| 業種 | 中小企業の資本金要件 |
|---|---|
| 小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 |
補助金を活用したい場合は、資本金が上限を超えないよう注意が必要です。
これら4つの基準をもとに、資本金は「事業の実態」と「将来の展望」に合わせて戦略的に設定することが大切です。次章では、実務的な観点から資本金を決める際のポイントをさらに掘り下げていきます。
資本金は多ければ多いほど、社会的信用が高まるのでその方がいいのではとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
しかし実際は、資本金や従業員数を一つの目安に企業の規模を定義し、資本金や従業員数が少ない中小や零細企業のみを支援する補助金や助成金などの支援制度がいくつもあります。
つまり資本金が少ない方がお得の場合もある訳です。
税制・行政からの支援・銀行等からの信用・従業員からの信頼など様々な側面をよく理解した上で資本金を決定することをオススメ致します。
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
🧮資本金を決める際の実務的なポイント
資本金の設定は、単なる数字の問題ではなく、事業の信頼性や資金調達の可能性に直結する「戦略的な判断」です。ここでは、実務上よく検討される5つのポイントを整理してご紹介します。
1. 節税目的で1,000万円未満にする
※下記に関しては、随時税制が変更されていますので、ご自身で最新情報をご確認下さい。
1)会社設立時の資本金が1,000万円未満であれば、消費税の免税特例が適用される可能性があります。これにより、設立初年度と翌年度の最大2年間、消費税の納税義務が免除されるケースがあります。
さらに、2)法人住民税の均等割も資本金1,000万円未満であれば年間7万円程度に抑えられますが、1,000万円を超えると18万円以上になるため、税負担が大きく変わります。特段の理由がなければ、資本金は1,000万円未満に設定するのが一般的です。
2. 銀行口座開設には100万円以上が望ましい
実店舗を持つメガバンクなどで法人口座を開設したい場合、資本金が100万円未満だと審査で不利になることがあります。銀行は資本金を企業の信用力の一つとして見ており、極端に少ない資本金では「事業の継続性」に疑問を持たれることも。
特に近年では、資本金が低すぎる法人に対して口座開設を断るケースも報告されているため、最低でも100万円以上の資本金を設定することが望ましいです。
3. 融資を希望するなら100万円以上が必要
創業時に公的機関や金融機関から融資を受けたい場合、資本金は会社の体力を示す指標になります。資本金が少ないと、返済能力が低いと判断され、希望通りの融資が受けられない可能性があります。
また、資本金は信用調査の対象項目でもあるため、取引先を増やしたいと考えている場合にも重要です。たとえば、同条件の提案を「資本金1万円の会社」と「資本金300万円の会社」が行った場合、後者の方が信用されやすいのは言うまでもありません。
4. 許認可取得には最低資本金額の確認が必須
前章でも触れた通り、業種によっては行政からの許認可取得に一定以上の資本金が必要です。たとえば:
- 人材派遣業:2,000万円以上
- 第1種旅行業:3,000万円以上
- 特定建設業:2,000万円以上+自己資本4,000万円以上
これらの事業を予定している場合は、資本金額が要件を満たしているか事前に確認しておく必要があります。
5. 初期費用+3ヶ月分の運転資金を見積もる
資本金は、事業開始後の資金繰りを安定させるためにも重要です。事務所の賃料、設備投資、人件費、光熱費などを含めた初期費用に加え、最低3ヶ月分の運転資金を確保できる額を資本金として設定するのが理想です。
仮に売上が立たない期間が続いても、資本金で事業を維持できる体力があれば、外部からの借入に頼らずに済み、会社の財務健全性を保つことができます。
これらの実務的な視点を踏まえることで、資本金は単なる「設立のための数字」ではなく、事業の信頼性と持続性を支える「経営戦略の一部」であることが理解できるはずです。
💡資本金1円でも設立できる?そのメリットと注意点
2006年の会社法改正により、株式会社でも資本金1円から設立できるようになりました。これは「誰でも起業できる社会」を目指した制度改革の一環であり、実際に「1円起業」という言葉が話題になった時期もあります。しかし、資本金1円での設立にはメリットと同時に、見過ごせないリスクも存在します。
メリット:資金が少なくても法人化できる
資本金1円で会社を設立する最大のメリットは、初期費用を抑えられることです。特に以下のようなケースでは、少額資本金でも事業が成立しやすい傾向があります。
- すでに個人事業主として事業を行っている
- 設備投資が不要なコンサル業やネットショップなどを運営している
- 自宅で事業を行い、オフィスを借りる必要がない
- 新規の取引先や人材採用を積極的に行う予定がない
このような事業形態であれば、資本金を抑えても法人化のメリット(信用力の向上、税務上の優遇など)を享受することが可能です。
デメリット:信用力・資金繰り・採用面での不利
一方で、資本金1円での設立には明確なデメリットもあります。
- 債務超過になりやすい:少額資本金では、ちょっとした支出でもすぐに資産を上回る負債が発生し、財務的に不安定になります
- 社会的信用度が低くなる:取引先や金融機関から「本気度が低い」「継続性に不安がある」と見られる可能性があります
- 銀行口座の開設が難しくなる:特にメガバンクでは、資本金が極端に少ない法人に対して口座開設を断るケースも
- 人材採用が困難になる:求職者から見て「資本金1円の会社」は安定性に欠ける印象を与えやすく、採用活動に影響することも
1円起業は誰に向いているか
資本金1円での設立は、すべての起業家に適しているわけではありません。以下のような方には向いている可能性があります。
- すでに事業経験があり、法人化は形式的なステップである
- 自己資金で十分に事業を回せる見込みがある
- 外部からの融資や補助金の活用を考えていない
- 信用力よりもスピード重視で法人化したい
ただし、これらに該当する場合でも、専門家に相談したうえで慎重に判断することが重要です。資本金の設定は、設立後の経営に長く影響を与えるため、安易な決定は避けましょう。
💼資本金100万円未満でも設立できるケースとは
資本金は多ければ安心、少なければ不安——そんなイメージを持たれがちですが、実際には資本金100万円未満で設立されている会社も数多く存在します。では、なぜこのような少額資本金での設立が可能なのでしょうか。その背景には、事業内容や運営スタイルに応じた合理的な判断があります。
少額資本金でも成立する事業の特徴
以下のような事業形態では、資本金を抑えても十分に事業が成り立つケースが多く見られます。
- すでに個人事業主としての経験がある
法人化は形式的なステップであり、事業の基盤がすでに整っているため、資本金を多く設定する必要がない - コンサルティング業やネットショップなど、設備投資が少ない業種
仕入れや店舗が不要で、パソコン1台で完結するような業態では、初期費用も少額で済む - 自宅で事業を行うため、オフィス賃料が不要
固定費が抑えられるため、運転資金も少なくて済む
このような事業では、資本金を100万円未満に設定しても、資金繰りや信用面で大きな問題が生じにくいのです。
注意点:少額資本金でも戦略的に
ただし、資本金が少ないことによるリスクはゼロではありません。融資を受けたい場合や、メガバンクで口座を開設したい場合、または新規の取引先との信用構築を重視する場合には、資本金が少ないことで不利になる可能性があります。
そのため、資本金を100万円未満に設定する場合でも、事業の性質・将来の展望・外部との関係性を十分に考慮したうえで判断することが重要です。
📈総務省の調査から見る資本金のトレンド
資本金の設定に関する実態は、総務省が実施した「令和3年経済センサス‐活動調査」によって、より鮮明に見えてきます。この調査では、全国約18万社の資本金額が分類されており、特に小規模事業者(常用雇用者0〜4名)における資本金の傾向が注目されています。
資本金300万円未満の会社が増加中
調査によると、資本金300万円未満の会社は2016年時点で約6.5%だったのに対し、2021年には約11.3%にまで増加しています。これは、会社法改正によって設立のハードルが下がったことや、少額資本金でも成立する業態が増えていることが背景にあります。
特に小規模企業に絞って見ると、資本金300万円未満の割合は約14.2%とさらに高く、前回調査からほぼ倍増しています。これは、個人事業主の法人化や、フリーランスからのステップアップとして会社設立を選ぶケースが増えていることを示しています。
資本金の分布と事業規模の関係
資本金の分布を見ると、300〜500万円未満の会社が最も多く、次いで500〜1,000万円未満、1,000〜3,000万円未満と続きます。これは、ある程度の初期投資や運転資金を見込んだうえで、税務上のメリットを考慮した設定が多いことを示しています。
一方で、資本金5,000万円以上の会社は全体のわずか0.13%程度であり、これは大企業や特定業種に限られたケースです。中小企業の大半は、資本金1,000万円未満で設立されているのが現状です。
トレンドから見える「適正額」のヒント
このような統計から見えてくるのは、資本金は事業規模や業種、設立目的に応じて柔軟に設定されているということです。特に小規模事業者にとっては、資本金300万円未満でも十分に事業が成立する環境が整ってきており、無理に高額を設定する必要はありません。
ただし、融資・補助金・信用力などを考慮する場合は、最低でも100万円以上の設定が望ましいとされる傾向もあります。次章では、これまでの内容を踏まえ、資本金設定のまとめと戦略的な考え方について整理していきます。
🧭まとめ:資本金は“戦略的に”決めるべき
会社設立時の資本金は、単なるスタート資金ではなく、事業の信頼性・資金繰り・税務負担・制度活用など、あらゆる側面に影響を与える重要な要素です。法律上は1円からでも設立可能ですが、現実的には「事業の実態に即した金額」を慎重に設定する必要があります。
ここまで見てきたように、資本金を決める際には以下の視点が欠かせません:
- 運転資金・初期投資額:最低でも3〜6ヶ月分の資金を見積もる
- 税金・手数料の負担:資本金1,000万円以上で消費税免除が受けられなくなるなど、節税の観点も重要
- 許認可の取得要件:業種によっては最低資本金額が定められている
- 補助金・助成金の対象条件:資本金額によって制度の利用可否が分かれる
- 信用力・融資・採用:資本金が少なすぎると外部からの評価に影響する
また、総務省の調査などからも、資本金100〜299万円で設立する企業が最も多いという現実が見えてきました。これは、税務・信用・資金計画のバランスを取った「現実的なライン」と言えるでしょう。
資本金は一度決めると変更に手間がかかるため、設立前にしっかりとシミュレーションを行い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
最後に、資本金の設定や補助金・融資の活用に関心のある方に向けて、実務に役立つ講座をご紹介します。起業支援やコンサルタントとしてのステップアップを目指す方にとって、非常に有益な内容です。
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
士業やコンサルとして中小・零細企業の社長様から要望の多い補助金支援業務について学びたい方はこちら。補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。