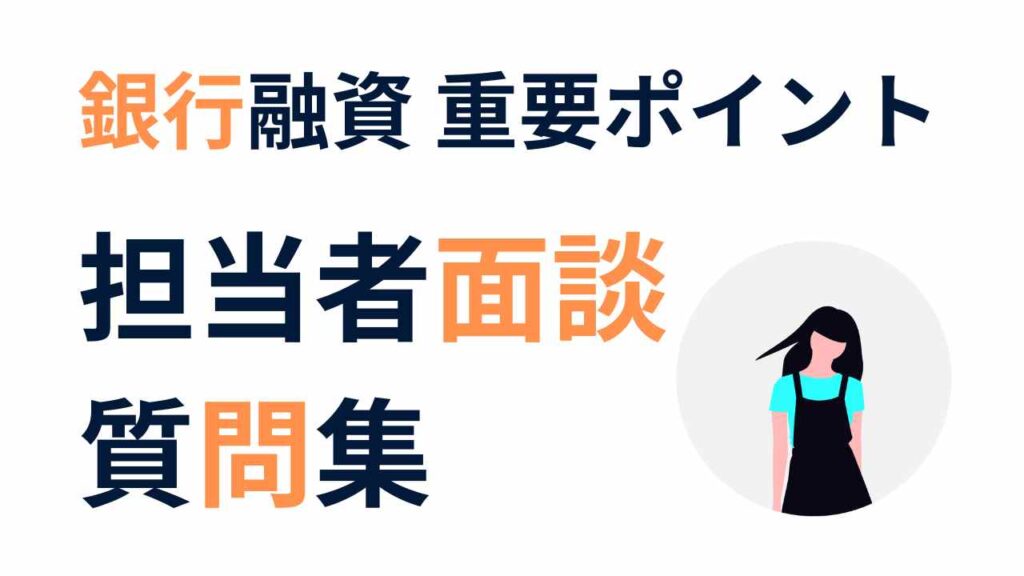創業融資面談の重要性とは?
創業という大きな一歩を踏み出す際、金融機関からの創業融資は事業の土台づくりに欠かせない資金源です。特に日本政策金融公庫などの創業融資では、申込後に「面談」が行われることが一般的。この面談は、事業の信頼性と経営者の資質が審査される大切なプロセスです。
失敗しないためには、事前準備と心構えが鍵を握ります。本記事では面談に必要な書類や想定問答、注意事項までを総まとめ。初心者の方でも安心して臨めるよう、分かりやすく解説します。
🗂事前に準備すべき書類
創業融資の面談は、単なる「話し合い」ではありません。我々申請者側は審査されます。持参する書類は審査の重要な判断材料となるため、しっかり整えておきましょう。
面談時に持参したい基本書類
※ご自身に必要なそれぞれ書類は異なります。
- 本人確認書類:運転免許証、パスポート、在留カード・特別永住者証明書(外国籍の方)など
- 自己資金を証明する書類:預金通帳(原本)(ネットバンキングなど紙の通帳が無い場合はPCやスマホなどでも可)、生命保険の保険証券など
- 勤務時の収入を示すもの:源泉徴収票(現在従業員として働いている場合)、確定申告書(個人事業主など)など
- 借入金の返済予定がわかる書類:資金繰り表、返済予定表、残高証明書など
- 支払いの履歴がわかる資料:クレジットカードの明細、公共料金の領収書
- 納税関連の書類:県民税の領収書、納税証明書、固定資産課税証明書など
- 資格証明書:資格が必要な事業を行う場合
- 許認可証:許認可が必要な事業を行う場合
- 不動産の賃貸借契約書:店舗や事務所の賃貸が事業運営上必要不可欠とされる場合など
営業を始める際に、行政から許認可が必要な主な業種を、申請窓口ごとにリストアップしました。自分のビジネスに関する許認可について事前にお調べになっていない方はご活用下さい。
【重要】必要な許認可を受けていない(受ける予定の無い)事業に対して、銀行は融資をしませんのご注意下さい。
※一部の業種では一定以上の売上となる業務を受注する場合に許認可が必要となる場合などあり
※複数の許認可が必要な業種あり(例:コンビニは食品、酒類、タバコなどの許認可が必要)
🏢 保健所が窓口の業種
- 飲食店:レストラン、居酒屋、カフェなど
- 食品製造・販売業:パン屋、弁当屋、八百屋、コンビニなど
- 宿泊業:ホテル、旅館、民宿
- 医療業:診療所、歯科、助産所
- 理容・美容業:理容室、美容室、まつエクサロンなど
- 洗濯業:クリーニング店、リネンサプライ
🚓 警察署が窓口の業種
- 接待を伴う飲食業:キャバレー、ホストクラブ、ラウンジなど
- 遊技場営業:パチンコ店、ゲームセンター、麻雀クラブ
- 古物営業:リサイクルショップ、古本屋、中古車販売
- 深夜酒類提供飲食店:午前0時〜6時に営業するバーなど
- 探偵業・警備業・運転代行業
🏛 都道府県庁・その他の行政機関が窓口の業種
たばこ小売業:たばこ販売店、シーシャバー(JT)
医薬品・化粧品販売業:薬局、ドラッグストア
公衆浴場業:銭湯、温泉、サウナ
興行場営業:映画館、劇場、ライブハウス
学校・保育施設:幼稚園、保育所、ベビーシッター
介護事業:訪問介護、入浴介護
住宅宿泊事業:民泊(年間180日以内)
動物取扱業:ペットショップ、動物園、猫カフェ
旅行業:旅行代理店、手配業者
宅地建物取引業:不動産仲介・販売
建設業・電気工事業
貸金業:消費者金融など
酒類製造・販売業:酒蔵、酒屋(税務署が窓口)
職業紹介業:人材派遣・転職エージェント(ハローワーク)
運送業・倉庫業:トラック運送、タクシー、バス、倉庫業(運輸局)
上記を含め銀行側から事前に指示された書類は必ず持参するようにしましょう。なお、依頼された書類が用意出来ない場合は担当者へ「事前に」その旨を必ず連絡しましょう。
プラス材料となる「追加書類」の例
◆商品の情報が分かる資料:試作品、メニュー表、仕入先との事前契約書、店内の様子(間取り、店内写真、商品写真など)、商品やサービスが分かるもの(例:商品を持参、本事業で提供予定のアプリを面談時に提示するなど)商標・特許などを証明する書類など
◆今後の見通しがわかる書類:新店物件のマイソク、契約書、図面、販売先(仮)契約書、卸先(仮)契約書(合意書)、資金繰り表、損益計算書など
◆市場分析に関する資料:業界レポート、アンケート調査結果表、商圏内競合他社の分析結果など
これらの資料は提出が必須ではありませんが、事業の実現性や計画性を補強する役割を果たします。但し、追加書類の持参が許可されない場合もありますので、追加資料の提出を希望する場合は、必ず事前に担当者の許可を取りましょう。
❓創業融資面談で想定される質問とは?
面談では、審査担当者から多岐にわたる質問が投げかけられます。回答に困らないよう、想定問答をあらかじめ準備しておくのが賢明です。
よくある質問一覧
- 経営者について
「創業の動機は?」「これまでの経歴は?」「家族構成は?」
※具体的な質問
「なぜこの地で創業する必要があるかお聞かせ下さい」
「創業する目的について教えてください」
「創業を通して社会にどのような影響を与えたいですか?」 - 事業内容について
「集客方法は?」「この事業の強みは?」「外注先との関係性は?」
※具体的な質問
「取得されている資格がどのようにこの事業に生かされるのか具体的に教えてください」
「経歴や職歴を通してどのような強みをお持ちですか?」
「取り扱う商品・サービスはどのようなものですか?」
「この事業のセールスポイントや競合他社との違いはどこにありますか?」
「仕入れ先や販売先について具体的に教えてください」 - 支払状況や借入の有無について
「他に借入はあるか?」「支払遅延の履歴は?」「税金滞納は?」
※具体的な質問
「現在、他の金融機関などからお借入れはありますか?」 - 資金調達計画について
「必要資金はいくらか?」「借入ができなければどうする?」「自己資金の準備方法は?」
※具体的な質問
「今回準備なさった自己資金〇〇万円はどのようにして用意されましたか?」
「この事業を始めるにあたって最低限必要な資金はいくらですか?」 - 今後の見通しについて
「売上の根拠は?」「計画未達の場合の対応は?」「人材確保の戦略は?」
※具体的な質問
「常勤する人数は何人ですか?」
「何人雇われる予定ですか?」
「販売先予定のA社との現在の状況と数値計画などあれば教えて下さい」
「いつ頃から黒字化されるとお考えですか?」
💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ
実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。
👉 詳しくはこちら
「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ
→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp
👤 面談には「経営者一人」で臨むのが原則—あなたの言葉で未来を語ろう
創業融資の面談は、銀行があなた自身の思いを直接聞く場です。そのため、経営者本人が単独で面談に臨むことが原則とされています。
🔍 なぜ「一人」で臨むのか?
◆プライバシーに関する質問があるため
収入状況、他の借入、生活費の支出など、個人的な内容を聞かれることがあります。第三者が同席すると話しにくくなる可能性もあるため、原則として一人での面談が推奨されます。
◆事業の内容は“本人の言葉”で語るべきだから
銀行は数字だけでなく、あなたの熱意や価値観、課題に対する考え方を重視しています。「どんな想いでこの事業を始めたのか」「将来どうしていきたいのか」といった問いに、自分の言葉で答えることが信頼につながります。
👥 例外的に同席が認められる場合も
- 配偶者が重要な支援者・共同出資者である場合
- 事業パートナーとの共同経営で、両者の役割が明確な場合
- 担当者が同席を問題なしと判断した場合
当社からのアドバイス:
同席を希望する場合は、事前に銀行担当者にその旨を伝えましょう。面談当日になって「同席はNG」と言われないよう、必ず確認をしましょう。
ちなみに、過去の経験では弊社のような経営コンサルタントの同席は基本的に認められません。
👔 面談時の「身だしなみ」も印象アップのカギ!見落としがちなポイントとは?
面談時の第一印象は、意外と審査の「空気感」に影響します。銀行担当者はあなた自身だけでなく、“事業者としての信頼感”も見ています。服装や振る舞いを少し意識するだけで、面談全体の雰囲気が前向きになります。
🧼 身だしなみチェックポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ビジネスマナー | ・名刺交換はテーブル越しではなく、立って丁寧に ・敬語に自信がなければ「丁寧な口調」でも十分 ・スマートフォンは必ずマナーモードにし、テーブル上に置かない |
| 服装の清潔感 | ・シャツやジャケットはシワのないものを選ぶ ・靴も磨いておくと印象アップ ・香水・整髪料は控えめに |
| 表情と姿勢 | ・笑顔は緊張を和らげる最大の武器 ・背筋を伸ばして座るだけでも自信と誠意が伝わる |
📌 服装はスーツが必須ではありませんが、“清潔感”と“誠実さ”が伝わるコーディネートを心がけましょう。
💡 不安な方は、面談当日の服装を家族や知人に見てもらい、「どう思う?」と聞いてみると客観的な気づきが得られます。
🏢 面談場所の確認は忘れずに!意外と見落としがちな準備ポイント
創業融資の面談は、銀行支店内で行われるケースがほとんどですが、事業内容や状況によっては、別の場所で行われることもあります。場所によって、準備すべき資料や環境が変わるため、事前確認はとても重要です。
🏦 銀行内での面談(一般的なケース)
- 会議室や応接室など、静かなスペースが使われます
- 必要書類はクリアファイルなどにまとめて持参しましょう
- 対話形式で進むため、メモ帳や筆記具もあると便利です
🏪 店舗・事務所での面談(イレギュラーなケース)
以下のような理由で、申請者側の施設で面談を銀行側が希望する場合があります:
- 営業実態を確認したい場合(特に飲食店・美容室など)
- 担当者の移動の都合上、現地の方がスムーズな場合など
⚠️ 施設が未完成の場合は?
- その旨を銀行に事前に伝える
- 写真・資料・図面などを用意して、完成後のイメージや計画をしっかり伝える
- 仮設の什器やレイアウトでも“説明できる準備”があればOKです
📌 「現地で面談したい」と言われた時点で、室内の掃除や案内動線も整えておくと、印象アップにつながります。また、施設が未完成で面談を出来る状態でない場合などは、事前に銀行側にその旨を伝え別の場所での面談を希望しましょう。
⏱面談当日の流れ:銀行担当者との“はじめての対話”を味方に
創業融資の面談は「試験」ではありません。銀行の担当者があなたの人柄や事業への思いをじっくり聞き、融資の可否を検討するための重要な時間です。緊張するのは当然ですが、事前に準備すれば安心して臨めます。ここでは、一般的な面談の流れと、心構えのポイントをわかりやすくご紹介します。
⏳ 所要時間の目安:30分〜1時間
時間に余裕を持って到着しましょう。面談場所は銀行の応接室など静かな場所で行われることが多く、対話は和やかな雰囲気のなか進む場合がほとんどです。
🗣【前半】あなたの想いや事業の背景を語る時間(約10〜15分)
面談の冒頭では、担当者があなたの人物像や事業に対する熱意を知るための質問をします。
- 自己紹介
・氏名、年齢、出身地、職歴などを簡潔に紹介しましょう
・これまでのキャリアが事業にどう活かされるかを伝えると好印象です - 創業のきっかけと理由
・「なぜこの事業を始めたいのか」「何を解決したいのか」
・あなた自身の経験、出会い、課題意識などを具体的に伝えると、想いが伝わります - 事業内容の説明
・どんなサービス/商品を提供するのか
・ターゲット顧客、収益の仕組み、差別化ポイントなど
・図表や事業計画書を活用すると理解が深まります
📌 ポイント:担当者はあなたの“情熱”と“現実的な視点”の両方を見ています。熱くなりすぎず、冷静に語りましょう。
📈【後半】事業の具体性と計画性を伝える時間(約15〜20分)
ここでは、融資を受ける目的や資金使途、今後の見通しについてより具体的に話します。
- 販売戦略と市場分析
・どうやって顧客を獲得するか?競合とどう差別化するか?
・地域性、価格設定、プロモーションなどを丁寧に説明しましょう - 収支計画(1年・3〜5年・将来)
・売上予測、原価、固定費、利益などを時系列で説明します
・実現可能な数字であることが重視されます - 資金計画(同上)
・創業に必要な金額と内訳、自己資金との比率
・融資希望額、返済計画の妥当性も説明できるよう準備しておきましょう - 質疑応答
・面談官からの質問には落ち着いて答えましょう
・わからないことがあっても「調べて後日回答します」と誠実な姿勢でOKです
📌 ポイント:数字やプランだけでなく、“根拠”や“あなた自身の言葉”が大切です。
当社からのアドバイス:
創業時は、すべての事業者にとって極めて有利なタイミングです。
通常、銀行から融資を受ける場合、過去の売上や経費などの実績を基に、将来の収支予測を立て、それに応じた融資可能額やリスクを判断されます。
しかし創業段階では、まだ販売や運営の実績がないため、例外的に「社長のビジョン(予測)」を銀行側がある程度信じてくれる状況が生まれます。
この特別な状況を最大限に活かし、自身が希望する融資額を獲得できるよう、面談では自社の強みや差別化ポイントをしっかりとアピールすることが重要です。
🌟面談を成功させるためのちょっとしたコツ
- 事前に練習しておくと安心です:友人や家族に面談役を頼み、話す内容を一度通してみましょう
- 事業計画書を紙で持参する:説明時に使えるだけでなく、担当者の印象にも残ります
- 服装は清潔感を重視して:スーツである必要はありませんが、誠実さを感じさせる装いがおすすめです
✅まとめ:面談成功の鍵は「準備と誠実さ」
創業融資面談において求められるのは「事業への本気度」と「計画性」。面談はあなたのビジョンを直接伝える貴重な機会です。
◆必要書類は抜けなく準備
◆想定問答で心の準備を
◆清潔感のある対応で好印象を
◆面談日時や場所を事前に確認
本記事を参考に、万全の準備で面談に臨み、創業への一歩を確かなものにしていきましょう。
補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内
補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。
この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。